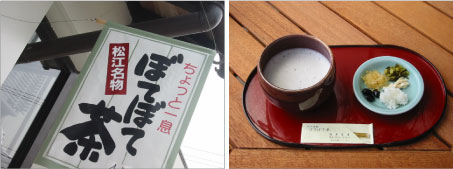□出雲大社は今回の旅の最重要課題だった。祀神は先の白兎海岸でふれた大国主。七福神の大黒であり、建速須佐之男の娘、須勢理毘売を正妻に持ち、この国を初めて治めた神。
タケダの愛読書「古事記」に大国主が須勢理毘売をつれて根の国を出る際、建速須佐之男が大国主にむけてこう叫ぶ場面
がある。いいか須勢理毘売といっしょにくらすならな、立派な神殿を建てなければならないぞ。よく聞けよ。出雲の地にはな、海に向かう宇賀の山があるだろう、その山のふもとに、宮をつくるんだ。深く深く、地面
に穴を掘ってな、その中にがんじょうな土台石を埋めるんだ。その穴にな、太い太い柱を、しっかりと据えつけるんだ。高い屋根をつけろよ。屋根の両端につける千木はな、高く高くしろよ。高く高くして高天原にとどくようにするんだ。そして、幸せに暮らせよ。いいなぁ、こにくらしい若造め。わかったなぁ。