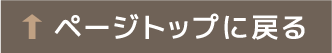�⌾�E�����E�����c�ƁE���F�E�_�E�y�����Ԗ��`�ύX�E�Ԍɏؖ�
�s�����m���茛�펖����
�@�@���쌧�ۋT�s�S�ƒ��Q�W�T�|�T
���C�y�ɂ��d�b�������B
0877-89-3297

����

�@����l�i�푊���l�j�̎��S�ɂ���đ����͊J�n���܂��B
�@�⌾����������⌾�ɏ]���A�Ȃ���Α����l�̋��c�ɂ���Y�̕��������肵�܂��B
�@���S�ɂ́A���H�鍐�ɂ�莀�S�������̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ�ꍇ���܂܂�܂��B
�@�푊���l�����S�����ꍇ�A�����J�n�̎�����A�푊���l�̍��Y�ɑ�������̌����`���i��g�ɐꑮ���Ă������́A�Ⴆ�Ύ��i��Ƌ��A�����ی�����Ȃǂ������j�����͈͂̐e���i�����l�j�Ɍp������܂��B
�����l
�@�����l�Ƃ́A�푊���l�̍��Y���p���l�������܂��B
�@�����l�ɂȂ��ҋy�т��̏��ʂ͖��@�ɂ���Ē�߂��Ă��܂��B
�@�v���X�̍��Y�����ł͂Ȃ��A�}�C�i�X�̍��Y����������܂��B
�@�����̒P�����F�A�����A���菳�F�́A�����Ƃ��āA�����l�����Ȃ̂��߂ɑ����̊J�n�����������Ƃ�m����������R�J���ȓ��ɂ��Ȃ���A�P�����F�������̂Ƃ݂Ȃ���܂��B
���@���菳�F�͑����l���S���ōs��Ȃ���Ȃ�܂���B
| �z��� | �z��҂͏�ɑ����l�ƂȂ�܂��B ���@�����̔z��҂͊܂܂�܂���B |
| ��P���� | �푊���l�̎q
�i���q�E�{�q�E���o�q�E�o�q��₢�܂���B�j ���@�����̎q�����鎞�́A�����ɑ������܂��B ���@�َ��ɂ����������F�߂��܂��B |
| ��Q���� | ���n���� ���@�e���̋߂����̂��D�悵�܂��B |
| ��R���� | �Z��o�� �푊���l�Ɏq�E���n���������Ȃ��ꍇ�ɂ͌Z��o���ƂȂ�܂��B ���@����̈����������Z��o���́A�����������Z�� �o���̑������̔����ƂȂ�܂��B |
���@���i���R�ɊY��������A�����p�����ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����l�Ƃ͂Ȃ�܂���B
���@��������������Ƃ��̎҂̎q�i���j�͑�P�����ł��܂���B���i�E�p���̏ꍇ��
���̎҂̎q�i���j�͑�P�����ł��܂��B
���@�Z��o���̎q�i�����E�߂��j�͑�P�����ł��܂����A���̎q�i�����E�߂��j�̎q�͑�P�����ł��܂���B
���@�{�q�̘A��q�́A��P�����ł��܂���B
���@��Ȃ̘A��q�ɂ́A�������͂���܂���B�i�{�q���g�����Ă���ꍇ�ɂ͑������͂���܂��B�j
�@
�@�葊����
�@�@�葊�����́A���@�i��900���j�ɋK�肳��Ă��܂��B
| �� �� �� �� | �� �� �l | �� �� �� |
| ��P���� | �z��� �q | �Q���̂P �Q���̂P |
| ��Q���� | �z��� ���n���� | �R���̂Q �R���̂P |
| ��R���� | �z��� �Z��o�� | �S���̂R �S���̂P |
���@�q�A���n�����A�Z��o������������ꍇ�́A���̐l���œ�������܂��B
��Y����
�@�⌾�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���������l�̘b�������ɂ���Ĉ�Y�����܂��B
�@�����J�n�ƂƂ��ɁA��Y�͋��L���`�ƂȂ��Ă��邽�߁A�e���̎������m�肷�邽�߂ɍs���܂��B
�@�O��Ƃ��āA
�@�@�@�@�����l�̊m��
�@�@�A�@�������Y�̒���
�@�@�B�@�������Y�̎Z��
�@�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@��Y�������c�ɂ́A�K�������ґS�����o�Ȃ�����ŋ��c���s��Ȃ���Ζ����ƂȂ�܂��B
�@���������l�̒��������N���i�e���҂������l�ł���Ƃ��j�A�F�m�ǂ̎��A�s���s����������ꍇ�ɂ͖{�l�͋��c�ł��܂���̂ŁA���ʑ㗝�l�A���N�㌩�l�A�s�ݎҍ��Y�Ǘ��l�̑I�C�̐\���ĂȂǂ��K�v�ƂȂ�܂��B
�@���c�̌��ʁA�S�������ӂ�������c�͐������܂��B
�@���c������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ƒ�ٔ����Ɉ�Y�����̐R����\���āA�����R���ɂ���ĕ������Ȃ���܂��B
�@�����Q�X�N�x�ɉƒ�ٔ����Ɏ������܂ꂽ�����A�P�Q�C�P�P�U��
�@��Y���z�A�P�O�O�O���~�ȉ�����R�Q���A�P�O�O�O���~���T�O�O�O���~�ȉ�����S�R��
�@�W����������l�̐��A�Q�l����Q�R���A�R�l����Q�V���A�S�l����P�W��
�@��Y�̋��z�����Ȃ��A�����l�̐������Ȃ��Ă���Y���߂����Ă̑����͋N���肤��̂ł��B
�@�܂��́A�⌾���D�悳��܂��̂ŁA�o���邾���e���Ԃő���Ȃ��ł��ނ悤�Ɉ⌾���͕K�v���Ǝv���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�⌾��
�◯���Ƃ�
�@�◯���Ƃ́A�푊���l�̈⌾�ɂ���Ă��N�����Ƃ̂ł��Ȃ��A�@�葊���l�������Ɋւ��ĕۏႳ��Ă���Œ���̍��Y���ƁB
�@�����A�⌾�ő����l�ȊO�̑�O�҂ɑS���Y���②�����Ƃ��Ă��A�����l�͈②�̍��Y�̈ꕔ�����߂����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B
�@�◯���́A���n�����݂̂������l�ł���ꍇ�ɂ͔푊���l�̍��Y�̂P/�R�A���̑��̏ꍇ�͔푊���l�̍��Y�̂P/�Q�ƂȂ�܂��B
���@�◯�����N�Q����Ă��Ă��A�◯�����E���������Ȃ���Ύ��߂����Ƃ͂ł��܂���B
�@�Ȃ��A�◯�������҂��A�����̊J�n�y�ь��E���ׂ����^���͈②�����������Ƃ�m����������P�N�ԁA�܂������J�n����P�O�N�o�߂����Ƃ��ɂ͏��ł��܂��B
���@�◯�������҂́A�z��ҁE�q�i���n�ڑ��j�E�e�i���n�����j�ŁA�Z��o���ɂ͂���܂���B
�@�Ⴆ�A�����l���Z��o�������̏ꍇ�ŁA�L���Ȉ⌾���Ɂu�S���Y���O�҂Ɉ②����v�Ə����Ă����ꍇ�ɂ́A�S���Y�͑�O�҂̂��̂ƂȂ�A�Z��o���ɂ͑������ꂸ�A�◯�����Ȃ��̂ō��Y�����炤���Ƃ��o���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
| �����l | ������ | �◯�� |
| �z��҂̂� | �z��� | �Q���̂P |
| �q�̂� | �q | �Q���̂P |
| �z��҂� �q | �z��� �q | �S���̂P �S���̂P |
| �z��҂� ���n���� | �z��� ���n���� | �R���̂P �U���̂P |
| ���n�����̂� | ���n���� | �R���̂P |
| �z��҂� �Z��o�� | �z��� �Z��o�� | �Q���̂P �\ |
| �Z��o���̂� | �\ | �\ |
���@�q�A���n��������������ꍇ�́A���̐l���œ�������܂��B
�◯���Z��̊�b�ƂȂ���Y
�@�����Ƃ��Ĉ◯���́A�푊���l�������J�n���ɗL�������Y�̉��i�ɁA���̑����J�n�O�P�N�ԁi�����l�ȊO�j�ɂ������^�̍��Y�̉��i���������z������̑S�z�����������ĎZ�肵�܂��B
�@���@�����l�ɑ��鍥���A�{�q���g��s���Y�w���A��w�i�w�̂��߂Ȃǂ̑��^�́A���ʎ�v�Ƃ��Ċ��Ԃɂ�����炸���^�̉��i�Ɋ܂܂�܂��B
�@�◯���Z��̊�b�ƂȂ���Y�@��
�@�@�i�����J�n���̑������Y�j�{�i�����J�n�O�P�N�ȓ��̑��^�̉��i�j�|�i���j
�@��������ƂɈ◯���̊����Ōv�Z����܂��B
�◯�����E����
�@�◯����N�Q���鑡�^�E�②���Ȃ��ꂽ�ꍇ�ɁA�◯�������҂��◯�������߂����Ƃ��◯�����E�����Ƃ����܂��B
�@�◯����N�Q���Ă��鑊����ɑ��āA�◯���̕Ԋ҂̈ӎv�\��������Ό��͔͂������܂����A�؋��Ƃ��Ďc���Ă������߂ɓ��e�ؖ��X�֓��Ő������܂��B
�@�◯�������҂������̊J�n�y�ь��E���ׂ����^�܂��͈②�����������Ƃ�m����������P�N�ԍs�g���Ȃ��Ƃ��A�܂������J�n�̎�����P�O�N�o�߂����Ƃ��ɂ͏��ł��܂��B
���@���@�����ɂ��◯���N�Q�z�������ƂȂ�܂��B���K���ɂ�菈������܂��B
���@�����l�ɑ�����ʎ�v(�����E�{�q���g�̎��Q���A���v�̎��{�Ȃ�)�͑����J�n�O�P�O�N�Ԃɍs��ꂽ���̂Ɍ����܂��B(2019�N7��1���{�s)
���@�������ԂQ�O�N�ȏ�̔z��҂��A���Z�p�s���Y�^�E�②���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����߂��̖Ə������������̂Ɛ��肳��܂��B(��Y�����̍��Y�ɂ͊܂܂�Ȃ��B)(2019�N7��1���{�s)
����������
�@�����l�łȂ��ҁi�Ⴆ�Δp������Ă���l�j�ɂ���āA�{���̑����l�����̑�������N�Q����Ă���ꍇ�ɁA�N�Q���ꂽ�����l���W�Q��r�����A�������̉𐿋����錠���𑊑��������Ƃ����܂��B
���@�����l�܂��͂��̖@��㗝�l����������N�Q���ꂽ������m����������T�N�ԍs�g���Ȃ��Ƃ��A�܂������J�n�̎�����Q�O�N�o�߂����Ƃ��ɂ͏��ł��܂��B
�@
���ʂ̊�^
�@���������l�̒��ɁA�푊���l�̎��ƂɊւ���J���̒��͍��Y��̋��t�A�푊���l�̗×{�Ō삻�̑��̕��@�ɂ��푊���l�̍��Y�̈ێ����͑����ɂ��ē��ʂ̊�^�������҂ɕt������鑊�������F�߂���ꍇ������܂��B�i���@��904����2�j
���@���@�����ɂ��A����܂ł͑����l�ȊO�͔F�߂��Ȃ������A�U�e�����̐e��,�R�e�����̈����i�q�̔z��҂Ȃǁj�ɂ����ʊ�^�̐��������V�݂���܂��B(2019�N7��1���{�s)
���₢���킹�̓R�`���ցI
�d�b�ԍ��F 0877-89-3297
�g�ѓd�b�F 090-8695-4203
�܂��͂��C�y�ɂ����k�������B
�����[���ł̂��₢���킹