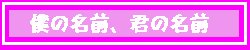
恋は突然降って来る
恋って…なんだろう?どうして突然襲われるのだろう…
学校の校庭で大きな声を出しながらサッカーをしている隣りのクラス。授業なのに張り切っているなぁ…と僕はぼんやり眺めていた。
ツンツン
背後から背中を突つかれたので右手をそっと後の机の下に伸ばす。いくつかに折り畳まれた紙片が渡される。
『昼休み、体育館の裏で円陣やろーぜ』
円陣というのは輪になってバレーボールを落さない様にパスし続ける練習方法の一つだ。今日は一年生が校庭、三年生が体育館を使う日なので僕達二年生は教室にいるか体育館裏でこそこそやるかのどっちかなんだ。
…かったるいな…
と、思ったが、僕は昼休みにはちゃんと体育館裏にいた。
「何だよ、誰もいねーじゃんか。」
僕を誘った張本人、龍野 由樹が来た。
「何人に声掛けたんだ?」
「榛南だけ。榛南は?」
「誰も。それじゃ誰も来ないよ。」
「そりゃそうだ。」
ははは…と乾いた笑いをした。
「榛南、隠れろっ」
突然由樹は僕の腕をとり強引に建物の陰に引き寄せた。
「なんだよ。」
「しっ。」
口に指を当てて、僕を黙らせるとその指をそのまま前方に突き出した。
「あれ…」
小声で囁く。
指差した先には三年生(学年章の色が緑色だから)の男子が2人。どちらも辺りを伺うようにキョロキョロしている。そして誰も見つけられなかったのかホッとした顔をして(僕達は見つからなかった様だ)…抱き合った。
「☆◎△!!」
僕は声も出せずに驚いた。だって、だって…。
暫くすると二人はどちらとも無く誘うように唇を重ねた。何度も、何度も。
「すっげー…人のキスシーンって初めて見たけど、男同志かよ。」
ぶつぶつと由樹が囁いている。その唇が僕の耳にぶつかる。
「っと・・・ごめん。」
由樹が赤面する。
「うん」
僕も俯いて赤面する。
ガサッ
草むらが音を立てた。原因は…僕の足だ。
「誰かいるの?」
パッと抱き合っていた二人が離れ、小さいほうの三年生がこちらに近づいてくる。
…ど・ど・どうしよう…
僕は気が動転した。いくらなんでも「キスシーンを見ていました。」なんて言えない。
すると、何を血迷ったのか由樹は僕を抱き締めた。
「榛南…」
耳元で僕の名を呼ぶ。
「好きだよ。」
「うわぁっ」
…僕は由樹に押し倒される格好になった。そこへ丁度さっきの三年生がやって来た。
「…ごめんよ、僕等の方が邪魔したみたいだ…」
赤面したまま二人はその場所からすごすごと消えて行った。
「…由樹ーっ」
僕はドキドキしていた。そのドキドキを聞かれたくなくてわざと大きな声を出し、由樹の身体を突き飛ばした。
由樹は尻餅を付いたまま頭をポリポリとかいていた。
「いってぇなぁー。でも上手く誤魔化せたじゃないか。あの人たちがやっていたことをそのまま真似ただけだったのに。」
…ジャア、スキッテイウノハナニ?…
頭の片隅で何か疑問が浮かんだけどすぐに消えた。だって僕の心臓はまだドキドキいってて由樹の顔さえまともに見ることが出来ないから。
僕は心臓に訊ねる。…このドキドキはびっくりしたドキドキだよな?さっきの人がこっちに気付いたからびっくりしたドキドキだよな?……心臓は答えない。
この件をきっかけに僕達はいつも一緒に居るようになった。
「ほら、あの娘だよ。可愛いだろ?」
「うん、そうだね。」
移動教室の時にすれ違った女の子をそっと見詰めながら由樹が照れくさそうに教えてくれた。僕は空返事をしている。だってどこが可愛いのか分らない。由樹を異常に意識しているような仕草、わざとらしく首を斜めに傾けて笑ってみたり、時々こちらに視線を送ってきてはすぐに視線をそらしてみたり…。嫌いだ。
一体これで何人目だろう、由樹が片想いする娘は。その度に僕はイライラする。
だって由樹の趣味がヘンだからだ。統一性が無いし。
好きになる理由だってヘンだ、「気付いたら好きだった」なんて…。
「恋」っていうのはもっと違うと思うんだ、例えば自分と同じ価値で物事を見ることが出来る人とか、
二人でいることによってお互いが向上できる人とかと恋に落ちるんだ、絶対。
あの娘も由樹には相応しくない…そして僕はまた由樹の恋を始まる前に終らせてしまうのだった。
「なぁ、どうして上手く行かないんだろうな?」
由樹はベッドの上に寝転がって溜息をついて僕に言う。
最近僕達は学校の帰りによく由樹の家で一緒に宿題をやる。時々僕の家にも来てくれるけど僕の部屋は弟達と一緒だから落ち付いて勉強出来ないからね。
「みんな由樹の良さが分らないだけだよ。きっとそのうち必ず由樹に相応しい人が現れる…」
いつもの台詞、いつもの表情で僕が答える。
「俺に相応しいって…どんなヤツだ?」
上半身を起こして僕を見る。
「どんなって…そうだな…由樹のことを好きになってくれる人…って当たり前だね。」
「沙里南ちゃんは駄目か?」
「沙里南はまだ小学生だよ。」
「先物買い…駄目?」
「うーん…聞いてはみるけど…ちょっと待っててくれる?」
「待つ待つ、いくらでも待っちゃう。」
満面の笑みで両手を擦り合わせている。僕はまたいつものイライラ…どうしてだろう?どうしてイライラするんだろう…。
「俺さぁ、彼女が出来たら富士見公園を手を繋いで歩きたいんだ。」
うっとりとした表情で由樹が空想の世界に入って行く。
「そしてさ、ベンチに腰掛けて彼女の肩を抱くんだ、「寒くない?」とか言っちゃってさ。そんでさ、彼女が「寒いの、由樹君の腕で温めて」とか言っちゃってさ僕は思いっきり抱き締めちゃったりしちゃうんだよね。当然その後はキスだよキス。あー畜生、キスしてぇーえっちもしてぇー。」
由樹の腕が沙里南の肩を抱いていて…顔が近づいていって…唇が重なる…。カッと顔が熱くなった。
「由樹、それヘンだよキスしたいから彼女作るの?えっちしたいから彼女作るの?…キスしたいだけなら…」
――僕がしてあげる――
心の奥でそう呟く自分がいて驚いた。
…僕がしてあげる?…って僕が?
「キスしたいだけならなんだよ。」
思考を中断させる由樹の声。
「キスだけなら…その辺のお姉さんに頼めば、由樹かっこいいからいくらでもさせてくれるよ。」
心にもないことを口走る。
「嫌だよ、そんなの。」
僕だって嫌だ…ってどうしてそんなこと思う…
僕の脳裏にいつかの三年生が浮かんだ。それがいつしか由樹と僕に変わる。
涙が溢れてきた。
「どうしたんだよ、榛南?そんなに俺が彼女作るの寂しいのか?ごめんよ、ちゃんと彼女が出来てもお前とはこうやって一緒にいるから。なんてったって俺達親友じゃないか、な?」
でも涙は止まらない…だって由樹は…。
「違う…恋っていうのはお互いが成長するためにするんだから…そんな簡単には…」
由樹の腕が僕の身体を自然に抱きしめにきた。
「バカだなぁ…恋は突然降って来るもんだよ。」
本当だね、由樹。恋は突然降ってきたよ。僕の負けだよ…僕は君が好きだ。
バシッ
突然目の前に人が立ちはだかった。
「バカッ、何試合中にぼんやりしているんだよ。」
「ごめん」
そっか、今は体育の授業中だった。しかもサッカーの試合。
「大丈夫か?どこか具合でも悪いのか?」
「いや…」
2年前にトリップしていたとは言えない。
「少し休んでろよ。
先生、榛南の具合が悪いみたいなのでちょっと抜けます。」
由樹はそういうとさっさと試合を放棄して日の当たらない校舎裏に僕を連れて行った。
「何?考えていたんだ?」
「…由樹の、こと。」
「バカ…可愛いこと言うなよ。」
由樹の左手の指が、僕の髪の間に埋め込まれる。それを支えに僕達はキスをした、深く深く…。
そっと、由樹の胸に顔を埋める。
「ねぇ由樹…僕彼女じゃないけど富士見公園で手を繋いでくれる?」
「…駄目だな…榛南にはもっとでっかい公園じゃなきゃ。」
「日比谷公園とか?」
「もっと」
「代々木公園とか?」
「もっと綺麗なとこ」
「岡山の後楽園とか?」
「えらい和風だな。」
くすくす、由樹が笑う。僕は由樹の笑った顔も好きだ。
「けど、富士見公園でいいよ、あそこがいい。」
「こだわるね。」
「うん。」
そこのベンチに腰掛けて…肩を抱いて欲しい…案外僕もロマンチスト。
その場に腰を下ろして眼下に広がる住宅街を見下ろす。僕らの高校は小高い丘の上に建っている。
「ねぇ由樹、あの家もあの家もあっちの家も、みんな突然降ってきたのかな?」
「なにが?」
「恋」
「なんだそれ?違うよ、恋はいつでも隣りにいて待っててくれるんだよ。」
くくく…思わず笑ってしまった、あまりにも由樹らしくて。
「そろそろ戻るか?」
僕は頷く。
先に立ち上がった由樹が手を差し伸べてくれる。
「榛南。」
「ん?」
僕は由樹が好きだった女の子達の様に小首を傾げて表情を作る。
「ずっと…隣りにいてくれるよな?」
小さく、頷く。
由樹の言うことはいつだって正しい。
本当だよ、「恋は突然降って来た」し、「いつでも隣りで待って」いてくれる。
大好き、由樹。
僕は急いで由樹の後を追った。
僕の名前、君の名前の続編です。というより前の話…でしたね。
2月に『春眠の森』が1周年を迎えられた記念に…と言い出した割には遅くなりました。
だけど大きな声で言っちゃいます、「1周年おめでとうございます。」
リニューアルされて益々頑張っていらっしゃる春眠ママ。これからもステキなお話を読ませてください。
榛南じゃないけど…大好きです。
Dear my best friend 春眠
by Sei☆Kazuki