ゆめのつづき
「愛してる…」
キスの予感に僕はうっとりと瞳を閉じる。
そっと唇に落とされるのは最近やっと馴れ始めた柔らかい感触。
それは甘い吐息と共に触れては離れ、消えては返る。
それが何度も繰り返されて…
まるで夢の世界にいるみたい
…郁くんのキスはいつも優しい
優しすぎて…
そのあまりの気持ち良さに引きずられそうになるが恐くて、僕は郁くんの背中にしがみつく。するとまるでそれに応えるかのように郁くんの手が僕の背中に回り、身体ごと支えられながらゆっくりと押し倒された。
瞳を閉じていても感じることができるほど、たくさんの光が僕に降り注いでいる。
そう、ここは図書館の5階・特別室
閲覧用の机の上に押し倒されたにもかかわらず、意外に背中は痛くないな。なんてボンヤリ考えている僕のネクタイに掛かった郁くんの指がシュっと難無くネクタイを引き抜いて…。
この後に続く行為を予感してひどく頭の中は混乱してしまう。
なのにそこには、その行動に戸惑う僕と、受け入れようとする僕が同時に存在していて、結局郁くんがシャツのボタンを外し終え、胸元にキスを落としても僕は何ひとつ抵抗しないでいた。
それどころか僕は腕を伸ばし、指で郁くんの髪の毛を剥くように撫ぜた後、ふと顔を上げて僕に笑顔を向けた郁くんのネクタイに手を掛けたりしてしまうんだ。
何か変だなと思いながらも手にしたネクタイの結び目を必死で解こうとして、だけどどういうわけか全然解けてくれない。
どんな結び方をしてるんだろう?
少し苛々しながら結び目に目を凝らしてみても、降り注ぐ光が更に強くなって僕の視界は霞んで行く。
そして、それに合わせるかのよう郁くんの存在自体も霧のようにぼやけてしまい
えっ? なに? 何?!
腕を掻くように伸ばして…
…僕は重力を無くした。
ドシンッ!
………
………
………
………
………
音の原因が分らないまま真っ直ぐに向けた視線の先には見慣れた天井の風景。
だけど、まだ今ひとつ状況が掴めない。
爆発するくらい心臓がドキドキしてる。
瞬きを繰り返しながら、やけに荒くなってる息を整えようと何度も何度も大きく深呼吸して、
――夢、…だった?
窓から射し込むのは久し振りに見る明るい太陽の日差し。
目だけでキョロキョロと辺りを見回しながら、さっきのはベッドから落ちた音だったと分った。
なんか、すごい夢を見た。
現実と混同してしまうくらいリアルな夢。
…だって触れられた感覚まで残ってるなんて。
僕は胸元にそっと手を置いてみる。
こんなところにキスされたことなんて無いのに…。
想像だけで感覚まで作り出すことができるのかなぁ。とか考えた後、ゆっくりと身体を起こすとベッドに凭れた。時計に目をやると目覚ましの時間にはまだ少し早い。
そのままベッドに突っ伏して、何も考えたくないと思いながらも夢の原因ははっきりと解っていた。
それはリビングに何とは無しに置かれていたから、暇つぶしのつもりで見てしまったのが運の尽き…というか何と言うか。
そう、原因は昨日観た動画のせいだ。
朝っぱらからすごく過激な夢を見て、まだその感覚から立ち直りきれないまま僕はひとり電車に揺られていた。
いつも一緒に登校している根岸には近頃恋人ができたらしく、毎週水曜日はその彼女との早朝デートでいない。
だけど学校までずっとひとりきりかというと、決してそういうわけでもなくて…。
人の波に揉まれながら制服フリーパスの改札を通り抜けると目の前に広がるロータリーの片隅、向けた視線の先には数人の女子高生達。
が居るんだけど僕の目的は彼女達じゃなくその間をわずかに見え隠れする郁くんだった。
相変わらずの人気振りに僕は思わず苦笑い。
だって郁くんを囲っているのは学園の生徒じゃなくて近くの女子高校の女の子達ばかりだから。
それに学園内にはファンクラブまで有るくらいに郁くんのモテ方は半端じゃなくて、郁くんが独りになるチャンスを窺っている女の子は星の数ほど…なんだろうな、きっと。
あの輪の中に割って入る勇気はさすがにないし、もう少し様子を見ようかと僕が足を止める寸前、ふいに郁くんが視線を向けた。
その瞬間軽く手を挙げた郁くんの良く見慣れているはずの笑顔に、
ドキン
なんて心臓が跳ねたのは…
夢での出来事を思い出してしまったから。
派手に赤面しただろう顔を必死で隠すよう両手を頬に当て、ゆっくりと僕が郁くんの傍に辿り着く頃には女の子達はいなくなっていて、
「…お、はよう」
それだけは口にしたけれど…。
どうしよう、まともに顔が見れないよ。
「ん? 顔がやけに赤いな。熱でもあるんじゃないのか?」
挨拶を返してくれた後、郁くんが自転車から腰を上げて言った。
まさか熱までは出てないにしても、困ったな。普通にしてても考えてることが分ってしまうのに、こんな顔してたら何かあったって直ぐにばれてしまう。
だけどやっぱり顔を上げられないまま俯いていた僕は、郁くんの手が額に触れるまで気が付かず、
「ぅわぁっ?!」
指が触れた途端びっくりして飛びのいてしまった。
「…優也?」
僕は何てことを!
「ごっ、ごめん…」
直ぐに謝って視線を向けた先にはさっきの声よりも驚いてるような郁くんの顔。
マズイと思って何か言葉を続けようと口だけは開いたのに、全然言い訳なんて浮かばない。
それでも何かをって焦れば焦るほど頭の中はもっと真っ白になって、意味も無く手だけをパタパタさせている僕を見ていた郁くんが、すっと目を細めて優しく笑った。
「瞬発力は人一倍だな」
怒るでもなくそう言って、
「運動神経悪くないのに、どうして持久力はあんなに乏しいんだか…」
首を捻ったまま先に歩き出した郁くんの背中を僕はじっと眺めた。
――僕が困ったから郁くんから話を逸らしてくれたんだ
そう分かった途端、僕は軽い自己嫌悪。
どうしていつもこうなんだろう…って。
僕達の関係はこんなふうに一方的に僕が郁くんに甘えきってるって状態で、もしそれが一番最初に泣き顔を見られたことに原因があったのだとしても、だからっていつもいつも甘えてばかりじゃそのうち郁くんに呆れられそうで、僕も何か返したいとか、してあげたいとか思う気持ちはあるんだけれど…。
僕には郁くんが望んでいることが分らない。
郁くんはなんでも持ってる気がするし、なんだってできるから。
郁くんのこと大好きだけど、でも最近ほんの少しだけ…
「何か悩みごと?」
優しい光を背に、そう言って笑顔を僕に向けてくれたのは生徒会副会長の瀬田さん。
生徒会役員の人なんて僕には恐れ多くて近寄りがたい存在だったんだけど、先月起こった事件から時々親しく話をするようになっていた。
中でもこの瀬田さんは柔かい物腰で、たどたどしい僕の言葉でもゆっくりと静かに聞いてくれるから一番話しやすい人なんだ。
先月の事件…っていうのは実は学校内で僕が何人かの人に襲われそうになったって事件。
そのことで少し思い出したことがあったからこうやって生徒会室まで報告に来てみれば、普段はもっとたくさんの役員が居るはずなのに珍しく今日の昼休みは瀬田さんしか居なかった。
で、さっきの言葉は用件が済んでしまっても中々席を立たない僕に向けられたもの。
「…って言うか」
他に人が居ないのをいいことに、ちょっと瀬田さんに相談したい気分になった僕。だけど、こんなことも悩みっていうんだろうか?
でもそれ以外の言葉で説明するのも難しい。
すっかり口篭もってしまった僕が随分長い間、眉間にしわを寄せて考えていたのが可笑しかったのか、クスッと笑った瀬田さんは、
「もし思い出すことが苦痛ならもう来なくてもいいんだよ。小西は充分協力してくれたんだから」
応接セットの深みのあるソファーから軽く身を乗り出すと、僕の頭をぽんと撫ぜてくれた。
確かにじっくりとあの時のことを思い返すのは今でも怖い。
だけど瀬田さんや生徒会長の東條さんの幼馴染み、三上さんって人は僕を襲ったのと同じ犯人にもっと酷いことをされていて、しかもそのせいでこの2年間ずっと病院に入院してるっていうんだから、僕ができる限りのことは精一杯しなければって思うんだ。
それにあの時の記憶が途中から切れてしまってるせいか、恐怖心は消えてしまわないにしても今はもう苦痛というほどのものはない。
だから僕が今抱えている問題は瀬田さんが言うような、そういうことじゃなく、
「…あの」
僕はためらいがちに口を開いた。
郁くんに相談したくても、こればっかりはちょっと、だしね。
「あの時助けてもらえなかったら、僕何されてたかって知ってます?」
言ってから失敗したなと思っても手後れで、驚きの表情を浮かべたまま瀬田さんは固まってしまった。
呆然とした視線を向けられて内心焦りながらも僕はただ瀬田さんが立ち直るのを待つしかなく、テーブルの上に置いたままの紙コップに視線を向けた。
色あせてくすんだ黄緑色と白色が波々線を境に謎めいた形を作り出してて、いつ見ても変な模様だなぁとつくづく再確認した頃、
「…まぁ、友人がそういう目に遇ってるから、知識としては理解してるつもりだが」
ようやく言葉を選びながらの瀬田さんがゆっくり答えてくれた。
そう、だろうな。
やっぱり誰でも知ってることなんだ…っとそういえば、
「もしかして、あの成澤もそういうつもりなんですか?」
これは瀬田さんの追っかけをしている1年男子生徒のこと。
全部分かっててあれだけ派手に同性を追っかけ回してるんなら中々大胆なんじゃないだろうか…。
と、少し表情を落とした瀬田さんは、
「さぁ。あいつはただ一方的に気持ちを押し付けてくるだけだから、何をどこまで考えているのか俺にはさっぱり…」
紙コップ片手にちチラっと僕を見た。
「悩みってそれのこと?」
僕は頷いた。
「橘に迫られた?」
問い掛けに今日二度目の赤面。
だけど、
「違います」
それは夢だけの話で現実の郁くんはそんなことしない。
「誰かに訊いたんだ?」
首を振ってみせ、
「動画で偶然」
答えに瀬田さんは同情の眼差し。
「それは驚いただろうね」
「すごく」
なんてものじゃなく…。
郁くんに告白しておいて、キスまでしてて今更かもしれないけれど本当に知らなかったんだ。
男同士でもああいうことができるなんて。
「橘と付き合ってるって聞いてたから知ってると思ってたよ」
「…付き合ってはいますけど」
「そういうことがあるから別れたいと思ったとか?」
「そんなことは考えてません」
別れるつもりなんて…。
「ただ」
言い澱んだ僕に瀬田さんはふふっと笑う。
「知ってしまった以上、意識しないわけにはいかないってことか」
もう夢に見るくらい意識しちゃって…。
言葉にはしなかったけど、気まずくなってテーブルの上の紙コップを取った。
瀬田さんも手にしていた紙コップに口を付け思案顔でしばらく視線を飛ばした後、
「…そうだなぁ。記憶は消してしまえないから、考え方を変えてみるっていうのはどうだろう」
考え方を、変える?
「どういうふうに」
「恋愛の延長線上に無理にセックスを結び付けるんじゃなく、恋愛の色々な形のうちのひとつだって理解できないか?」
「…でも」
夢の中ではしっかり結び付いてた。
「そう思えないかもしれません」
抵抗しないどころか、ネクタイまで解こうとしてたんだから…。
また夢を思い出して僕が俯いてしまうと、紙コップをコトンとテーブルに置いた瀬田さんは足を組みながら溜め息をひとつついた。
「いきなり現実を突きつけられて混乱してるのかもしれないが、慌てて答えを出すようなことでもないんだ。橘が強要しているわけじゃないなら今のままでもいいんじゃないのか?」
「でも、それは良くないって…」
って?
…あれ?
直ぐに答えたというのに、自分でもこの言葉の意味がよく解らなってしまった。
今確かにそうひらめいたんだけど、どうして…何が良くないって思ったんだろう。
しばらく悩んでいた僕は、
「…あの」
返事が無かったことに気が付いて視線を上げると、瀬田さんは突然不思議な笑みを浮かべてそうかそうかと頷きながら、
「白河が言っていたのはそういうことか」
「は?」
どうしてここでつぐちゃんの名前が…。
「最近橘と二人っきりで会うことが無いって小耳に挟んだんだが」
「今朝、会いましたけど」
「あー、そういう会うじゃなくて…そうだな。極端な話し、小西の家や橘の部屋で夜に二人っきりで会うようなことは?」
僕は首を振って、
「ありません」
言われて気が付いたけど、僕は郁くんを家に呼んだことも無いし、郁くんの部屋…というより家がどこにあるのかすら知らないんだ。
せめて住所くらいは早いうちに訊いておかなきゃ
「だから、そういうことなんだよ」
?
何がそういうことなんだ?
どうもさっきから瀬田さんの会話に付いて行けない。
「…言ってることが全然」
眉をしかめた僕に、
「橘は頭がいいからね」
それは
「知ってますけど」
言葉で二度頷いた瀬田さんは、相変わらず不思議な笑みを浮かべたまま、
「あの手のタイプの人間はいつも先々を読んで行動してしまう癖があるから、絶対に自分を窮地に追い込むようなことはしないんだ」
なんだかすごく難しいことを言っているらしく、
「だから二人きりで会わないんだろう?」
なんてまとめられても、ちっとも話が理解できない。
郁くんは頭が良くて、いつも先を読んでるから二人きりで会わない…の前に、自分を追い込むような、ってことは、
「僕、郁くんに何か悪いこと」
言った途端、瀬田さんの不思議な笑みは苦笑いに変わった。
「どうも、これ以上の説明が必要なら橘自身に尋ねた方がいいように思えるんだが」
「それができないから困ってるんですけど」
と今度は面白そうに笑いながらの瀬田さん。
「何もダイレクトに尋ねる必要は無いさ。橘の逃げ場を塞いでしまえば、向こうからアクションを起こしてくれるから」
「……?」
思いっきり首を傾げている僕を無視したたまま、しばらくクスクスと笑っていた瀬田さんは、
「じゃあひとつだけ」
テーブルの紙コップを取ると一口喉を潤したあと、人差し指を立てて見せ、
「小西が一言“もっと会いたい”って言えば解決するよ」
そんなこと言われてもなぁ…
そりゃあ郁くんにもっと会いたいのは山々だけど、ただでさえ郁くんに迷惑掛けっぱなしなのに、これ以上の我が侭なんて言えるわけ無いし…。
本当の本当は瀬田さん、何が言いたかったんだろう?
低く唸り声を上げながら僕は生徒会室を後にする。
と、
「小西君」
生徒会室を出て何歩も行かないうちに声を掛けられた。
見るとどうやら僕を呼んだのは、この窓側の壁に凭れている男子生徒のようだ。
「僕…ですか?」
誰だろう?
思いっきり警戒心丸出しの僕の視線なんて相手はまったくお構い無いらしく、
「一人でいるところを見かけてね、チャンスとばかりに待ってたんだけど」
なれなれしい笑顔に、ちょっと不信感。
わざわざ一人の時を狙ったって言葉も何やら怪しげで、僕は何も答えないままちらっと胸の辺りに視線を移してみた。
ネクタイの色は青。ってことは3年生…
「ちょっと大事な話があるから、場所変えてもいいかな」
「ここじゃ駄目ですか?」
即座にそう答えた僕に見知らぬ3年生は意外そうな顔をみせた。
だけどこれは仕方が無いこと。
生徒会室は第3校舎1階の東の端にあって、同じ階には職員室。昨日までの大雨が嘘みたいな快晴に直ぐ南側のグラウンドでよっくん達が遊んでる、って条件がそろってるからこそ僕はこうやって一人でいることを許可してもらっているから。
まるで子供扱いなんだけど、また皆に心配をかけたくはない。
「俺としてはもう少し人気の無い所に…」
とんでもない!
「ここでできない話なら聞きません」
どんな要件にしろ、そんなことしたら臣くんを先頭に何言われるか。
すると僕の事情なんて知るはずも無い見知らぬ3年生は、
「相当ガードが固いと見える」
あたりをチラッと見渡して仕方ないといったふうに溜め息をひとつこぼした。
「ここで辛抱するか…こんなチャンスは滅多に無いからね」
独り言のよう呟きながら壁から背中を剥がし僕に一歩詰め寄ると、
「俺3年4組の長沢って言うんだけど、小西君ってさ。付き合ってる人とかいるの?」
「は?」
付き合っている人…って、それが何なんだろう。
「つまりね、特定の人がいないなら俺と付き合ってもらえないかなぁと思って」
「へ?」
付き合うって何だっけ。付き合うって…付き合うって……?
「えええぇぇぇ!!!」
ななな、何をこの人はいきなりっ!
と、慌てて僕は口を塞がれた。
「そんなに驚くことは無いじゃないか、男に告白されるのは初めてじゃないだろう?」
そりゃそうだけど郁くんしか経験が無い。
「あの中の誰かと、って心配してたんだがこの様子じゃあ決まった相手はいなさそうだな」
僕が混乱している間に勝手に話を進める長沢さんは、何も言い返せないのをいいことに、
「図星?」
更に勝手な誤解をしてしまう。
「だったら俺と」
「違います」
慌てた僕の返事のタイミングが外れ、何だといった表情の長沢さんを見上げ、
「好きな人はいるし、その人と付き合ってもいます」
続けた言葉に長沢さんはしばらく目を見開いたまま。
よっぽど意外だったのか、ビックリ眼であまりに眺め入られたものだから視線を逸らそうとした間際、ふっと長沢さんが小さく笑った。
その笑顔がちょっと残念そうにも見えたんだけど…、
「そう、か…。ふぅん」
まるで自分を納得させるみたいに顎に指を当てそうこぼし、
「その相手がどんな奴か非常に興味あるって言ったら?」
「…すみません」
今のところ、僕と郁くんとのことは非公開だし、
「俺にチャンスは全く無い?」
僕は頷いた。
郁くん以外の誰かなんて考えられなくて…。
「そいつって、そんなにいい男?」
「学園一」
続けざまの質問を締めくくるみたいに、きっぱりそう言い切った僕からようやく視線を外すと同時に、
「なんだ、そういうことか」
言って軽く吹き出した長沢さんが続けた言葉はさっきどこかで…
「だったら戦うだけ無駄かな」
…あぁそうか。
ひとり納得したのは瀬田さんと一緒なんだ。
だけどやっぱり何を言っているのか分からず、
「あの」
尋ね返そうとした僕の言葉を片手で遮った長沢さん、
「引き止めて悪かったね」
じゃあ、と手を挙げるとなんだか清々しい顔で立ち去ってしまった。
廊下に取り残され長沢さんの姿が見えなくなっても、ただ首を傾げるしかない僕。
おかしいなぁ。
なんで皆勝手に分かっちゃうんだろう。
僕のこと、話してるはずなのに…
なんだか見えそうで見えない、すごく中途半端な感じ。
そんなもやもやした気持ちのままでいるのが嫌で僕はそこで大きく深呼吸をした。
久し振りに郁くんが図書館の特別室で待ってくれてるのに、やっぱりいい気分で会いたいから。
ここから目と鼻の先にある図書館へ向かうため、何度目かの深呼吸の後、僕がヨシッと気合を入れ直して一歩を踏み出した時、
「優也」
今度は控え目に僕を呼ぶ声。
聞き覚えのある声にキョロキョロと見回すと、階段踊り場の暗がりからゆっくりと出て来た人影に僕は知らず笑顔で傍に駆け寄っていた。
「久し振りだね」
手を振りながら話し掛けたのは1年生の時クラスが同じでいつも一緒にいた岡部公平。
そう言えば2年になってから殆ど話したことが無かったような…。
元気?
って僕が口を開くより先に、
「意外とあっさり引き下がったんだな」
岡部の言葉に僕はキョトンとしまう。
なんだか今日は意味不明な発言をする人ばっかりで、
「何が?」
訊き返した僕に、
「さっきの、長沢さんの告白を蹴ったんじゃなかったのか?」
唖然としてしまった。
なんでなんでなんで?!
…どうして分かったんだろう
ってそんな僕の心の声に答えるかのよう、
「あいつ、1年の時からすっげぇ優也にアプローチ掛けてたからな」
続いた言葉に開いた目と口が塞がらない。
うそぉ
「僕そんなこと全然…」
「優也以外は皆知ってたさ」
………
なんだか突き放すかのような口調に、僕はさっきと別の意味で言葉に詰まった。
今の岡部の言いようがいつもの岡部らしくなくってその上、言ったっきり俯いてしまうなんてもっと変。
なにか気を悪くするようなことでも言っただろうかと考えてる間、岡部は何も言ってはくれず僕も黙り込んだまま…。
こんな暗がりで黙って立っているものだから階段から降りて来る生徒がいちいち驚いて通り過ぎ、何人目かの生徒の姿を見送った後、
「岡部のクラスって1年の時の友達とか結構集まってたよね」
どうにか僕は話題を切り出した。
視線を上げた岡部を見ながら、
「みんな、元気にしてる?」
ああ、とやっと向けられた笑顔にホッとして、
「階が違ってみんなとも…、岡部とも全然会わなくなっちゃったから」
またいつのもペースで話し始めた途端、
「そうでもない」
突然真顔になった岡部。
「優也が俺に気付かないだけだ」
僕は眉間にしわを寄せてしまった。
ちょっと怒ってるようにも見えるのは暗がりに居るせい…かな?
だって今の会話はただの世間話しで岡部を怒らせるようなことは何も無く、第一こんなおっきな身体してる岡部が傍を通って気付かないわけが無い。
ということは、
「や、やだなぁ。久し振りに会ったと思ったら真面目な顔して冗談ばっかり」
あははっと笑ってみたのに、やっぱり岡部の表情は変わらなくって…、
「そりゃあ、あいつに比べれば俺なんてそこの印刷室より存在感薄いだろうが」
確かに直ぐ傍にある印刷室はすっごく地味な部屋なんだけど、
「1年の時はあんなに嫌ってたのに一体何があったんだよ」
やっぱり笑わないままの岡部は僕の勘違いじゃなく本当に怒ってた。
それが分かっても、
「それは」
何の話?
って訊くのはさすがにちょっとマズイ気がして、馬鹿みたいに口をポカンと空けたまま困っている僕の耳に、
「お前、いい加減にしろっ!」
突然渡り廊下から響いてきたのは郁くんの声だった。
うっわぁ…。
郁くんが怒鳴るなんてすごく珍しい。
何事かと踊り場から声の方へと覗き込んで見ればそこには、
「お願いしますっ。橘さんの肩に僕の将来が掛かってるんですから」
「勝手に人の肩にそんなもん乗せるなっ。自分の将来くらい自分で何とかしろよっ!」
「だからこうやって頑張ってるんじゃないですかっ」
「頑張るのは結構だが他人を踏み台にするならもっと暇な奴が沢山居るだろう! さっきも説明した通り、俺は山ほど部活を掛け持ちしてて滅茶苦茶忙しいんだ。どんなに頑張られてもできないことはできないし無理なものは無理なんだ」
きっぱり言い切って歩き出そうとした郁くん。だったのに、
「橘さぁん、僕を見捨てないでくださいぃぃ」
急に弱気になって縋り付いたのが誰かというと、瀬田さんの追っかけ少年、成澤桂樹。
驚きながらも郁くんが慌てて引き離そうとしたにも係わらず、ラグビーとかのタックルみたいにウエストあたりに組みついたまま成澤はちっとも離れそうになくて、おまけになんだか少し遠巻きに人集りまでできてきて、
「こらっ! お前離れろ、馬鹿っっ!」
本気で困ってる郁くんもなんだか珍しい…なんて思ってる場合じゃないんだよな。今こそ郁くんに日頃の恩返しをしなくっちゃの時だ。
僕は拳をギュッと握り締めズンズンズンと郁くん達の方に向かって行くと、人垣の隙間から顔を出し、
「成澤っ」
っと威勢良く名前を呼んだところまでは良かったのに郁くんと成澤と…後、周りを囲んでいた生徒達全員に注目されて、いきなり押し寄せてきた緊張の波に、
「よよよよん、でるよ」
ひゃーっ
思いっきりどもって発音も変で片言の中国人みたくなっちゃった。
疑問符いっぱいの顔で成澤に見つめられ、どうしよかと焦っていると、
「瀬田さんがお呼びだそうだ」
言った瞬間、成澤をぱっと引き剥がした郁くんの通訳。
「えっ! えっ? どこで?!」
「そりゃあ、生徒会室しかないんじゃないか? なぁ、優也」
問い掛けに急いで数回頷いた僕を見て、大喜びの成澤は渡り廊下から生徒会室方向へ猛ダッシュして行ってしまった。
あっと言う間に成澤が姿を消した暗い廊下を呆然と眺めたままの僕の背中に、
「サンキュ」
声で振り返った先には郁くんの笑顔。
僕は何だか申し訳無い気分になって、
「う、ん。でも全然役に立たなかったけど」
言いながら気まずい笑顔を返せば、
「誰でもいいから成澤の気をそいでくれれば良かったんだ」
「…本当に?」
うんうん、と二度頷いた郁くん。
やったぁ
僕でも役に立てたのかなって思う気持ちが顔に出て、ニコっと笑った背中に静かに添えられた郁くんの手。
触れられた瞬間やっぱりちょっとドキッとしたんだけど、今朝みたいに飛び退くなんてことは無く…。
周りに居る見物人には目もくれず、まるで僕をエスコートするかのよう堂々と歩き出した郁くんとは対照的に、背中に添えられた手のせいか他人の視線がいつもよりやけに気になった僕は、顔を隠すみたいに俯いたまま人垣を抜けた。
ようやく人気も減ってきた頃、
「悪かったな」
…?
成澤のことだったら、さっきお礼は済んでるはず…、
「約束通り特別室で待ってるつもりだったんだが昼休みに入った途端にあいつ、教室まで押し掛けて来やがって…。どうにもこうにも離れそうに無いから仕方なく特別室は諦めて生徒会室まで優也を迎えに行く途中の騒動だったんだ」
「ふぅん」
そういうことだったのか。
「でもなんかすごく大切なこと、頼まれてたみたいに見えたけど」
と、郁くんは迷惑そうな顔をしながら、
「昨日バレー部の主将が俺を入部させろって東條さんの所に行ったらしいんだ」
「郁くんに…じゃなくて?」
ああ、と頷く郁くん。
「直接俺に言ってもどうしようもないだろうから、生徒会長の権限でなんとかさせようと思ったんだろう。その話の何がどう変わったのか、俺をバレー部に入部させることと引き換えに、瀬田さんとのデートの権利が貰えるというご褒美に成澤が飛びついたんだよ」
あー、そっかそっか。だからあんなに必死になってたんだ。
いつもながらの大胆不敵振り。
「だけど成澤ってすっごい一途だよね、前にも瀬田さんと二人だけで会うために朝早く登校して来てたし」
「フレディを待ち伏せしてた日のことか?」
「うん。生徒会室で時間潰してる間二人のこと見てたんだけど、瀬田さんの助手みたいに良く働いてたよ」
でもずっと喋り通しでうるさかったけど。
「瀬田さんは落ち着いてるから、意外とああいうタイプがお似合いだったりして…」
と、
「へぇ、優也も成澤支援派だったのか」
「は?」
成澤…
「何、…だって?」
首を傾げて郁くんを見上げると何でも無いといったふうに軽く肩を竦めて見せ、
「それより、これからどうする?」
ゆっくりと足を止めた場所は、図書館へと上がる短い階段の極手前。
「予定通りのつもりでここまで来たんだが…」
視線を向けた先には図書館の大きな柱時計が、もうお昼休みは僅かだぞとはっきりしっかり告げていた。
「なぁんだ、残念」
思わずそう呟いた僕の口からは溜め息までこぼれ落ちる。
…本当に自分でも意外なくらい、すごくすごく残念な気分になって郁くんに視線を戻すと何故だかひどく困ったような素振りで郁くんは僕から視線を逸らしてしまった。
「郁、くん?」
どうかしたんだろうかと不安たっぷりの声で僕が呼び掛けると、腰に手を当て軽く俯いて見せた後、
「瀬田さんと時間も忘れるくらい話し込んでたのかと、ちょっとしたジェラシーが湧いたりして」
悪戯っぽい笑顔の郁くん。
で、ホッとした僕もへへっとばかりに笑顔を返してから約3秒…。
「ジェラシーっ?!」
って、あれだよねアレ。
私よりあの女の方が大切なのっ?
とか言ってドラマで揉めるやつ。
「こっ、ここ。っこんな所でなななんてこと…」
今日何回目か分かんないけどまたまた真っ赤になって焦った僕に、
「…反応、遅過ぎ」
大袈裟に呆れて見せた郁くん。
そしてクルッと反転したかと思うと図書館を背に歩き出したスマートな背中を慌てて追いかけながら、
「別に瀬田さんとばかり話してたわけじゃなくて、生徒会室出てから他の人にも…」
っとそこで唐突に、
「あっ!」
小さく叫んだ僕は一瞬その場でハタっと足を止めてしまった。
僕、なんてことを…
思った瞬間には既に僕は走り出していて、
「優也?!」
郁くんの呼び声を背中で受けながらも振り返る余裕が無く、渡り廊下から第3校舎に入り踊り場まで戻って来て…。
はぁはぁ言いながら辺りを見回してみたんだけど、
「どうしたんだ、急に」
追い付いたというより殆ど僕が立ち止まったのと同時だった郁くんの声。
「瀬田さんの話は冗談のつもりで…」
「分かってる」
言葉を遮りながら、息継ぎがてらに僕は大きく頷いて、
「そう、いうの…じゃなくて。ちょっと…」
ここで岡部と話してたのに、
「誰か、探してるのか?」
僕は郁くんの顔を見ないまま、ただ首だけを横に振った。
郁くんの声を聞いただけで岡部と一緒にいたことなんかすっかり忘れてしまってて…
“優也が俺に気付かないだけだ”
…本当にそんなことがあったのかもしれない。
心配そうにもう一度僕の名前を呼んだ郁くんを見上げると、
「郁くん」
問い返すよう優しい笑顔で首を傾げる郁くんに、
「僕ね…」
郁くんのこと
すっごく好きかもしれない
バンバンバンっ
とボールがバウンドする音。
シューズのゴムが足の動きに合わせてキュッキュッと小さな悲鳴を上げる。
昨日はあんなに晴れたというのに今日はまた梅雨らしくジメジメと雨が降っていて、僕達はすっかり昼休み恒例になってしまったバレーボール対抗試合を見学している…のじゃなく、今日から種目はバスケットボールに変わってしまった。
種目が変わった理由は簡単で、郁くんがただバレーボールの腕前を披露するのを嫌がっただけみたい。
っと、そうそうそれから。昨日みたいに成澤が郁くんに付きまとっていないのは、郁くん自身があの後きっちり自分でカタを付けてしまっていたからだ。
岡部を探しに踊り場まで戻った僕達のところへ、ダマされたと気付くや否やもう一度郁くんを口説き落とすべく大急ぎで引き返して来たチャレンジャー成澤の腕を掴んだ郁くん。そのままバレー部主将の井上さんの教室へと成澤を引き摺って行き、絶対に折れそうになかった井上さんのその口から、
“橘の入部は諦める”
って言葉を見事に引き出してしまった。
相手が誰でも全く物怖じなんてせず自分の意見を主張できるだけでも立派なのに、その上きちんと納得させてしまうあたり、やっぱり郁くんはスゴイなぁと感心して成り行きを眺め入ってた僕。
しかも僕が教室に戻ったのとほぼ同時に5時間目開始の本鈴が鳴ったのだから、もうこれって頭がいいとかのレベルじゃないんじゃないのかな。
実は郁くん、超高性能のサイボーグだったりして…。
だってコート内を活き活きと走る郁くんの姿はこんなにも綺麗でしなやかで、だけど力強くて凛々しくて。あまりに何もかもができすぎてて人間っぽく無いかもって信じたくなるほどだけど、…でも。
触れる指先、抱きしめてくれる腕…そして柔らかく重なる唇は誰よりも優しくて暖かいってことを知ってる。
離せなくなるくらいにその感覚が気持ち良過ぎるから、ついその素肌にもっと触れたいって。
もっと触れていて欲しいって、僕は…。
…僕は?
もっと…?
何を、今…思った?
「謝りに行くって?」
滅多にお弁当を作ってこない一人暮しの翠くんはマンション下のコンビニで買ってきたサンドイッチを食べ終えると、驚いたみたいにそう言った。
ちょうど口の中にご飯の塊が入っていて黙ったまま頷いた僕へと、
「止めた方がいいんじゃない?」
翠くんの向こうから、お箸片手に続けたのはつぐちゃん。
僕が視線を向けると、
「だってその岡部君、優也君が誰に気を取られて自分の存在無視されたか分かってるんでしょう?」
「…やっぱり分かってたって思う?」
やっと口の中がすっきりした僕はつぐちゃんに尋ね返してみた。
夕べ一晩、岡部のことが気になって昼休みの会話を思い返してみたんだけど、なんか岡部は僕が郁くんのことを好きだって知ってる気がしてきて…。
「っていうより、優也君が1年生の時に逃げ回ってる相手が橘君達以外にも居たっていうなら話は別だけど、そうじゃないならどう考えても橘君のことを指してるとしか考えられないじゃない」
「けど、僕は岡部に郁くんのことが嫌いなんて言ったことないよ」
「言わなくったって松前君でも気が付かないくらいなんだから、相当逃げ回ってたんでしょう? ずっと傍に居たなら橘君に会いたくないのは嫌いだからだろうって思うのが普通よ」
「そう、かなぁ…」
今一納得し切れなくて僕が呟いた途端、クスッと翠くんの笑い声。
「まぁ岡部君がなぜ気付いたか云々の話は置いておくとして、さっきの口振りからすると佐伯君も謝りに行かない方がいいって思ってるってことなんでしょう?」
口元に持って行っていたペットボトルのストレートティを一口飲んだ翠くんは、
「うん。今度どこかで擦れ違った時にでもゴメンって言う程度で構わないんじゃないかなぁ。わざわざ謝りに行っちゃうと事が大きくなるような気がするし」
「そうそう。どうして橘が傍に居ると俺のことを忘れるんだって尋ねられたら困るでしょう?」
言って今度はつぐちゃんがペットボトルのお茶を飲む。
僕は波打つ液体をボンヤリと眺めながら、
「変に思われるかなぁ。郁くんのことが好きだからって言っ」
「ガハッ!!」
…?
って
「つぐちゃん!」
僕が叫んだのと同時に翠くんが慌ててつぐちゃんにハンカチを差し出して背中をさすりながら、
「ちょっと白河。仮にも女の子なんだから」
なんて言葉が大袈裟でないくらいつぐちゃんは派手にお茶を吹き出していた。
「ゲヘッ! ごほっ! ごほほっ…ん、ん、ぅうんっ!」
大きな咳払いの後、もう一度お茶をしっかり口に含んで飲み干して、
「そんなこと言ったら火に油を注ぐような物じゃないっ」
なんていきなり真顔で言われたって…
何の話だっけ?
と、口を開き掛けた時、
「えらく派手にぶちまけたなぁ」
声と人影に見上げてみれば直ぐ傍に呆れ笑いの臣くんが立っていた。
「まるで百年の恋が凍て付くような光景だったぞ」
するとサッと翠くんの腕に手を回したつぐちゃん、
「私、佐伯君が居てくれたら松前君に嫌われたって構わないもの」
「お前そういう過激な行動に出るとっ、っ!」
バンッ!!!!!
息を呑んだのはここに居る4人全員。
その音
…っていうより、その音の原因になった物のせいで僕達4人は揃って口をつぐんでしまい、自分の前髪をすごい勢いで掠めて通ったバスケットボールを床から拾い上げた臣くんは、
「も〜り〜お〜か〜〜っ」
言いながら何食わぬ顔で仁王立ちしているよっくんに大きく投げ返す、マネだけ。
そのままボールを小脇に抱え、
「まさかフェミニストなんだ、とか言うんじゃないだろうな」
「何の話か俺にはさっぱり」
全く謝るつもりが無いのか、笑顔で右手を差し出したよっくん。
臣くんはどうするのかなぁと見ていると意外にあっさりボールを渡してしまうと、
「郁っ」
少し離れた場所に立っていた郁くんを呼び付けて、よっくんの傍に並んだ郁くんと3人で何やら少し話した後、
「じゃあ後はヨロシク」
笑顔でコートに向かって手を挙げた郁くんはどうやら抜けるみたい。
それはもちろん僕達以外に見学している生徒にも伝わったみたいで女の子達がなんだかブーブー言ってるんだけど、ここに立ってるみんなは全然そういうことが平気なんだ。
「休み時間に話してた件かしら」
ボールが飛んで来た瞬間に翠くんから腕を離していたつぐちゃんの郁くん達を目で追いながらの呟き。
そして、
「優也」
少し離れた所から僕を呼んだのは郁くん。
「食べてる途中悪いな」
手招きしながらの臣くんの言葉で、なんだか分からないけど僕は取り敢えずお弁当箱をパタパタと片付けて立ち上がり、
「ごめん、ちょっと行ってくる」
一歩を踏み出した僕の手からスルっとお弁当箱を取り上げた翠くんは笑顔で手を振ってくれて、その横で同じく軽く手を挙げたつぐちゃんにも笑顔を向けると僕は二人の後を追った。
それから約15分後――
「知らない声。だったと思うんですけど…」
生徒会室の奥にあるミーティングルームで気まずく僕は呟く羽目になっていた。
体育館を出て最初に連れて行かれた先は第1応接室。で入る直前、臣くんに、
“一切の私語は厳禁だぞ”
そう念を押されて静かに入室すると部屋の奥に在ったつい立の向こうには既に人が座っていた。
会話の内容は良く分からなかったんだけど多分向こう側に居たのは3人の人物。
その中に東條さんが居るってことだけは分かった。
低いけど変に篭り過ぎてない耳障りのいい声で歯切れのいいしゃべり方をするんだ、東條さんは。
そして会話の終わりを待つこと無く静かに応接室を出た後はそのままここに連れて来られ、パイプ椅子に座った時点で初めて僕はことのあらましを説明された。
パタンと扉を閉じたと同時に臣くんが、
“セラフィムの一人が見つかった”
と淡々と告げ、
“だけど本人が言うには、小西を襲った現場には居なかったと言ってるんだ。…実は今寄ってきてもらった応接室に居た中の一人がそうなんだけど、知ってる声じゃなかったかな?”
窓に背を向ける形で椅子に腰掛けていた瀬田さんが続けた質問に僕がさっき気まずく言ったのがその答え。
「僕があの時聞いた声は一人だけなんです」
それは、
“セラフィム”
と名乗ったあの声だけ。
あの状況に全くそぐわない、静かに流れるような声だった。
せっかく犯人の一人が分かったのに何の役にも立てない自分が申し訳無くて、
「すいません」
謝った僕に瀬田さんが笑顔を向けてくれる。
「なにも小西が謝るようなことじゃない。野々宮が主犯じゃないってことくらい、みんな分かってるから」
「ののみや?」
「っと、あーごめんごめん。見つかった犯人、1年生の野々宮満って寮生なんだ」
「それと何れ分かるだろうから先に言っておくが、もう一人。野々宮が犯人を喋ってくれた」
言いながら瀬田さんの隣に腰を下ろしていた臣くんは、胸から出した生徒手帳を机の上にコトンと置いた。
開かれた真っ白いページの片側には臣くんの字で、
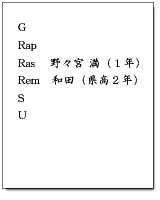
「…なに? このGとかSとかって」
「ああ、奴等の連絡手段はインターネットのチャットだったんだ。そのアルファベットで書いてあるのがチャットで使うハンドルネーム…って分かるか?」
僕は小さく頷いた。
実際に見たことは無いけどマンガとかテレビとかで使ってるのを見たことがある。
「野々宮がネット上で会話をしたのは本人を含めてこの6人だ。ただこの中で奴がオフで知っている人間は和田って男だけなんだよ」
「県高って一駅向こうの?」
訊いたのはこの部屋に入って初めて口を開いた郁くん。
「そうだ。野々宮の話を全て鵜呑みにするなら、この和田って男が薬の調達係らしいんだが、こいつも当日現場には居なかったはずだと言ってる」
「野々宮の話はどこまで信憑性がありそうなんだ?」
続けられた質問に臣くんは少し笑顔を険しくしてしまい、その隣りで大きな溜め息をついた瀬田さんは長机の上で指を組みながら、
「…即答しないということは、松前も俺と同意見ってことか」
重く呟いた。
どういうことだろうかと隣に座る郁くんを見て、その視線をそのまま逆方向に居る臣くんに移すと、
「寮生の1年生が2年前に起こった三上さんの事件に関与してなかったことは簡単に推測できる。念のため身内だとか友人関係は調べてみるが、本人が言ってるとおりこの春、学園に入学してから他のメンバーとネットで知り合ったと考えるのが妥当な線だろう。実行犯として参加させてもらえなかったのは、まだ知り合ってからの日が浅くて信頼度が薄かった。ってところかなぁ…。だがさっきの会話聞いてりゃ分かるだろうが、主犯の野郎が野々宮のことをあれだけ口の軽い男だと分かってるなら、まず面識は無いだろうな」
つまり僕や三上さんを直接襲った犯人までは辿り着かない…と思うからさっき瀬田さんは大きな溜め息をついてしまったってこと、かな。
いいたいことはどうにか理解できるにしろ、そこに至った論理はなんだかぼやけてしまっている…なんて当たり前か。
大体この三人の会話にまともに付いて行けるくらいなら学力テストの成績がもうちょっと上がってるって。
はぁ…
っと、すっかり会話から外れてしまった僕は、ちょっと哀しい気分で小さく溜め息をつき、手持ち無沙汰で開かれたまま机にちょんと乗っている臣くんの手帳をそれとなく眺めて見た。
この中で野々宮と和田の二人は僕を襲った時に居なかったって話だから六人−二人…で四人、もあの部屋に居たってことなのかな。
いや、居たんだろうな。
幾ら僕の身体が小さいほうだからって渾身の力で抵抗したっていうのに腕も足も全く動かせなくなってたんだから。
と、
“恐がらなくていいんだよ”
…そう、だ。
あの声はすごく意外な方向から…
“君を天国に連れて行ってあげる”
確か僕の真上から、降ってきたんじゃなかっただろうか…って、
「え?」
不意に肩を掴まれて僕は目をパチクリしてしまう。
「何? …か、僕」
瀬田さんと臣くんと、それから僕の肩に手を置いたままの郁くん。も含めてみんなが心配そうに僕を見ていて、
「何度呼んでも返事が無いから…、大丈夫か?」
覗き込んできた包み込むような柔らかい郁くんの瞳にうっかり引きずり込まれそうになった僕。
慌てて頭を振った仕草で、
「やっぱりどこか調子が」
「…じゃなくて」
勘違いを素早く訂正すると、深呼吸でどうにか形だけでも落ち着きを取り戻し、
「思い出したんだ。床に倒されて押さえつけられた後、最後に僕の上に誰かが跨ったってこと…」
途端、部屋の空気が張り詰める気配に僕はもう一度深く息を吸ってから視線を瀬田さんに向けた。
「あの時僕が唯一聞いた声は、多分この男の声だったと思います」
それから、
「その声…は」
目を閉じて顔を両手で覆い隠した僕に、
「優也、無理しなくてもいいんだぞ」
これは労るような臣くんの声。
なんだかこんなふうに声だけ聞いてるのって不思議な気分…
「優也」
って続けて心配気に投げ掛けられた郁くんの声で、余計なことを考えてる場合じゃないことを思い出し、
「うん、大丈夫。辛いわけじゃなくって…その、男の喋る感じがね」
「特徴的な何かがあった?」
「というか…」
…そうだ、衝立の向こうからの声。
ハキハキとした東條さんの声と、それとは対照的にオドオドとしどろもどろだったのが多分野々村って1年生。それから後もう一人、ひどく落ち着いた感じで誰よりも静かな口調で話していたのが、
「さっきの応接室に誰か先生が…」
閃いたことを言い掛けはしたものの自信が無いから言葉の途中で顔から手を離してそっと目を開けて見る。
最初に目が合った瀬田さんはニコッと笑うと、
「居たよ、生徒会の顧問だからね」
ああそうか。
生徒会顧問の先生っていえば千郷先生っていう頭の切れるベテラン教師で、3年生の学年主任も兼任してるうえに学園理事長の息子さんだったはず。
直接係わることは無いけれど、全校朝礼の時なんかに何度か声を聞いてもいるし…、どうりて知ってるような声だと思った。
と、
「まさか恐ろしい発言をするつもりじゃないだろうな」
言葉の意味が分からず何のことかと臣くんを見ると、
「千郷はあの事件の時、3年生の教室で授業をやってたんだぞ」
ニヤッと浮かべた悪戯っぽい笑みで僕もようやく言葉の意味を理解した。
こんなズレた会話はしょっちゅう有って、別に臣くんが呆れたり責めたりしてたわけでも無いのに、
「…ごめん、思ってることが上手くまとめられなくって」
何だか今日は変に落ち込んでしまう。
みんなに勘違いばかりさせてる自分が情けなくて嫌になるよ。
「犯人の声はあんなに低い声じゃなかったんだけど…だから千郷先生が犯人だって言いたかったんじゃなくて、その。しゃべり方っていうか雰囲気っていうかがどこと無く先生に似てた気がして」
視線を机に落とした僕が一生懸命にどうにかそこまで話したところで、
「…大人の男の声、だった」
静かにまとめてくれたのは郁くん。
隣を見上げてみたけれど腕を組んだままさっきの僕みたいに机を見つめる郁くんの視線は動きそうに無い。
仕方が無いから瀬田さんに向き直って、
「そんな感じだったと思います」
言った僕に、有り難うと告げた瀬田さんはなぜだか妙に嬉し気に席を立った。
それは新情報が嬉しくて喜んでるってふうではなくて、
「じゃあそろそろお開きということで」
言いながら次いで席を立った臣くんまでもが楽しそう。
そして、
「少しだけ橘の背中を押しておいてやるよ」
後ろを通り過ぎがてらの瀬田さんが小さくそんな言葉を僕に耳打ちして行った。
パタンっ
パタパタパタパタ…
窓を打つ雨の音が強くなったり弱くなったり…。
朝から薄暗い部屋でジッとしてるせいか時間の感覚が無くなってることに気が付いて、壁の時計に目をやると夕方の4時前。
もうこんな時間になってたんだ。
お昼ご飯食べるの忘れてた。
けど、なんか今更だからもういいや。
郁くんのことで頭の中が一杯だからお腹まで一杯な気分。
なぜだかここのところ、僕はこんなふうに郁くんのことばかり考えている。
あの夢を見てからの僕はすごく変で、郁くんを見るたびに胸の奥の方から込み上げてくる何かが僕に何かを伝えようってしてるんだけど、どうしても僕はその答えを見つけることができないまま…って、あれ?
胸の中で何かがつかえてるような感じになるのは、いつも郁くんが傍に居る時じゃなかったっけ。
ってことは郁くんとゆっくり会えれば答えが見つかる、ってことなんだろうか…。
僕から誘ってみれば時間を取ってくれるかな、とか思いながらパタリとそこに転がって何気に天井を見上げた時、
“小西が一言もっと会いたい、って言えば解決するよ”
ふと、瀬田さんのそんな言葉を思い出した。
あの時は瀬田さんの言葉の意味が理解できずにいたからすっかり忘れていた言葉だけど、確かにそうすることが一番いい方法なのかもしれない。
瀬田さんのアドバイスっていうことが何より心強く思えてきて、ジッとしていられなくなった僕は勢い良く身体を起こすと机の上に置いてある携帯電話を手に取った。までは良かったんだけど次の瞬間すっかり固まってしまった。
なぜって、
僕、郁くん家の電話番号知らない
ひぇ〜、なんでなんでなんで?! いつも電話で話してるのに〜…って、そうか。郁くんがほとんど家に居ないから掛けてもらってばっかりなんだ。
だからって一度もそんな大切なことを訊きもせずにいた自分に今更ながら呆れてしまう。
両想いになれただけですっかり浮かれてしまっていた僕は郁くんのことを何一つ知ろうともしなかった。
郁くんともっとたくさん会いたい。
郁くんともっと一杯話をしたい。
そして、それから…
「? …それから?」
一瞬頭の中を過ぎった何かについ手を止めてそう呟いてしまった僕だけど、
「そ、れはちょっと後回し。電話電話と…」
これ以上独りで考えると、きっと頭が爆発してしまう。
とにかくまず行動してみようと手に持っていた携帯電話のアドレスから見知った名前を表示させボタンを押す。
ツ、ツ、ツ、と小さな接続音の後程なくプルルルと響いた呼び出しベルがプツっと途切れ、
『…れっ、優也?』
少し戸惑ったような翠くんの声。
電話口の向こう側から聞こえて来る何か騒がしい雑音に、
「ごめん。今大丈夫かな?」
『あー…っと。電車が…るま…の、間で良か、たら』
「じゃ、じゃああのさ。郁くんの電話番号知らない?」
駅構内だからか電波の調子もすごく悪そうで、とにかく僕が慌てて用件だけ伝えると、
『橘…? 電話っ…て、携た…持ってた…、け?』
「違う違う、家の方の」
聞き辛い声を必死で聞き取っているというのに、
『何だって? 橘がついに携帯電話を持ったのか?!』
通話相手がよっくんに変わってしまった。
けどなぜか電波は突然良好。
「よっくんてアンテナみたい」
『は? 何を言ってるんだ』
「だってよっくんに変わった途端、通話が良くなったから」
『場所をちょっと移動しただけだ、馬鹿なことを言ってないで質問に答えろって。橘が携帯持ったのか?』
別に質問まで繰り返さなくってもいいのに。
大体よっくんがこんなふうにしつこく訊いてくる時って、何となく嫌な予感がするんだけど仕方なく、
「…持ってないよ」
正直に答えた。
『じゃあ何の番号の問い合わせなんだよ』
…やっぱり今更知らないのって変だよなぁ、とか思いながらも、
「自宅の電話番号」
『それは番号を忘れたってことか?』
よっくん達は時間がないはずなのに、
「違うよ」
『控えたメモかなんかを無くしたとか?』
なんてまだしつこく問い掛けてきた。
「よっくん、僕急いでるんだけど」
途端、わはははっと響いたよっくんの大笑い。さすがにムッとしてしまった僕の気配は電波化してしまったのか、
『悪い悪い。確か俺の携帯に登録…』
ゴソゴソと音がしたなと思ったら、
『もしもし、僕。美都が今番号探してくれてるから』
また予告無く翠くんに戻ってしまった。
だけどこういうのが阿吽の呼吸…。というか、つうかあの仲ってやつかも。
僕にとっては夢の夢。
『何か橘に急用?』
「っていうか。う〜ん…と、まぁ。そうかなぁ…」
うにゃうにゃと言葉を濁した僕に、クスクスって笑い声の後、
『家に居るといいね』
翠くんには見えないけど、
「うん」
目の前に居るような気分になって笑顔でそう言った時だった。
ピンポーン、ピンポーン…
鳴ったのはインターフォンの音。
『…誰か来た?』
心配そうな翠くんの声に、
「みたいだけど、よっくんは…」
『大丈夫だよ。取り敢えずお客さんの方、出たら?』
話してる間に僕はインターフォンまで移動していたから短い返事を残し空いてる手でインターフォンの受話器を取った。
「はい?」
『………』
せっかく片手間で出たというのに相手は無言。
もう一度訊き返してもやっぱり何も言ってはこず、
忙しいのにまったく!
なんて思って受話器を置く寸前、
『……俺』
スピーカーを通してるせいか声色が聞き取り難くいし“俺”なんて一言じゃ僕には誰だか分からない。
「すいません、どちら様」
『岡部』
なぁんだ。
言われてみれば、あの声は紛れも無く岡部だよ。
「あれ? 何? どしたの」
訊くより先に玄関、開けてあげなくちゃ。
「直ぐに開けるから待ってて」
そのまま受話器を置いて、もう片方にある電話の存在を思い出し、
「ごめんごめん、番号分かった?」
『うん。じゃあ市外局番から…』
僕は素早くメモに書き写すと、
「ありがとう。よっくんにもヨロシク言っといて」
『分かった。っと、ちなみにさっきの、宅配か何か?』
「ううん。岡部が遊びに来たんだ」
『えっ?!』
って翠くんの驚いたみたいな声を残して突然通話が切れてしまった。
雑音が大きくなってたから電車が傍を通ったのかもしれないけど、それ以上は考える余裕も無く僕は玄関に向かうその途中、ちょっと部屋の中が散らかり過ぎていることに気が付くと簡単に部屋を整理し終え改めて玄関へと向かった。
「お待たせ」
扉を開き岡部を中に招き入れると僕は鍵を閉めながら、
「結構雨、降ってるんだろう?」
僕の言葉に答えが無い。
けど尋ねたっきり背を向けた僕が気付かなかったんだろう、きっと。
「飲む物、持ってくるよ。いつものでいいかな?」
この“いつもの”はスポーツドリンクを指している。
新製品が出ると嬉しくなって直ぐに飛び付いてしまう僕とは大違いで、岡部はとても一途なアルカリ飲料愛好家なんだ。
部屋に入った岡部が小さく薄っぺらな座布団に座ると同時に台所へ行こうとした僕に、
「いらない…から。ちょっと座ってくれないか?」
後から思えばこの日、最初から岡部の様子はおかしかった。
何の連絡も無く家まで訪ねて来たことにもっと疑問を持てば良かったのに、岡部は何度か家に遊びに来たことも有るから特には気にならなかった。
それに飲み物のことにしたって単純に岡部は喉が渇いてないんだ、くらいにしか僕は思ってなかったんだ。
だから言葉通りに小さな物置代わりのテーブルを挟んだ向かい側に僕は腰を下ろした。というのに、それっきり岡部は夏用の海色で薄いラグを見つめたまま何も話し出す気配がない。
変だな、とは思いつつ、
「何か大事な話?」
言い難いことなんだろうかと僕から尋ねてみると、ようやく岡部は顔を上げ口だけは開いた。けど、やっぱり何も言わずに僕から視線を逸らしてしまう。
「…悩みの相談とか?」
言ってはみたものの、俯いている岡部の額の辺りを睨みながら僕じゃ絶対役不足だなと眉間にシワを寄せてしまった。
う〜ん、どうしたものか。
こんな時、郁くんなんかだと全然別の会話から上手く用件を訊き出したりできるのに、もちろん僕にそんな技が有るはずもなく、だけど岡部の沈黙が長引くようなら僕からとにかく話題を切り出さなきゃこの間の二の舞に…って、それで思い出した。
「そうだ、僕。岡部に謝ろうと思ってて」
忘れてたわけじゃないんだけど野々宮の件とか、郁くんとのこともあって気持ちにすっかり余裕が無くなってた。
また僕は岡部のこと、後回しにしてたね。
「こないだはごめん、話の途中でいきなり居なくなったりして。ずっと気にはなってたんだけど色々」
とそこまで言った時、
「好きだ」
岡部の低い声で僕は口をつぐんでしまった。
ジッと僕を見つめる岡部の顔を見たまま、
スキダ…?
頭の中で上手く漢字に置き換わらない。
少し首を傾げた僕に、
「ずっと、1年の頃から好きだったんだ。最初はただの世間慣れしてない頼りない奴、くらいにしか思ってなかったけどいつの間にかすごく好きになってて…。優也に近寄ってくる奴、全部蹴散らして、俺」
言いながらガガっとテーブルを除けた岡部が這うように段々迫って来たりしたから、
「ちょちょっ、ちょっと岡部っ」
反射的に僕は逃げようと座ったまま、ずり下がる。
「誰にも取られたくなかった、優也のことを誰にも渡したくなかった」
「そそそんなっ。わっ、悪いじょーだんばっか」
突然に振って湧いた岡部の告白に頭の中は大混乱。
それでも笑顔でどうにかそう言えたのは、嘘だよねって気持ちが強かったから。
なのに、
「橘にだって、渡したくない」
…僕の引きつった笑顔は見る影もなく消えてしまった。
やっぱり岡部は郁くんとのことに気がついていた。
だから僕のことを怒ってて…
「俺の告白は冗談にしか思えなくても橘の名前が出ただけでそこまで顔色が変わるっての、どう解釈しろっていうんだ?」
ほとんど上から乗っ掛かってる態勢でさげすむように睨まれて、
「たった3ヵ月前までは顔すら見たくないって感じで逃げまわってたくせに」
「それは」
「よっぽど上手く口説かれたんだろうなぁ」
…口説く、って
「違う。告白したのは」
「仮にもバージンキラーなんて呼ばれてるんだ、優也みたいな世間知らずなガキ堕とすのなんて1分もかからなかったんじゃないか?」
目つきも言葉もなんかすごく僕のことを馬鹿にしてるって思ったけど、
「甘い言葉で、慣れた手つきで…」
Tシャツの中に突然入ってきた手に、
「ばっ! ちょっと岡部!」
ビックリした僕は岡部の下から抜け出ようとしたのに、そのまま僕の上に体重を掛けられて、
「あいつはどんなふうに抱いてくれるんだ?」
つい睨み返したのは圧し掛かられた重さで苦しかったからじゃなく、その言葉…というよりは、なぶるような言い方にひどくカチンときたから。
僕のことはともかく、岡部がさっきから郁くんのことを馬鹿にしてるのが何より腹立たしくて、
「いい加減にしろよっ!」
叫ぶなり僕は自分でも驚くような力で岡部を突き飛ばしていた。
バランスを崩した岡部がヨロヨロっと部屋の端っこへとふらついた隙に素早く勉強机の縁にしがみ付いて立ち上がる。
「なんにも知らないくせにっ」
言った瞬間岡部の起き上がる気配に、ペン立てにあったペーパーナイフを握り締め、
帰れっ!
って叫ぶつもりだったけど、
「かっ」
の一言だけで止まってしまった。
正座したまま両手をついて俯いてる岡部の姿が、土下座してるみたいで…
「…おるくんは、そんなんじゃないんだ」
咄嗟に続きを変更すると、
「別に変な誘い方をされたわけでも無くって…。僕が郁くんを嫌ってたわけでも無くってね」
そこで一旦、言葉を切ってまず自分の気持ちを静めようと大きな深呼吸をした。
ついさっきの岡部はあんなだったけど1年生の時はずっと一緒に居てくれて、話も楽しくていい友達だったんだ。
落ち着いて話せば分かってくれる。
岡部ならきっと分かってくれるはずだから…
「僕の両親が高校に入学する直前に事故で死んだって知ってるだろ。その時に…っていうか、すっごく辛かった時にホント、偶然なんだけど僕は郁くんに助けてもらってたんだ。なのにちょっとした僕の思い違いで、郁くんが同級生だったって分かった途端に逃げ回ったりしちゃって…、だから岡部がさっき言ったみたいに僕が郁くんを嫌ってるって誤解しても仕方がないと思うんだ。けど…うん、でも本当はね」
いつの間にか僕の心の中に入り込んでいた郁くん。
きっと、多分僕は、
「初めて会った時から好きだったんじゃないかって思うんだ。だから岡部が勘違いしてるみたいなことは何も無くって…。その、先に好きになったのは僕だし、告白したのも僕で、郁くんはただそれに応えてくれただけ。僕は岡部のことも好きだけど、でもそれは」
「悪魔」
低い声が小さく部屋に響いた。
喋ってる途中の言葉だったから聞き違いだろうかと、
「え?」
床にうずくまっている岡部に短く尋ね返した。
すると膝を付いたままゆっくりと身体を起こした岡部が、
「こうやって俺の目の前で喋ってるのは、可愛い顔の仮面を被った悪魔じゃないかって思うことが何度かあった」
真っ直ぐに僕を捕らえる岡部の凍りつくような冷めた視線。
「どんなことより…自分のことよりもお前を優先して、大事にして…ずっと俺が傍に居たっていうのに。確かに、はっきりと告白しなかった俺も悪かったかもしれない。でも、だからって俺の気持ちに全く気付かなかった優也にだって責任は無かったのか?」
…だけど僕は、
「そういうのは、苦手」
「そうだな。優也はそうやって…いつもそうやって自分は分かりませんって顔してたよ、俺の気持ちを知る努力すらしないで…。一番近くに居ながら、俺はずっと優也に無視され続けてきたんだっ。お前のその無邪気さは」
継いだ息がやけに震えてるって感じたのは、
「俺にとっては凶器だよ」
いつからか僕が岡部を見てなかったから。
だけど今、自分の目が何を映しているのかはよく分からない。
なにか、ものすごく重い物が全身に乗っかってきたような感覚に身体が支えられそうになくて、今にも押し潰されそうなんだけど、まだ駄目だって頭のどこかが命令するから…。
どうにか僕は机に乗せていた手だけで身体の安定を保っていた。
「橘がそんなに好きならそれでいいさ。けどあいつが今までどんな女と付き合ってたか知ってるのか? 本気で橘と付き合うつもりなら、遊ばれて要らなくなったら捨てられるってことくらいは覚悟しておくんだな」
…聞き終える頃には僕の思考はほぼ停止。
パタン
っと小さな音で一気に僕の身体は全ての支えを失って、まるで糸の切れた操り人形みたいに床へと座り込んでしまった。
岡部が部屋から居なくなったってことは分かったけど、それ以外のことは何一つ考えられない。
ただ…ひどく胸が締め付けられる感覚が不快で、それに加えて何かが苦しくてきつく瞼を閉じながら、僕は泣きたいのかなって思ったんだけど涙は出てこなかった。
でも泣きたいってことは、もしかして辛いのかな。とか、悲しいのかな…とか、岡部の話の内容じゃなくそんなことばかり考えている僕の耳に、
RRRRR……
鳴り響いたのは電話のベル。
だけど僕は誰かと喋るような気分じゃなくて、というより立ち上がる気力が出ない。
しつこくしつこく鳴るベルに、うるさいぞって思いながらもその間、ただずっとベルの音だけに意識を集中させていた。
RRRRR……、RRRRR……、RRRRR……
一体どれくらい鳴っていたのか…
しばらくしてようやく鳴り止んだベルになぜだか少しホッとしてしまう。
ついでに気持ちもちょっとだけ落ち着いたのか、机にもたれ切ってた身体をどうにか起こすだけの力は出た。
それでもまだ立ち上がるまでには回復してなくて、ボーっと岡部が座っていた場所を眺めていると今度は、
ピンポーン、ピンポーン…
また家に誰かがやって来た。
まさか岡部が戻って来た…ってことは有り得無い。
だって玄関の鍵、開いたままって知ってるだろうし。
でも何にしろ誰にしろ、さっきの電話以上に出る気分になれるはず、無いよ。
なのにどうしたことか電話同様このお客さんも結構しつこく何度も呼び鈴を鳴らしている。
それどころかコンコンコンっと控え目ながらドアをノックまでし始めて、戸口の前で何か言ってるみたい。なんだけどこの声、…って思った時にはもうすでに僕は部屋から飛び出ていた。
すると玄関先で、
「あ…っと、悪い。鍵開いてたから勝手に」
心配顔だった郁くんがそこで言葉を切ったのは、僕が廊下で座り込んでしまったから。
きっと“オイオイ泣く”のお手本みたいになってるだろう僕。
即座に駆け寄って抱き締めて、そして黙って静かに抱き込んでくれた郁くんの腕の中は、最初に遇った夜と同じで本当に居心地が良くて…。
で、やっぱり結局はこうやって甘えることしかできない自分に気が付いて嫌気が差したりもしたから、もうこの際泣いてるついでにもうしばらく泣いてみることにした。
それって全然辻褄が合ってない…
とか考えるの、今だけは止めよう。
…だって、二人だけの時間を僕はずっと待ってたんだから。
「ここ、優也の部屋だよな」
すっかり落ち着きを取り戻した頃、僕の肩を抱いたまま立ち上がった郁くんは言うなり返事も待たずに僕を連れ立って中へと入る。
そして僕をベッドサイドに座らせた後、郁くん自身はそこからほんの少しだけ離れたテーブルの横に腰を下してしまった。
…傍に居て欲しかったのに
残念…って思わず咽喉から出掛かった言葉を慌てて呑み込んだ。
だって手を伸ばせば充分に届く距離に郁くんは居るっていうのに…変なの。
すると、
「話す気分じゃないなら、それでもいいんだぞ」
僕が俯いてしまっていたから、きっと郁くんが気遣ってくれたんだろう。
だけど顔を上げ郁くんへと視線を向けながらの僕は首を横に振った。
岡部のことを言い付けるだとかそういうんじゃなくて、ただ聴いて貰いたかったんだ。
郁くんには知っていて欲しいって思うから…、何だって僕のこと。
「実は、さっき岡部が来てね…」
主を失った薄っぺらい座布団をジッと眺めながら僕は話し出す。
話しながら、僕も何が起こったのかもう一度よく考えてみようと思う。
僕が好きだと言った岡部。
誰にも渡したくない、とも言った。
そして郁くんとのことを勘違いして、怒って僕の上に圧し掛かってきて、
“あいつはどんなふうに抱いてくれるんだ?”
…郁くんはそんなこと、しやしないのに。
今だって、こうやって二人っきりになれたって郁くんは何も…
「それで?」
声に視線を郁くんに戻すと、
「俺から逃げ回ってた理由を説明して、それからどう」
「あ、うん。それから」
話の途中だったことを思い出し、僕はどうにかこうにかでもできるだけ要点を絞って話を続ける。
そうしながら今度は座布団ではなく郁くんをジッと僕は眺めて見た。
片膝を立てテーブルに軽く肘を付いたまま、真剣に僕の言葉に耳を傾けてくれる郁くんは、私服姿だとやっぱりかなり大人びて見える。
白のTシャツにアイボリーのカバーオール、それからパンツが黒のせいか座っているというのに制服を着ているよりもずっと足がスマートに…
って、あれ?
どうして郁くん、床に直接座ってるんだろう。
せめてラグの上に座るくらいのことをしたって、とそうだ。
さっき岡部とのドタバタで床の上のレイアウトが崩れちゃったんだ。
狭いラグと小さなテーブル、そして薄い座布団のバランスが随分と変。
それぞれを元の配置に戻して郁くんに座り直してもらうつもりで僕はスクッと立ち上がった。んだけど、不思議そうに見上げた郁くんと目が合った途端に、
「隣に座ってもいいかな?」
思わずそんな言葉が口を衝いて出た。
何を言ってるんだ
目を細める仕草がそう言ったように感じて、
「なぁんて…、暑っ苦しいのにね。やっぱりいい、ごめん」
パタパタとワザとらしく手で顔を煽りながら、気まずくなった僕はそのままそこに座り直した。と殆ど同時に静かに立ち上がった郁くんが、
「そんなに暑くはないぞ…」
言い終わる頃には僕はすっぽりと腕の中に納まっていた。
一瞬拒まれたのかと思ったから、ホッとしたせいで僕は引き寄せられるまま郁くんの胸に頬を寄せ、
これってまるで公園のベンチで寄り添う恋人達みたい
とか思ってる間に知らず郁くんの背中に腕を回していた僕。
人目のある所でこういうことするって何考えてんだかって思ってたけど、あの人達の気持ちが今なら分かる気がする。
…きっと、好きな人しか見えてない
郁くんも同じこと、思ってくれてたらいいな。
今、郁くんも僕と同じふうに感じていてくれたら…
と、僕の想いが伝わったのかゆっくりと覆い被さる影の気配に僕は素直に瞼を閉じて、
「愛してる」
…甘く優しく唇がそう触れた。
そして何度も繰り返されるキス。
だけど、しっかりと重なりきらない中途半端な感覚に、
もっと
って。
何が欲しくてそう思うのか分からないまま、薄いため息を洩らした僕の唇を今度はしっかりと塞いだ郁くん。
気持ちごと身体ごと全部引きずられてしまいそう…なんだけど。
でも…
これって最近どこかで体験しなかっただろうか?
なんて頭の隅で思いつつ、ズルズルと心地良い波にさらわれてしまうのが何だか少し怖くなって郁くんの背中に回した腕に力を込めた時、ようやく僕は気が付いた。
そう…、あの夢の最初に似てるんだ
確かこんな優しい空気の中に僕は包まれていて、郁くんがこんなふうに傍に居てくれて、そしてそれから…。
頭の中で絡み合う夢と現実との境目が段々と分からなくなってきた。
なんだかもうどうでもいい気分。
流されるなら流されるままに任せてみよう。
郁くんなら…
郁くんとなら大丈夫
…ってそう感じた瞬間だった。
唐突に両肩を掴まれ引き離された僕は思わず、
嫌だっ
「消えないでっ!」
そう叫んでからの沈黙は実際にはどれくらいの時間だったんだろう。
強く郁くんにすがりついたまま不規則な雨の音に耳を傾けていた。
バクバク鳴ってた心臓の音はすっかり納まって呼吸もほぼ正常に戻ってもジッと動かないでいると、
「優也」
郁くんの囁きに驚いた感じは無い。
でも、
「ごめん…。俺がいきなり」
何かを誤解した郁くんの肩に顔を押し付けたまま僕は首を振った。
謝らなきゃいけないのは僕の方だ。
あんな動画なんて見るんじゃなかった。
そうすれば、あんな…
「夢、見なくてすんだのに」
何もしない郁くんに僕が望んでしまったこと。
それは
「…夢、って?」
郁くんの柔かい問い掛けにただ黙ったままの僕。
「悪夢の類…かそれとも」
「良くない夢」
だけど
良くないことだって分かっているけど、僕は気付いてしまったから…
夢の最後に思ったこと。
「郁くん」
あのね
「言っても嫌いにならないで欲しいんだけど」
クスっと耳元で小さな笑い声。
嫌いになんてならないさ
って言葉の代わりに優しく抱き込んでくれるから、そんな郁くんだからこそ
「ついこの間、僕が見た夢」
…望まずにはいられない。
「場所は図書館の特別室。そこでいつもみたいに僕と郁くんは二人きりで座ってて」
今みたいに柔らかい時間が流れていた。
「郁くんは優しい声で愛してるって言ってくれて…。それから、さっきみたいにキス、してくれたけど…だけど夢の中の郁くんはそこで終わりじゃなかった」
まだ心の隅っこに残る迷いを振り切りたくて、僕は一度郁くんから身体を離す。
そしてゆっくりと見上げた先の郁くんにはいつの間にか笑顔が消えていた。
話し終わっても表情が固まったままだったら…
そう考えるとなんだかすこく怖くなって、視線を落とすと胸に手を当て僕は大きく息を継ぐ。
郁くんのことを失くしてしまうかもしれない
けど…
「そこに居た郁くんは、僕をあの大きな机の上にゆっくり押し倒して、制服のネクタイ外してね」
「優也」
「シャツのボタン外して」
「まさ…っ」
郁くんの口をパタンと手で塞いだ僕は郁くんの言葉を止めた。
「それからね」
端正で薄い唇を覆った僕の指は頬から顎…喉元をゆっくりと通り過ぎた後、シャツの上からだけど郁くんの胸の真ん中辺りでピタリと止めて、
「ここにもキスしてくれた」
声が…、掠れるみたいに震えてる。
「…僕は、夢の中の僕はどうしようかって迷ってた。けど、でも…それでいいのかなって思ったんだ。だから僕も郁くんのネクタイ外そうとしたのに、やっぱり夢の中でも僕はモタモタしてて全然ネクタイが上手く解けてくれなくて。そうこうしてる間に目の前の郁くんが段々薄けてきて」
そして、
「郁くんがいなくなってしまう瞬間、僕はとっさに手を伸ばしてね」
消えてしまわないでっ
って…、そう叫びたかった。
「あのまま、消えてなんか欲しくなかった…」
だから
そう願ってしまった自分自身がすごくショックだったから、知らない間にその気持ちを封印してしまってたんだ。
瀬田さんが不思議な笑顔で言った、
“あぁそうか”
の意味がやっと分かった。
悩んでる本当の訳さえ分かってない僕より先に、瀬田さんはその答えに辿り着いてたってこと。
でも瀬田さん。
それに気付いたことが本当の解決にはなりそうにないです。
だって話が終わっても郁くんは何の反応もしてはくれないし、顔を上げて表情を確かめることができないくらいに僕は追い詰められてしまってて…。
細く息を吐きながら、そっと郁くんの胸元から手を離そうとしたその時だった。
「見たいか?」
……
ふいに投げ掛けられた言葉に反応できず、ただ黙ったままでいる僕の耳元へ、
「その夢の続きを…、見たい?」
静かにゆっくりと、だけどはっきりした口調で郁くんは言った。
しばらく郁くんの胸元を眺めた後、僕は数回瞬きをして、
コクン
頷いた瞬間、強く郁くんに抱き締められた。
「ごめん。言い難いこと、言わせて…」
僕の髪に顔を埋めながらの言葉に今度は首を横に振って見せると、
「お姉さん、夜までにってことは?」
訊いた郁くん。
当然の質問なんだけど、なんだかこれからのことがひどく現実味を帯びてきて、
「…多分夜中になる、と思う。から、うん。大丈夫」
紅くなりながらも答え終わる。や否や、フワっと僕は中に浮いていた。
何の前触れも無かったものだから驚いて必死で郁くんにしがみつたんだけど郁くんは戸口辺りまで数歩移動したきり動き出す気配が無い。
…もしかしてこういう時って僕も何かしなくちゃいけないんだろうか?
でも…、だったらちょっと困ったかも。
僕が見たビデオはいきなり縺れ合う場面しかなかったし、夢の中にこんな状況は無かった。
いつまでもこんなことをしてるわけには行かないってことくらいは分かるのに、どうしよう。
どうしよう、どうしよう、ど
「電気」
? …がナニ?
「俺、今両手が塞がってるんだ。そういうのが好みだというなら別に構わないが」
言葉でようやく郁くんの肩から頭を上げると、目の前にはホルダーに収まった電気のリモコン。
あーそっかそっかぁ
なんて言われるがまま手を伸ばした僕に、
「思い直すなら今のうちだぞ」
真顔での郁くんの言葉。
僕はしっかりとその言葉と視線を受けとめた後、
ピピピ
とボタンを押した。
僕は分かってないことが多いけど、郁くんにも分からないことがあるんだね。
だって今更迷うくらいなら僕、夢の話なんかしなかったよ。
って心の中でだけ呟くと、弱々しく部屋を照らしているオレンジの光から視線を逸らしてリモコンをホルダーへと戻した。
静かにその視線を郁くんへと戻したことが合図みたいに、数歩引き返した郁くんごと僕たちはベッドの上。
こつん
と額を当てたままの距離で少し見つめ合っていたんだけれど…
ふわりと微笑んだ郁くん、の指がそっと僕の頬に触れて
僕の名前を囁いた唇が薄く重なって…
それからのことは
うーん、と。
その後のことは
…えーっと。
ナイショ☆
「かおるく〜ん、かおるく〜ん、かおるく〜ん」
「だから直ぐに戻ってくるから」
「やだ〜やだ〜やだ〜」
子供みたいに郁くんの素肌に擦り寄ったりすると、呆れ顔でため息をつきながらも、
「そこの電話を取るだけじゃないか。まったく、いつからそんな甘えん坊になったんだ」
僕の髪をクシャクシャっと撫ぜてくれる。
いつからって、それは…
「つい、今さっきから」
途端に眉を上げた郁くんに得意げに笑って見せると、
「随分とご機嫌なんだな」
言った郁くんの笑顔に大きく大きく微笑み返した。
…ご機嫌って言われると確かに超上機嫌。
こうやってるだけでも口元が緩んできて、ヘラヘラ笑い声が出てしまいそうなくらい何だか楽しい気分なんだ。
それにどんなワガママ言ったって許してくれるんじゃないかってくらい郁くんだって機嫌が良さそうに見えて、そんな郁くんを見てると顔中…どころか身体全部の筋肉が緩んじゃいそうなくらい嬉しくなってくる。
ずっとこうしていられたらいいなぁ
なんて夢見心地で郁くんにくっ付いていた僕なんだけど、
「いつまでこうして居られるのかな」
口から出た言葉は少し表現が変わってしまっていた。
すると、
「それ、どういう意味だ?」
低い声で目を細めた郁くん。
間近でジッと見つめられて、
「郁くん、去年は美人で頭の良さそうな人ばっかりと噂になってたから」
ふいに突いて出た言葉でさっきの岡部の言葉が引っかかっていたことにようやく気が付いた。
「それで?」
「…って言われても」
岡部の話の流れからすると、僕は遊ばれて、捨てられて、それから…
「お前、何か勘違いしてないか?」
僕を抱き締めながらの郁くんの言葉。
…勘違い?
「遊びだけのつもりなら、もっと適当な相手を選んでるさ」
つまり、
「僕は適当な相手じゃない」
ってこと、なんだろうか?
僕の髪へと顔をうずめ小さく笑った気配の後、
「それじゃあ、語尾を反転させただけだろう。俺の言ってる意味が…ってまぁ、いいか」
ため息交じりの言葉。
「…郁くん?」
不安になって顔を上げた僕へと、
「分からないならそれでいい」
だけど、
「それじゃ」
言葉の途中で唇を塞がれた。
………
さっきの熱を思い出させるよう、深く長く口づけられた後、
「俺が今、優也をどれだけ好きかってことは分かるんだろ?」
こんな近くで、そんな優しく見つめられたらもう…。
ふわふわとした心地のまま、こくりと小さく頷いてギュッと郁くんにしがみ付く。
郁くんは僕を丸ごと抱きしめながら、
「それだけで充分だから。俺にとってはそのままの優也でいいんだよ、無理して分かり過ぎる必要は無いんだ」
途端、何だか胸がすごく軽くなった。
だって…このままの僕でいい、って。
何もできなくて何も分からないけど、そんな僕でいい。ってことだよね、それは。
ありがとう、ありがとう、ありがとう
っていっぱいいっぱい思いながら、郁くんを抱く腕に力を入れた僕、
「郁くん」
「ん?」
「大好き」
クスっと笑うと、
「できれば愛してるの方がいいんだが」
言って頬に小さくキス。
「郁くん…」
言葉が咽喉まで出掛かったのに、期待たっぷりの瞳で覗き込まれてしまっては、
「…それはまた今度」
瞬時に吹き出されても言えないものは言えないよ。
「意外にケチなんだな」
「だってぇ…」
ふざけながらも優しい笑顔を向けられて、僕は甘えん坊に逆戻り。
…やっぱり、ずっとを望まずにはいられない。
って思いながら郁くんの手に僕の指を絡ませたりしていると、
「優也」
囁くような呼び掛けに僕は顔を上げる。
「初めて優也と会った夜な」
それは、郁くんが僕を救ってくれた夜のこと…
声のトーンが変わったから、真面目な話になるって分かったけど、
「俺は天使を見たと思った」
あまりに信じられない言葉に、
「僕のこと?」
訊き返さずにはいられない。
僕…が、天使?
「何よりも綺麗な瞳をした天使にもう一度会いたいって、あれから俺はずっと優也のことを捜してたんだ」
そのひたむきで、だけど静かで穏やかな声。
郁くんは本気で言ってくれてる、って感じられないようなら嘘だ。
「1年以上捜し続けてやっと手に入れた天使なんだ。そう簡単に手放したりはしない」
夢にさえ思わなかった郁くんの告白にジーンと胸が熱くなってきて、何だか涙が出てきそう…
「良く憶えててくれ」
黙ったまま、郁くんの腕の中で瞼を閉じた。
「俺は絶対に優也とのことを終わらせるつもりは無いからな」
翌日は雨の月曜日。
その放課後、僕は大切な用件を持って第2校舎の裏側に居た。
ちょっとした雨の切れ間ができたから、曇り空でも外に出たいと思ったんだ。
もちろん僕一人で立ってるわけじゃなく…
「分かってもらえないなら仕方無いけど」
最初に切り出したのはそんな僕の言葉。
下駄箱の傍で待ち伏せしてた僕に気付いた瞬間、はっきりと顔色を変えた岡部。
昨日の今日だから当たり前だと思うけど、少し離れた場所で立っていた郁くんの存在に気が付かなかったら、そのまま無視されていたかもしれない。
しばらく時間を置いた方が…って言ってくれた翠くんたちの気持ちも分かるんだけど、最終的に岡部がどんな結論を出そうとも勘違いされたまま納得して欲しくは無くて…。
「昨日はあまりにも僕の言いたいこととか思ってることが全然岡部に伝えられなかったから」
ふぅん、と軽蔑したような声の岡部は、
「で? 橘を連れて来たのは俺に対する嫌みなのか?」
だけど真っ直ぐに向けた僕の視線に岡部の視線が定まらない。
僕はゆっくり首を振って、
「僕の頭が良くても悪くても、そんなふうには回らないって知ってるんだろう?」
「…さぁ。どうだか」
俯く岡部。
伏せてしまった岡部の顔を眺めながら少し考えた後、
「そうやって本気じゃないのに悪ぶって見せるのは、郁くんを連れて来たから怒ってるってこと?」
ふん
と鼻で笑った岡部は顔を上げ、
「どうせ俺の信用なんて地に落ちたと同じなんだ。今更どう思ってもらっても構わないよ」
ポケットに手を突っ込み顎をしゃくるみたいに胸を張って見せた。けど、昨日みたいな意味の分からない怖さはどこにも感じられないから、
「じゃあ僕に申し訳無いと思うあまりに、ワザと悪ぶってるって思うことにするね」
言った僕を今度は呆れ気味に見下ろした岡部、
「お前、馬鹿なんじゃないか?」
返された言葉が意外にもなんだかおかしかった。
自分で分かっていても人に言われると腹が立つ言葉があって、それが本気でも嘘ん気でもやっぱり馬鹿って言われるとあまりいい気分じゃなかったのに、
こんな僕でもいいんだ
って思わせてくれた人が居るから。
「だから僕は岡部のことを信じていたいって思えるのかも知れないね」
言葉で嫌みな笑顔を消した岡部を見上げ、
「それと一緒で僕のことを好きだって言ってくれる郁くんを信じたいんだ」
「俺が昨日言ったことは」
僕はひとつ頷くと、
「それもちゃんと考えた。良く考えて考えて分かったのは、僕が郁くんを好きってことだった」
郁くんが待っていてくれてる方向に目を凝らして、
「岡部のことも好きだけど、でもそれは郁くんを好きっていうのとは全然別もの…。いつも一緒に居たいって思うのは岡部じゃなく郁くんで、もし岡部が言ったみたいに遊ばれてたとしても、それでもいいやって思えるくらい僕は郁くんが好きで、だから少しでも長く傍で一緒に居られたらって」
「…本当はノロケに来たのか?」
いつの間にか言い募っていた僕。
遮られた言葉で我に返ると岡部は軽い笑みを浮かべていた。
それは僕が1年間傍で見続けていた、僕の一番良く知っている柔かい笑顔だ。
「実際のところは」
コホンと小さな咳払いの後、
「悔しかったっていうのが本音かもな」
ポケットに突っ込んでいた手をさりげなく抜くと、腰に当て溜め息をついた岡部を僕は黙って見ていた。
「やること成すこと全てソツ無くこなして、どこに居たって人目を引いて…せめて腹ん中は真っ黒な奴。って思ってなきゃ俺みたいな凡人はやってらんないんだぜ」
「僕だって何にも無いただの凡人だよ」
ちょっとだけ苦笑いで言った僕に岡部は首を振りながら、
「優也は違う。上手く言葉で説明してやれないけど…、あの橘に選ばれたってことにもっと自信を持つべきなんじゃないかな。あいつを信じるって決めたんだろう?」
問い掛けながらも気まずく口の端を上げ、
「…なんて、フられた俺がなんでフった優也を慰めてんだか」
言葉の途中崩れかけた笑顔を無理に作り直した岡部の姿がすごく悲しく見えて、
「ごめん」
としか言えない自分が悔しくて…。
だけど、
「ごめんね、岡部」
って。
それ以上はやっぱり何も言えなかった。
小さな僕の呟きに頷くように無言で俯いた岡部。
僕は全然違う場所に落ちている石ころへと見るでもなく視線を置いたまま、二人ともしばらくはただ黙って立っていた。
どれくらいそうしていたか…。
ポツリ
とまた降り出した雨で僕が空を見上げた時、
「今、直ぐには無理だけど」
岡部が静かに口を開き、
「時間かけて気持ちの整理をちゃんとつけて、前みたいな友達同士に戻れるように努力してみるから」
言ったその顔はすごく穏やかで、
「また時々はどっか遊びに行こうな」
向けられた笑顔に僕は大きく大きく頷いた。
ポツリ、ポツリの間隔がゆっくりと…だけど確実に短くなっていく。
岡部の背中が見えなくなり、深呼吸と一緒に僕はもう一度空を見上げた。
本当にこんな日は空が低いなぁって…
心まで重い雲に押しつぶされてしまいそう。
「髪、濡れてるよ」
本降りになりかかっているのに傘も差さずにそこで待っていてくれた郁くん。
声に振り返るなり、先に僕の髪の雫をその長い指先でパサパサと払いのけ、
「どうだった?」
言って傘を広げてみせた。
それを僕に差し掛けながら、チラッと確認するかのよう僕が今やって来た方向へと視線を向けたから、
「岡部は向こうから帰ったんだ」
まだしばらくは郁くんと会いたくないからって…。
だけど、
「ちゃんと僕の気持ち、分かってくれた。今直ぐには無理だけど、また遊んだりしようって…」
岡部の優しくて、せつない笑顔。
郁くんから手渡された傘を受け取りながらも僕の口から知らず洩れた溜め息に、
「そっか」
静かな笑顔を向けた郁くんは短い言葉だけを返し、もう1本の傘をパンと開く。
せっかくの雨の日だから、肩を並べて歩きたかったんだけど…
郁くんのファンには狂暴なのが沢山いるから
って教えてくれたのは、確か臣くん。
…こんな人気の無い所から相合傘なんかで揃って出て行くわけにはいかない。
「俺達も戻るか」
僕を見ること無くそう言った郁くんが先に歩き出してしまうと、背中が傘に隠れて見えなくなってしまった。
仕方なくもう少し先に視線を移せば、けやき並木の向こうにあるグラウンドにはさすがに人影は見当らない。
そんな寂しいグラウンドに落ちてくる雨の重苦しさが、まるで岡部の涙みたいに思えて、
「もうヤだな、こんなの」
本気で好きになってくれたのに僕は謝る以外、何もできなかった。
また重い溜め息が出てしまうのが嫌で俯きかけたその時、
「そんな顔するな」
ちょうどけやき並木から出る一歩手前で振り返った郁くんの言葉。
「いつもの優也で居ればいいから」
傘の中、真っ直ぐに正面から僕を見据えた郁くん、
「いい奴に惚れた。って、岡部が胸を張れるような優也で居ればいい。笑顔の優也を岡部は好きになったんだ。何もできなくても、絶対に好きになったことを後悔させるんじゃないぞ」
僕は少しの間、郁くんを見入ってしまった。
だって、それは意外にも励ましの言葉だったから。
慰めてくれると思っていたから、最初は無言で小さく頷いてしまった僕だけど…
今の郁くんの言葉をギュッと胸の中で噛み締めて、
「ありがとう」
って次ははっきり言葉で返した。
岡部が好きになってくれた僕。
それは郁くんが好きになってくれた僕だから。
あと3秒で笑顔に戻るんだって確信を持って、僕は郁くんの隣に駆け寄った。
満面の笑顔でけやき並木を再度歩き出した郁くんは、やっぱりいつだって僕の一番を知ってる。
そんな郁くんの一番がずっと僕ならいいな。
…そう居続けるためには頑張らなきゃ、って。
僕が僕で居続けるために、強くならなきゃ…って、なぜだか力が湧いてくる。
人を好きになるって不思議なことだったんだね、郁くん。
ありがとう
夢の続きを見させてくれて
郁くんが見させてくれた夢の続きが、僕達の未来へと続く最初の一歩だったらいいなって、僕は心からそう願わずにはいられなかった。
そうそう、後日談ってことになるのかもしれないけど…。
郁くんとのことがあったその翌朝、そろって登校した僕達が学園最寄の駅から翠くんのマンションの前まで来ると、なんとなんと翠くんとよっくんがそこに立っていた。
だけど驚いたのは僕だけで、
「どうしてお前はそんなに元気なんだ」
いきなり両手で頭をグリグリしてきたよっくんはどうやら僕達の事情を知ってるみたい。
ってことはもちろん翠くんもってことになる。
二人が事情を知ってる原因は郁くんにあった…というべきか、その説明だと順序は逆で、僕達がこうなった原因にはよっくんと翠くんが居たんだ。
昨日岡部が来たって言った途端に切れた電話。
勘のいい翠くんが、よっくん→臣くんルートで郁くんに連絡してくれたんだって。
普通はあんなタイミングで郁くんが来た時点で疑問に思わなきゃいけなかったんだけど、どこまでいってもやっぱり僕は僕ってことなのかな。
その後学校に着くまでの間、ただただ僕達を冷やかすだけのよっくんを途中から郁くんに任せてしまい、ようやくって感じで僕の横に並んだ翠くんの、
「良かったね」
の言葉と笑顔にやっぱりまた嬉しくなった。
ありがとうって笑顔で返した僕に、
「でも大丈夫?」
今度は少し表情を落としての、翠くんの言葉の意味が分からない。
そういえばよっくんの第一声も気になるし、この言葉は夕べ…ってつまりあの後なんだけど、郁くんがやけに僕に問い掛けていた言葉だった。 だけに留まらず実はこの日、僕達の関係を知った少数の人全員が決まって同じことを僕に問い掛けるという不思議な現象に、常に傍に居た郁くんはただ苦笑いを浮かべるだけで何も説明はしてくれず、みんなに特異体質扱いされたまま結局僕は新たなる謎に首を捻るしかなかった。
それにしても一体何が
“大丈夫?”
だったのかな…?
作:杜水月
ホーム > 小説 > 某学園シリーズ本編 > ゆめのつづき
ご意見・ご感想・ご質問等は 杜水月 まで。
当サイトの無断転載はご遠慮ください。
![]()