Angel eyes
どこかで一人になりたい…
まだ親戚達でバタバタしている部屋から、優也は気取られないようそっと抜け出した。
例年より早めに訪れた春。
それでもまだ夜になると風が肌寒く感じられて、思わず身震いをしたがコートを取りに戻る気にもなれずそのままマンションを後にした。
優也の中学卒業式を待って、ようやく購入したマンションに引っ越したのがほんの10日ほど前。
両親の事故の連絡が入ったのはそれから5日後のことだった。
病院に駆けつけてから丸一日昏睡状態を続けていた両親は、ほんの数時間差で相次いで息を引き取ることになる。
遺体に泣きすがる姉の横でじっと優也は立ちすくんでいた。
親戚に連絡を入れ遺体を引き取り、葬式が無事済んでも泣けない。
周りに人が多すぎる
歩きながら知らず両親の姿が思い浮かんだ。
「市役所行ってくるから、ちゃんと片づけ頑張るのよ」
それが母の最期の言葉。
振り向きもせず二人で出て行ったきり生きては戻ってこなかった。
…仲のいい夫婦だったから
ゆっくりと思いを巡らすと、涙が込み上げてくる。
まだ歩き慣れない住宅地の長い塀を抜けた途端、思いがけず公園の脇に出た。
ライトにボンヤリ映し出される桜。
静かに足を進め、木の下から桜を見上げる。
そういえば去年は家族4人そろって花見に行ったっけ
来年はもっと盛大にやろうって、父さん弱いくせにお酒飲んで顔紅くして…
瞼を閉じるのと同時に大粒の雫が瞳から零れ落ちた。そのままその場にしゃがみ込んでしまう。
こらえきれない感情を押え込もうと頭を抱え込んで、それでも身体の震えは止まらない。
「嘘つき」
…震える声で小さく小さく何度もそう繰り返した。
「おっ、桜」
郁はアルバイトからの帰り道、偶然通りかかった公園で自転車を止めた。今年はまだちゃんと桜を見ていなかったことに気付き入り口の脇に自転車を置くと、公園の灯かりにボンヤリと映し出されている桜を眺めながらゆっくりと中に足を踏み入れた。
春の日差しの中でほころびる清らかさに相反して、どこか妖しさを漂わせる夜の桜。
ちょうど視線の先にあった公園備え付けの時計は10時を少し過ぎたところだった。
さすがにこんな時間に花見する奴もいないか
思いつつ視線を公園内に巡らせてみる。と、3本向こうの桜の木の下に在る何かで視線が止まった。
ゴミ、にしてはやけに大きい気もするが…何だろう?
確認するかのようにそれに焦点を合わせてみると、どうやら人が蹲っているようだ。暗がりではあるが雰囲気からして自分より少し年下の男の子だと判断した郁は、内心首を傾げながらその人影へと歩み寄った。
「どうした。具合でも悪いのか?」
人影はピクっと全身で震える。
かなり側まで寄っていたにもかかわらず、その少年は声を掛けられるまで郁の存在に気付いていなかったようだ。
「家、近くなんだろ? 立てないんだったら負ぶっていってやるから」
「……」
再度の呼び掛けにも、少年は返事をするどころか顔すら上げようとしない。
郁はひとつ溜め息をついた。
お節介は和臣の本分、自分は関係ないと思いながらも…結構面倒みのいい郁である。
「ほら、こんな時間にうろうろして補導でもされたらどうするんだ」
自分も充分それに値する年齢ではあるが、郁はそんなことはおくびにも思っていない。
なおも反応の無い少年に少し苛立った郁は、
「親御さんも心配してるだろうし…とにかく立て」
言って強引に少年の二の腕を掴んで引っ張り上げた。
「家で喧嘩でも…」
次の言葉を告げようとその顔を覗き込んで、郁はまともにうろたえてしまう。
もっとも少年の方はもっと驚いた顔で呆然と郁を見つめていたが、泣き顔を見たれたくないのか直ぐに顔を隠すように視線を逸らせた。
あまりに突然の出来事に郁は言葉が出ない。
「…だい…じょ…ぅぶ、です・・から」
辛そうにその大きな瞳から涙を流し、少年は捕まれた二の腕を振り払おうとする。思いの他強く抗われた腕に、次の瞬間郁は自分でも思ってもみない行動をとっていた。
………
衝動的に抱きしめてしまった
としか説明のしようが無い。
多分少年も何が起こったのか理解できていないのだろう。抱き込まれた腕の中で鳴咽も忘れて硬直している。
「…あっ、…あのっ…!」
「桜の木だと思えばいい」
戸惑う少年に不思議なくらい落ち着いた声で郁は告げた。
少年は何も言い返してはこない。
「落ち着くまで付いていてやるから」
それでもまだ硬直したままの少年の背中を軽く摩ってやる。
「ひとりで泣くな」
辛すぎる…
小さな囁きを少年の耳元に告げると、頭を手で抱え込んでやって郁は少年の髪に頬を埋めた。
しん…とした夜の黙。
静かに深い呼吸を繰り返す。
まるでその鼓動に聴き入るかのように、少年は郁の胸に頭を預けた。
軽く郁のジャケットを掴んでいた指が何度も何度も躊躇いながら、それでもやっとの思いで郁の背に回される。
その感覚が何よりも愛しくて、郁は抱き込む腕にぐっと力を込めた。
…やがて漏れはじめる小さな泣き声。
郁はやさしくやさしく少年の髪を撫ぜながら、心の片隅でずっと考え続けていた。
何か…変だ
何だろう、この感情は
こんなに近くに居るのにもっと近づきたいと思う
全て受け入れて許してしまいたくなる
自分の全ても委ねたくて…
このままずっと離したくない
今まで抱いたことの無い充実した幸福感
…この想いは、なんなのだろう
「人はそれを恋と呼ぶんだ」
高校生活初日
幼稚園からの腐れ縁、松前和臣はその笑顔の仮面を貼り付けたままこの高校生にしては超越したような秀麗な容姿の持ち主・橘郁にそう言ってのけた。
「お前良くそんなセリフを真顔で…」
「ははは、笑顔だぜ」
「言葉遊びをしてる場合か」
郁は呆れ口調。
「余裕が無いのは本気の証拠、ってね」
「そうは言うけど、お前おかしいと思わないのか?」
郁の言葉に相変わらずの笑顔で何がと訊き返す和臣。
「相手は男なんだぜ」
「郁にしては随分弱気な発言じゃないか」
「あのなぁ…」
郁は反論しかけて諦めた。
和臣はたいていの物事には動じない。
「そもそも性別云々より先に、昔からモテ過ぎて恋愛感情がどこかぶっ壊れてんだよ、お前は…。遊び相手は星の数だが、一度だって本気で誰かに惚れたことなんて無いだろう?」
随分な言われようだ。
黙って視線を向けた郁へと、
「まぁそう睨みなさんなって。そこそこ俺は喜んでるんだ、ようやく訪れた幼馴染の初恋に」
言いながらもその笑顔を更に濃くして、
「俺の必殺の情報網でその“桜の君”さっさと見つけ出してやるからさ」
言葉に郁はすんなり怒りを収めた。
和臣の行動力と実力を誰よりも理解しているのだ。
彼の人脈の広さを考えれば、これ程頼りになる人材も無いだろう。
同性愛に対して抵抗が無いと言えば嘘になるが、それでももう一度…と願わずにはいられないのも事実だ。
初恋、と言われれば確かにそうなのだろう
…そう簡単に諦めたくはなかった
「はぁーるのぉ うらぁらぁのー すぅみぃだーがぁーわ〜」
入学式から2週間目のある休み時間。歌詞に不釣り合いな低いだみ声をBGMに優也はボンヤリと中庭を見下ろしていた。
次の授業は体育なのだろう。校舎からジャージ姿の生徒がワラワラと出てきている。
ここの学校、単パン・ブルマーじゃ無いところがいいよな、そんな格好させられちゃ小学生に見られてしまう。
なんて思いながら視線を生徒達に泳がせていた優也が、ある1点でピタリと止めた。
視線のその先にはやけに人目を引く二人の男子生徒が何やら話しながらグラウンドのほうへと向かっていた。
「ねえ、あそこに居るのって…」
優也は微かに震える声をどうにか気取られないよう努力しながら、隣でまだ歌い続けている岡部に声を掛けた。
岡部は優也の視線の先を辿り、なるほどといったふうに頷いてみせる。
「小西は入学式休んでたから知らないか」
両親の不慮の事故で優也の初登校は人より1週間遅れていた。
「右の男前の方が主席入学の橘郁、でその左にいる笑顔の男が松前和臣。二人共入学前から超有名人らしいぜ、橘なんかはファンクラブができるとか、できたとか…」
それから後の岡部の言葉は覚えていない。
どう見ても見間違いようが無いのだ。
明らかにあそこで目立っている岡部の言うところの“たちばなかおる”とやらはあの時の青年だ。
つい3週間程前、見ず知らずの人だったにも関わらずその胸にすがって泣いたあの時の…。
思い出して顔が紅くなる。
優也はとっさに俯いて頭を抱え込んだ。
まさか同じ学校だったなんて…
大学生くらいかと思ってたのに。
確かにお世話になった人だけど、あんな情けない姿を同級生に見られたなんて恥ずかしすぎる。どこかでばったり会って向うが憶えてでもいたらなんて言えばいいんだよ。その節はどうもありがとうなんて絶対絶対言えないよぉ…。でも、お世話になった人にはお礼を言うのが常識だし…。
あーでもでもでも。困った困った…しどろもどろになって笑われでもしたらもっと恥ずかしいし、同級生だと思われる方がもっともっと恥ずかしいかも。いやいや恥ずかしいのはそうじゃなくって…いやそれも恥ずかしいんだけど…
などと混乱しながら余計なことを散々考えて、考え疲れて出した結論が、
そうだ、会わなければいいんだ
だったのだ。
切に1年間想い続ける羽目になった原因がこれでは、郁にはあまりにも気の毒な話である。
さて、それから1年後のある日
『残念ながら収穫無しだ』
入学式の夜、和臣の電話での第一声。
その声に郁は思わず溜め息を洩らしてしまう。
1年経っても忘れられないどころか、会えないことが更に郁の想いに拍車を掛けていた。
どういうわけかあの後、和臣の情報網を持ってしても例の少年は箸にも引っ掛からなかったのだ…と、まぁ優也が意識的に二人から必死で逃げ回っていたのだから当然の成り行きではあるのだが…。
『あの辺りの中学は該当者無しだったよな。まさか小学生ってことは?』
郁は小さく苦笑い。
『…それはないと思う』
初めて会った時はその可能性も考えたが、二度目に駅で見掛けた姿はどう考えても小学生には見えなかった。
『県高の方に行ったか…。これだけ捜して見つからないんだ、最悪は錦木の辺りに知り合いでも居て、実際住んでる所は別ってことになるなぁ』
県高とは一駅離れた所にある学園と同名の公立高校のことだ。あまり評判が良くないためか少しお金に余裕がある生徒は大抵学園の方に流れてきている。
『県高だったらどうにかなるが、そうじゃなかったらもうお手上げだ…』
珍しく和臣が声に表情をつけて呟いた。和臣は忙しい中“桜の君”探しにかなり奔走してくれたのだ。郁も和臣の苦労を考えると嘆いてばかりもいられない。
『仕方ない、縁が無かったんだ』
自分に言い聞かせるように呟き、また洩れそうになった溜め息をどうにか押し殺した。
この想いをまた繰り返すのはかなり辛い。
だからといって今更諦め切れるはずも無く悶々とした気持ちのまま高校生活2年目をスタートさせた郁だったのだが、始業式から間も無い頃、ひょんなことから待ち人は現れることになる。
それは、ある特別教室での授業前。
南北に伸びる第2校舎、最南端にある教室。この校舎からグラウンドが見える数少ない教室なのだが、その窓からグラウンドを眺めている森丘美都に和臣が声を掛けた。
「類は友を呼ぶとは言うが…、あの二人がつるむようになるとは俺でも予想外だったよ」
美都とは1年の頃から付き合いの有った和臣と郁だ。こっちが自然とつるむようになるのは意外な話ではない。
で、彼が眺めているのは1年生の間に相思相愛になっている佐伯翠。
男にしては美人という形容が当てはまるほど綺麗な顔立ちをしている。
入学したての頃はその美貌を7割減させるようなダサい眼鏡をしていたが去年の秋頃からその仮面を取っていた。
それと時を前後して起こった1年2組での大乱闘事件の原因が、彼に有ったという事実を知っている人間は意外に少ない。元凶は未だに自宅療養中になっている。
それでも密かに噂というものは広がるもので翠はその頃から結構学園では有名人になっていた。
そしてその彼と肩を並べているのが“小西優也”。
翠もそれ程背が高いほうではないが優也はそれよりも更に肩を低くしている。
遠目からでもはっきりと解る大きなその瞳は、今時の女子高生より遥かに綺麗で澄んだ色を湛えているのだ。
「俺もビックリだよ。この間7組行った時なんかマジで絶句したんだぜ」
「周りの女子の影、薄くなってただろ?」
美都は苦笑いで頷いた。
「初めて近くで見たんだが、思わず抱きしめてしまいたくなるって表現は中々的を得てるぞ」
それまで何気なく二人の会話を聞いていた郁だったが、
“思わず抱きしめてしまいたくなる”
のフレーズにほんの少し心動かされるものが有った。
特にその意味を確かめるつもりも無いまま、ゆっくりと二人の視線の先を追う。
「おいおい、佐伯以外の男には反応しないんじゃなかったのか?」
「小西は何か独特だよ、父性愛を呼び起こすというか…。松前は何とも思わないのか?」
どうだろうか…
和臣は目を凝らして優也をじっと眺めている最中、ふとある疑念が浮かんだ。
あれ?
「橘君、どうしたの?」
声に和臣の疑念は一端打ち消されてしまう。
にこやかに輪の中へと入って来たのは学年一の美少女・白河亜美。 進学クラスの数少ない女子なのだが、彼女一人で他のクラスの何倍も華やかな気分にさせてくれるという有り難い存在だ。
和臣と美都は彼女の言葉で初めて郁が呆然と窓の外を眺めていることに気が付いた。
郁は心ここに有らずといったふうに窓ガラスにへばり付いているではないか。
あまりにらしくない郁の行動に3人共黙ってしまったが、それでも直ぐに和臣が呼びかける。
「…郁?」
応答の無い友人の視線の先を一瞥で確認した和臣は、
「おい」
少し強めに郁の肩を引いた。
「…えっ、あ。 何だ?」
郁は夢から覚めたような面持ちで、和臣にどうにか視線を向けて見せた。
「立ったまま寝るんじゃない」
言葉に素早く郁は立ち直ってみせると適当に笑って誤魔化してみる。がしかし1組は頭のいい生徒ばかりの集団なのだ、これで二人が誤魔化されたかどうかは定かではない。
そしてその日の夜
和臣が久し振りに郁の家に遊びに来ていた。
お互い何かと忙しい身の上なのだ、詰めた話をするには学校では少し無理が有った。
別に美都や亜美を信用していないわけではないが、そうおいそれとできる話の内容でもなく、特に美都には殴られてしまいそうな内容なのだ。
「…まさか小西だったとはね」
言いながらの和臣はペットボトルの水を一口。
「未だに信じられない…、暫く森丘には黙っててもらえるか?」
和臣は笑って頷いた。
郁の大本命捜しに美都も手を貸してくれていたのだ。去年その相手が学園の生徒じゃないと断言した手前、同じ学校のしかも同級生でしたとはさすがに言い難い。
「それにしてもあんなメジャーな小西のことを1年間気が付かないなんてとんでもない話だ」
「仕方がないだろう、会わなかったんだから」
これに関しては和臣にも若干思い当たる節があった。
学校で浮かんだ疑念の延長なのだが、和臣自信顔は知っていても優也とは会話をしたことが無い。もっと言うなら出会ったことが無かったのだ。自ら会いに行く用向きが無かったにしろ有名人どころか凡人にでも平気で声を掛けまくる和臣が、すれ違ったことも無いというのはかなり解せない。
メンツにかけてもこの答えは明日確かめようと思っている和臣だった。
「まぁ責める気はないが…」
「で、何か解ったか?」
余裕の笑顔を浮かべた和臣は、
「名前は言わずと知れた“こにしまさや”。大中小の小に東西南北の西、まさやは優れるに也(なり)だ」
郁は直ぐに文字を浮かべて頷いてみせる。
「2年になってからはクラス全員に名前で呼ばれてるらしい」
郁は眉を上げた。
「何でまた」
「7組には小西がもう一人居て、紛らわしいからということになってる。一応は」
「一応?」
「小西のシンパはどこにでも居るんだよ。これ幸いに名前で呼んでみたかったってのが本当の理由だそうだ」
少し間を置いて和臣は続ける。
「自宅は郁が会ったあの公園の傍にある新築のマンション。去年の春先、飯桐市から引っ越して来てた。捜し難かったのは多分そのせいもあるな。家族構成は6歳上のお姉さんとの二人っきり」
「家庭環境複雑ってことか?」
ゆっくりと首を振る和臣。
「事故で一度に両親亡くしてるんだ、それが入学式の少し前」
その言葉に郁は顔を上げて和臣を見やった。
「小西は容姿のわりに中々に負けん気が強いって聞いたことがあるんだが、それでも両親の事故死は相当堪えただろう。泣き叫んだっておかしな話じゃないさ」
郁は去年のあの日に想いを馳せる。
小さな肩を震わせてしばらく泣き続けていた。きっと誰に縋ることもできなかったのだろう。
それでもようやく泣き止んだ優也は家まで送ると言った郁の申し出を頑として拒み続け、小さく頭を下げるとそこから走り去って行った。
「去年の入学式で小西を捜し出せなかったのは事故のせいで小西が欠席していたからだったよ。なんか色々な偶然が邪魔してたみたいだな」
郁はそれでも嬉しそうだ。
ようやく巡り合えた想い人なのだ、1年間待っただけあって感慨も一入なのだろう。どうやって声を掛けようかと郁が算段をしていると…
「郁には悪いんだが最初は俺に任せてもらえるか? 実はあいつとは早いうちにコンタクトを取りたかったんだ」
「何かまずいことでも有るのか?」
「ちょっと…、いや。かなりかな」
和臣の瞳が僅かに曇る。
「佐伯の事件憶えてるだろ? 崎田を休ませることでそれなりに事件は穏便に片付いたように見えるが、ハイエナみたいに嗅ぎ付けてくる奴はいるもんでね。お前も知っての通り全校生徒を集めるとその気のある奴は意外に多い。おまけにあの後佐伯が眼鏡外したもんだから、小西より評判になってた時期があったんだ」
「それで?」
「世のセオリーだが、決まった相手ができると人気は下火になる」
「森丘との噂ね」
噂をそれとなく流したのは和臣だが、そのきっかけを作ったのは郁である。その経緯を思い出し郁は苦笑いを浮かべた。
「真相を知っている人間は殆どいないが、森丘の効力は想像以上に大きかったんだよ」
「あいつのバックは強力だからな」
美都は入学当時から和臣達とは別の意味で一目置かれていた。ただ単に目付きが鋭いだけであれだけ周りが恐れおののくわけは無いのだ。それなりの理由が有る。
森丘三兄弟は全員この学園出身なのだが、中でも長男の清志は在学当時かなりこの界隈でその名を轟かせていた。
美都に輪をかけたようなその鋭い眼光でかなり因縁をつけられる人生を送ってきたのか、やたらと喧嘩には強かった。特に悪さをしていたわけでもないのに、
学園に森丘清志有り
という言葉は未だに裏の世界では語り継がれているのだ。
「小西の評判があの程度で済んでたのは、去年までは3年生に似たようなタイプがいたことと、1年の時の岡部って友人がかなり強力にガードしてたからだ。だが今年度からはそうはいかない。岡部とクラスは別れたうえに新入生を見た限りじゃ同系はいない。思わず抱きしめてしまいたいだけの正統派はそれでいいんだが…」
言葉を切った和臣に郁は続きを促す視線を向ける。
「2年になって佐伯とつるみ出したものだから、今まで以上に人目を引いてる。その上小西がフリーだってことは周知の事実なんだ。無理矢理犯っちまいたいって奴、俺の知ってるだけで両手の指じゃ足りないくらいいるんだぜ」
マジかよ…
郁は眉間を寄せ瞼を閉じた。
「崎田みたいに単独ならまだしも、そいつ等が束になってみろ。俺の情報網でも限界が有るんだ」
それは身を持って経験している郁である。
「いつどこで犯られてもおかしくないわけだ」
「おまけに小西本人はそのことに自覚が無い。早いところ何か手を打たないと、先々どうなるかは目に見えてる」
今日わざわざ和臣が訪ねて来たのには、そういう事情も有ったのだ。
遠目からでも分かるあの綺麗な瞳の少年を、そんな奴等に犯させるわけには行かない。ましてや郁の初恋の君となるとなおのことである。この1年間郁がどれほど想い焦がれていたかは、充分すぎるほど理解しているのだ。
「まずは俺達の庇護の下ということをアピールするところから始めるとするか」
ペットボトルの水を飲み干した和臣は、それでも少し楽しそうにしていた。
昨夜学園の名物コンビの間でそんな会話がされていたなどとは夢にも思っていない優也は、その日もごく普通の朝を迎えた。
残業やら飲み会やらで毎晩遅くに帰って来て出勤ぎりぎりまで寝ている姉のためにお弁当を作り終えた優也は一人で朝食を取る。
両親が死んだ後しばらくは…特に食事時に寂しさが堪えたが、人間どんなことでも時間が解決してくれるものだ。いつの間にか寂しさに慣れてしまっている。
優也は食べ終えた食器をシンクの洗い桶に浸けると簡単に身支度を済ませマンションを後にした。
入学当初は引っ越して来たばかりでこの辺りに知り合いはいなかったのだが、去年の6月頃から同じ駅を利用しているクラスメートと一緒に登校するようになっていた。
いつものように駅横のコンビニの前で落ち合うと改札をくぐり混雑している人の列に付ける。重そうに滑り込んで来る電車を見やり、吐き出された乗客に次いで電車に乗り込んだ。
中学時代は学校が近かったため電車通学は高校からの初体験。
それにしても満員電車というものは毎朝乗っていても慣れるものじゃない。乗車区間が短いだけまだマシだろう。
急行電車一駅目で二人は下車し、人の波に流されながら制服フリーパスの特設改札を抜けて学校に向かう。
いつもと違ってくるのはここからだった。
駅前のロータリーを抜け住宅街に入った所で、
「小西優也っ」
突然声を掛けられて…。
真後ろからの呼び掛けに反射的に振り向いて、声の主を確認すると優也は一にも二にも無く走り出そうとした。が、相手もそれを予測していたのか優也が地面を蹴る間もなく、その腕を掴み取っていた。
「そうやって1年間逃げ回ってくれたわけだ」
相変わらずの笑顔で言ったのは和臣。
「え!? なっ? だっ…」
あまりの出来事に優也は意味不明の音声を発し、口をぱくぱくしている。
それでも目だけはキョロキョロさせて何か捜してしまうのは、これも既に条件反射なのだろう。
「郁は居ないよ」
再び図星を指された優也はその大きな瞳と口を開けたまま固まってしまった。
その仕草に内心和臣は笑みが零れる。
なるほど、抱きしめたくなるようなとは頷ける
「悪いが先に行って貰えるか?」
優也の友人は和臣のその言葉ににっこりと頷くと手を振ってスタスタと歩き出して行ってしまった。
幾ら優也が縋るような目を向けたって相手がかの有名な松前和臣では仕方が無いことだ。待ち伏せされていただけでも光栄と思えといったところか…。
「…腕、離してもらいたいんだけど」
郁が居ないことがまだ救いだったのか優也は思いの他、早く気を取り直すと果敢にも和臣に抗議した。
こんな通学路の往来で和臣に腕を掴まれているのだ、目立って仕方が無い。と優也は思っているが、その原因の半分が自分に有るなどとはこれっぽっちも考えてはいない。
「逃げないって約束するなら離してやろう」
「だっ、誰が逃げるんだよ!」
「お前しかいないだろうが」
掴まれている腕が何よりも逃げたという事実を物語っているのだ。言葉に詰まった優也へと、
「返事が無いなら、夕方までこうしてようか?」
更に追い打ちを掛けた和臣の発言は脅しのようだが、冗談半分でもない。
小西優也は松前和臣と何かしら繋がりが有ると思わせておくだけで、それなりの効果は有るのだ。
「…逃げないよ」
ついに諦めて肩を落とした優也の様子に和臣はあっさりと掴んだ腕を放し、
「じゃあ行こうか」
路面に落としてしまっている優也の鞄を拾い上げる。
次いでパンパンと埃を軽く掃ってその小さな胸に押し付けると、
「ありがとう…」
小さく呟いた優也は鞄を胸に抱き込みながら先に歩き出した和臣の後に付いた。
和臣がどういう目的で自分を呼び止めたのかは解らないが余計なことを喋ってあらぬ詮索をされたくはない。優也の口と足は自然と重くなり…
「…なぁ」
歩き出して直ぐの和臣の言葉に、
「えっ!」
そんなに驚かなくても、というくらいびっくりしてみせ数歩横に飛び退いてしまった。
せめて後5歩は時間が欲しかったようだ。
片や、
ちょっと利きすぎたか…
そう思ったのは優也の様子を若干目を細めて眺めながらの和臣。
優也に逃げ回られていたおかげで和臣と郁は随分と無駄な時間を費やしたのだ。郁はともかくとしても和臣の方は、多少それについて報復心が湧いても仕方が無いだろう。
つまり和臣はほんの少し怒っていたわけなのだ。
「だれも取って食やしないって」
いつもの笑顔に少しだけ優しさを乗せて視線を向けてみたけれど優也には余り効果が無いようで、力一杯鞄を抱きしめている優也を横目に和臣はまた歩き出した。
予定通り優也は直ぐに追いかけて来たのだが…。
「ごめん…、何?」
追いついた優也の素直な謝罪。この素直さも人気の要因の一つなのだろう。
「優也…」
呼び掛けにまた驚いてはいたが、それでもどうにか持ちこたえて優也は和臣を見上げた。
「でいいか?」
「…構わないよ」
優也に拒否する理由は何も無い、今のクラスでは皆にそう呼ばれているのだから。
「2年になってからだよな、名前で呼ばれてるの」
「うん」
「最初に名前で呼んだ奴、誰か憶えてないか?」
「は?」
あまりに唐突で意味不明な質問。
けれど、
「最近のことだ、思い出せるだろ?」
そんな優也に構いもせずに続けた和臣から視線を逸らすと、戸惑いながらも仕方無しに優也は首を捻って記憶の糸を手繰り寄せる。
確かにそれほど前のことじゃない。
あれは…あの時も今日みたいに突然名前で呼びかけられて、驚いて振り返ったんだ。
“向こうの小西とややこしいだろ?”
そう言ったのは、
「…由岐」
優也の言葉に和臣は顎に指を当てて考える。
「仲いいのか?」
優也は首を振ってみせた。
「まだ、あまり話したこと無い…」
ブラックリストには今のところ載ってはいないが調べてみる必要は有るだろうと目を細めている和臣に、
「でも、何で?」
質問の意図がどうしても掴めずに漸う優也は尋ねてみたが、
「深い意味はない、気にするな」
その笑顔であっさりと躱される。
そのまま正面を向かれてしまいこれ以上取り合ってくれそうにはない。 けれど、
「松前」
学園の有名人がわざわざこんなことのために朝から待ち伏せしていたとは到底思えない。
幾ら鈍感な優也でもそれくらいの疑問は浮かぶのだ。
「他に何か…」
「臣でいいよ」
「えっ」
せっかくの問いかけは途中で中断され優也は今朝何度目かの驚きを顔に出すと、慌ててブンブン手と顔を振った。
「とんでもないっ!」
彼を臣と呼んでいるのは郁くらいしか思い当たらないのだ。
すると呆れ顔の和臣が、
「いちいち大袈裟に驚く奴だなぁ。俺もお前のことを名前で呼ぶんだから、大したことじゃないだろう」
翠にも同じことを言われて既に実行している優也である。
和臣がそんな事情を知っているはずはないのだがやはり言い返せない優也だった。
「…くん付けでいいかな?」
「結構。それから」
和臣は人差し指を立ててみせ、
「今後誰かに俺とのことを尋ねられたら友達だって答えろ」
「でも今日はじめて話したばかりだよ」
「時間の問題じゃない。ついでに郁のこともだ」
郁の名前を不意に出されて優也はギョッとしてしまう。
「後…」
「まだ有るの?」
さっきから心臓に悪い注文ばかりつけられて優也の口が思うより先に動いたって仕方が無い。
「これで最後。郁のことも名前で呼べよ」
疲れた…
結局和臣の一方的な条件をすべて受け入れることになった優也。
これでは郁と顔を合わすのも時間の問題となるだろう。
一体何の因果でこんなことに…
よろよろと下駄箱で上履きに履き替えていると、
「おはよう」
良く知っている声に優也は安堵の表情で振り返る。
「朝から疲れてるじゃん」
言いながらその美貌で微笑んでみせたのは翠、そしてその隣には当然の如く美都がいる。
じゃあなと自分の下駄箱へと向かう美都に向かって翠は軽く手を振った後、
「さては寝坊でもしたな?」
上履きを出しながら優也に視線を移した。
普通に登校していれば、翠達とは会わない時間帯に登校している優也。出会ってしまった原因は和臣に有るのだが…。
さっきの会話を思い出すと優也は返事も忘れて大きな溜め息を一つ。
「…何か有った?」
優也の様子に翠は不安顔で尋ねる。
一瞬どうしようかと迷った優也だが思うことが直ぐに顔に出てしまうことには本人にも自覚が有る。優しい上に良くしてくれている翠に嘘もつきたくはなかった。
「あのさ」
何? と首を傾げた翠に、
「ま…」
松前と言いかけて、こういう場合松前でいいのだろうかと俄かに躊躇。
「ま?」
その訊き返しに優也は困ったふうに視線を向ける。
臣と呼べと言われたことを思い出し、
「お」
けれど言い難い。
「お?」
適当な言葉も見当たらず、
「あー…」
「あ?」
翠も困惑の表情を向けた。まともな高校生の会話ではない。
階段の踊り場で立ち止まってしまった二人だが、奇妙な会話につい吹き出してしまったのは翠の方だった。
「話し難いんだったら無理に話さなくてもいいよ」
笑いながらもさり気なく優也を気遣ってくれる。そんな翠だから優也は安心できるのだ。
どうにか気を取り直した優也は、
「そういうわけじゃなくって…。松前和臣って知ってる、よね?」
悩んだ末のフルネームだった。
「うん、有名人だからね」
「今朝何故だか呼び止められたんだ」
翠は特に驚く様子も無い。
「松前は人に声掛けるの趣味みたいだよ」
なんて迷惑な趣味なんだ。勝手に友達になったり、名前呼ばせたりすることが趣味なんだろうか。
と眉間にしわを寄せながらの優也は、
「友達多すぎて困らないかな」
再び翠は笑う。
これだから優也は面白い。
「ここのキャパが違うんだろうけど…」
翠は頭を人差し指で二度ほど突ついてみせ、
「松前の場合声掛けるのには、それなりに意味が有るみたいな気がするよ」
「意味…?」
優也は今朝の会話を思い浮かべてみるが、どこにどんな意味が有るのか皆目見当が付かないでいる。
「何て言われたの?」
「友達って言えって」
「松前のことを?」
「うん」
翠にとっても意外な言葉だった。わざわざそんなことを強要するような和臣ではない。
それでも優也より遥かに予備知識のある翠だ、それなりに見当をつけて、
「そんなに困ることないと思うよ。僕も去年助けてもらったことが有るし、橘共々あれほど強い味方いないじゃん」
言いながら翠は少し表情の色を落とした。
優也の噂は以前から知っている。裏での人気は自覚のある翠より遥かに高い。それなのに優也のこの無警戒さときたら…。
しっかり見ててやらないと狼が布団担いで枕持って誘いに来たって平気で付いて行ってしまいそうなのだ。
崎田の事件以降美都との噂が有るにも関わらず自分にちょっかいを出してくる奴はいる。そういう奴は翠でも予測不可な人物が多い。
つまり和臣がそこまでするということは…
かなり良くない状況ってことだ。
この時翠は自分の思考にとらわれて橘という単語で優也の顔色が変わったことをすっかり見落としてしまった。
二人して心痛な面持ちで教室に入ると揃って席に着く。席が前後ろなのだ。
つるむようになったのも真ん前が教卓で話し相手がいなかった優也がしょっ中後ろを振り向いていたのがきっかけだった。翠も1年生の時の友達とは見事に離れてしまったため新しい友達を作る必要があったのだから、これもある意味当然の成り行きだろう。
「優也…」
後ろ向きで翠の机に肘を付いていた優也は、まだ何か悩みが有るのか重たげに頭を上げると、
「知らない人に付いて行っちゃ駄目だよ」
翠の言葉にキョトンとして、
「そんなに子供っぽく見えるかなぁ」
少し拗ねてみせた。
そんな優也から視線を逸らした翠は少し哀しげに表情を落とす。
どうしてこんな無垢な心を壊してしまおうと思えるんだろう…
「今日は4時間目が早く終わったから余裕だな」
昼休み開始のチャイムと同時に昼食を食べ終えた郁は何時になく上機嫌だった。
「只今の発言には訂正及び表現が不足している箇所が有ります。正しくを5秒以内に答えなさい」
「今日の4時間目は俺達が無理矢理早く終わらせたから、普段より10分も余裕を持てたな」
含み笑いで質問を投げかけたのは亜美。で、回答したのは弁当箱を片づけながらの美都。
昼休みのグラウンドは競争率が高い。いい場所を確保するには誰よりも早くグラウンドに出る必要が有るのだが今日の和臣と郁には、その前に一仕事しておくべきことが有った。
「はははは。まぁいいじゃないか、愛しの君に早く逢えるんだから」
茶化し口調の言葉に美都は軽く和臣を睨んだ。もちろんそんなことに動じる和臣でもない。
「さてと…」
それでも一応3分待ってみせてから全員が席を立つ。
向かう先は階下の7組。
翠と優也の教室だ。
どうやら7組も少し早めに授業が終わったようで既に教室に出入りする者も無く入り口は閉められていた。
自分のクラス以外の教室に入る時は大概の人間が躊躇する物だが、そこは有名人達の集団。軽快なノックの後、美都は躊躇いも無く派手に扉を開けた。
当然クラス中の注目を浴びたのだがその隣に松前和臣、やや下がって白河亜美、窓側の壁に凭れているのが橘郁とくれば教室内は嫌でも色めきたつ。
直ぐに視線を向けた翠へと美都は笑顔で手招き。休み時間に携帯電話にメッセージを入れておいたお陰で、翠は直ぐに席から立ち上がったのだが…
「まーさやっ」
心の準備が全くできないまま椅子にへばりついているのは優也。
和臣にこれ見よがしに呼びかけられても身体がいうことをきかない。
何故なら、そこには郁が居るから。
けれどそんな事情まではまだ把握しきれていない翠には、どうしてそこまで優也が躊躇しているのかが解らない。
何にしろ和臣が自分達を傘下だと印象付けようとしてくれているのだから、ここで優也一人を置いて行くわけには絶対行かない。
「早くしないと怒鳴られるよ」
和臣はもちろんそんなことをしないのは知っている、怒鳴るとすれば美都だろう。
翠の言葉に優也の方は今朝のやり取りを思い出し落胆の表情で席を立つ。翠に背中を軽く押されながら美都と和臣の間を通りぬけると教室の扉がピシャッと閉められた。
美都と翠それに亜美が先に歩き出すと和臣は少し送れて後ろから翠を呼び止める。翠も予測していたようで直ぐに二人は並んで歩き出した。
残ったのは郁と優也だ。
郁の視線にどうしていいか解らずに優也は扉に背中をつけたまま瞼を閉じてしまった。
心の中で3秒数え、思い切って開いた瞳が映したもの。
それは…
窓から射し込む光の粒がキラキラと散舞する中、郁はゆったりとその輝きを湛えたまま優也に微笑んでいる。それはあの晩薄明かりの中で見た時よりも、ずっと澄んで美しく見えた。
人間綺麗なものの前では自然と笑みが零れるのか、あれだけ警戒していたにもかかわらず知らず優也も微笑んでいた。
すごく…きれい
半分陶酔感に浸りながら、その容姿をもっと見ていたいという優也の希望はもろくも崩れ去ってしまう。
「ど、うしたんだ…」
驚愕の表情で歩み寄られて、
「あれ?」
優也は初めて自分が涙を流していることに気が付いた。
慌てて涙を拭うと、郁を安心させようともう一度微笑み返して見せる。
感動して泣くなんて…
優也の笑顔で郁は安堵の表情を浮かべると4人の行った先をちらっと横目で見て、とっくにその姿が見えなくなっていることを確認すると、
「ちょっとふけるか?」
にっこりと微笑んだ。
躊躇いもなく頷いた優也はあんなに逃げ回っていたことが嘘みたいに、すんなりと郁の存在を受け入れてしまった。
程なく郁は和臣達とは逆方向に歩き出し第2校舎とはL字につながる第1校舎を抜け玄関ホールも素通りし…着いた所は図書館だ。
第1校舎と平行に並ぶ第3校舎を挟み東側に位置する図書館に行くには、その西側に建っている第2校舎からは少し遠回りな道のりをとったのだ。
グラウンドの脇を通った方が早かったのに…、知らないのかな?
と内心首を捻っていた優也。
4人を避けるために郁がわざとそうしたことに全く気付くはずも無い。
図書館の1階、自動販売機の前で立ち止まった郁は、
「何がいい?」
振り返って優也に尋ねた。
「昼飯、まだなんだろう?」
郁は優也が手にぶら下げている弁当箱をちらっと見る。
「じ、自分で買うから…」
慌てて優也が一歩踏み出したがそれを笑顔で制した郁は、ポケットから取り出した5百円玉を投入口に入れた。
好きなものを選べと言わんばかりに自販機の前を譲る郁に優也がもう一度視線を向けると、
「次回は期待してるよ」
その端正な瞳で見つめられ黙って言葉に従った。
さして迷わず優也は日本茶を選び次いでホットコーヒーのボタンを押した郁。
そのままコミュニケーションルームに腰を下ろすのかと思いきや、予想に反して階段に向かった郁の姿に首を傾げてしまう優也。
確か図書館って…
「物食べちゃ駄目だったと思うんだけど」
「良く知ってるな」
少し関心しかけた郁だが、
「前に怒られた」
どうやら優也は前科持ちのようだ。
「今日は大丈夫、図書館には驚くような穴場が有るんだぜ」
向けられた笑顔に、
郁が言うなら間違いはないだろう
漠然とした安心感を胸に優也は郁に付いて階段を上った。
2階…3階……4階、
「ちょっと待ってろよ」
そのまま踊り場で待つこと数分。戻って来た郁は更に階段を上る。
「……?」
図書館って4階までじゃなかったっけ?
不思議に思ったものの持久力が人よりかなり乏しい優也は、息が上がっていて尋ねる気力がない。郁は“関係者以外立ち入り禁止”の看板をちらりとも見ず最上階への鉄扉の鍵を開けた。
どうしてそんなものを…
思いながらそこに足を踏み入れた優也は、
「うわぁ…」
疲れも忘れて驚嘆の声を上げた。
下から見るとコンクリートの柱しか見えずただの屋上だとばかり思っていたのだが、外周を観葉植物で覆われた内に教会を思わすような建物が有った。壁の上3分の1は傾斜のついた硝子がはめ込まれていて、屋根はアーチ状になっている。
中に入ってみると本当に教会のように清楚で崇高な雰囲気が漂い、天井を見上げるとアーチの大部分は明かり取りのためかガラス張りにしてある。誰のために設けられているのか壁側に背の低い書棚が並び、それに挟まれて閲覧用の大きな机と座りごごちが良さそうな椅子が整然と置かれていた。
「驚きだろ?」
その大きな瞳を更に大きく見開いて頷いて見せる優也。
郁はその反応に満足そうに微笑んだ。
「ここは特別な人用に設けられた部屋なんだ。そこに並べられている本も、かなり貴重な物ばかりなんだぜ」
「…どうしてそんなこと知ってるの?」
「最初は偶然アーチの屋根に気が付いてね。興味を持って眺めてみるとコンクリの柱で旨く誤魔化してはいるが、明らかにもう一つ部屋が有るように見える。5階はエレベーターも止まらないようになってるし、立ち入り禁止って書いてあると入りたくなるのが人情ってもんだろう?」
それにしたって誰にでも入れるものじゃない。
「館長口説き落とすのに、結構労力使ったんだぜ」
そのためにわざわざ読書部なる地味な部活に籍を置いたという事実を優也が知るのは、もう少し後のことだった。
「でも、特別な人って誰?」
郁に促されるままその辺の席に腰を落ち着けると、弁当箱を開けながら優也は尋ねる。
「学園のOB関係とか…時々教師連中も来るみたいだけど、知らない先生も多いんじゃないかな。ついでに言うと生徒で入ったことが有るのは俺と…優也が2番目」
手を止めて優也は郁を見つめた。
話の内容に驚いてしまい初めて名前で呼ばれたことも聞き流してしまう。
「臣も連れて来たことは無い」
「本当に…?」
ゆったりと郁は頷いて、
「想像以上に喜んで貰えて連れてきた甲斐が有ったってものだ」
好きな人と一緒に来たかったから
続く言葉を呑み込んだ。
そんな想いを知るはずもなく満面の笑顔で郁を見つめた優也に、郁は心の中で自嘲の笑みを浮かべてしまう。
“会えば今より辛くなるかもしれないね”
そう翠が以前言った言葉は、まさしく今の郁の心境を予言していたから。
純真無垢な天使のままでと願いながら、郁が優也に求めているものはそれとは正反対の想いだ。
妄想しようが夢に見ようが心の中だけの罪は誰にも咎められないと言い聞かせてきた郁だが、こうして見つめ返されると想いは心の内だけでは留めきれそうにない。
全て奪ってしまいたい、と…
抑え切れない欲望と壊したくない理性とが心の中で交錯する。
この相反する想いはどう処理すれば良いのだろう…
|
|
「優也って器用だね」
テーブルの上で優也が次々に仕上げにかかってる料理を翠は綺麗にレイアウトしながらちょっとつまみ食い。
「パーティ料理なんて初めてだから味に保障はしないよ」
「大丈夫」
にっこり笑って翠はVサインを送った。
「なら安心」
優也も微笑み返し、忙しそうにまたキッチンへと向き直る。
黙々と二人で準備に専念していると、
ピンポーン
呼び鈴が鳴る。
近くの布巾で翠は手を拭いてインターホンに走った。
「はい」
『亜美でーす、こんにちは』
「はいはい」
オートロック解除のボタンを押す。
「開いた?」
『OK』
返事に受話器を置くと元の位置に戻った翠に、
「それにしても、なんで調理係につぐちゃんが入ってないの?」
背中を向けたまま尋ねる優也。
「全然、まったく、すっかり、さっぱりできないってさ」
「…将来困るよ」
「お金が有るみたいだから大丈夫なんじゃない?」
「そういう問題かなぁ」
「でも、白河に台所は似合わないじゃん」
「僕だって似合ってないよ」
「ご謙遜を」
「どういう意味?」
包丁を持って振り返った優也に、
「深い意味はありません」
翠が小さくホールドアップしてみると、うんうんと頷いて優也はまたキッチンで格闘体勢。
その後ろ姿を眺めながら、
本当に似合ってるんだけどなぁ…
小さく翠は心の中で呟いた。
ピンポーン、ピンポーン
再度鳴った呼び鈴に、今度はインターホンを取らずに翠は玄関に向かう。
「いらっしゃい」
扉を開けると薄紫のパンツスーツでケーキを買ってくるだけ担当の亜美が顔を覗かせ、
「お邪魔しまーす」
微笑んで玄関をくぐるなり、
「ん〜っ、いい匂い♪」
「優也が腕に寄りをかけてるからね」
「まあっ、ご亭主の誕生日に愛妻の手料理ってとこかしら」
亜美はわざと科を作ってみせた。
「まだそこまで行ってないって」
「見てると苛々するのよね」
優也は感情がそのまま態度に出る。
優也の郁への気持ちは傍目にははっきりと分っていた。
郁の1年越しの想い人が優也だったということも既に内輪には公表していた、というよりはバレたといった方が正しいが…まぁつまり、両想いなのは明白であるにもかかわらず二人が未だ付き合っていないのは、
「優也がまだ気付いてないから…」
「橘君の気持ちに?」
「自分の気持ちに」
呆れ顔の亜美。
「それじゃあ、天下の橘君も手が出せないわよね」
「僕も努力してるんだけど、手が貸せる範囲があるからさ」
「はっきり言ってあげなきゃ永遠に気が付かないわよ」
「それは橘の仕事」
「翠くん」
リビングからの柔らかい呼び掛けに揃って振り返る。
「電話鳴ってるよ」
「美都かな。白河、仕上げだけでも手伝ってよ」
言って翠は廊下から立ち去った。
「こんにちは」
亜美は笑顔を向けている優也にまず挨拶。
「優也君、そういう物持ってウロウロするの止めようね」
優也の右手で出刃包丁がキラリと光った。
今日は郁の誕生日。
高校生にもなってお誕生会もないだろうが発案者が和臣とくれば目的は一つしかない。
アルコールでも入れて箍を外せば何か進展が有るかもしれないということだ。
メンバーが揃い宴も酣。
それぞれにアルコールがかなり入り少し場の雰囲気が乱れかけてきた頃、
「かおるく〜ん」
紅い顔で少し眠そうに瞳を潤ませながら郁の側にズズっと這って来た優也。
いつになく艶がかった声で呼び掛けれられた郁が苦笑いを向けると、優也はにこっと笑ってみせ擦り寄るように郁の横に腰を落とす。
それまで郁と話し込んでいた亜美は、軽いウインクを残し席を外した。
「お前、飲み過ぎじゃないか?」
視線を優也に戻した郁の言葉。
訊くまでもなく優也が素面でこんなことをするわけがないのだが世間一般的に酔っ払いにはその自覚がない。
「そぉんなことないよぉ。ちゃあんとしてるもん…」
言ってさも眠たそうに額を胸に押し付けてくる優也の肩を困惑気味に郁が抱く。
普段押え込んでる欲望を刺激して欲しくはないんだが…
そうは思いながらも優也の髪に頬を寄せると、
「あれ?」
自分の両手を眺めながら優也は首を傾げた。
そして少しの間そうしていたが急に慌てたように郁の胸から身体を起こし辺りを見回した。
「何か捜してるのか?」
郁の呼び掛けは耳に入っていない様子で、あからさまに物を捜してます体勢の優也がある一点を向いて止まる。
「あったー」
嬉しそうに郁を通り越した向こうの何かを指差して、その方向に這い出した。が、テーブルと郁との間は狭い。
郁の足に躓いてバランスを崩した身体を慌てて郁が抱き寄せた。
「怪我するぞ」
「へーき」
「平気じゃない」
「でもぉ」
「でももない」
「だって」
「大人しくしてるんだっ」
「…はぁい」
一瞬大人しくなった優也だが目的があったことを思い出し、ぱっと顔を上げた。
「何が欲しいんだ?」
優也の視線の先を追いながら郁が尋ねると優也は子供のように目的物を指差してみせる。
その人差し指の延長線上に有るのは電話台の棚に置かれているワインのコルク。
郁は一度優也から身体を離し少し腕を伸ばしてそれを手に取ると再度優也の肩を抱いた。視線の隅で和臣と美都の冷やかし笑いが目に入ったが当然無視。
「これか?」
言いながら差し出したコルクを何故かそのまま優也は押し返す。
「…?」
意図が分らずに首を捻った郁へニッコリと優也は天使の笑みを向け、
「それ、かおるくん持っててくれないかな」
すっかり酔っ払ってると思っていたのだが優也は意外にしっかりと話し出した。
「今日僕が持ってきたワインのコルクなんだけど…」
どのワインだったっけ?
と郁はその辺に転がっている空の瓶に視線を漂わす。
「僕さプレゼント何がいいか考えたんだけど、かおるくんの好みわかんないし、お金もあんまりなくって…。でね、実はあのワイン、父さん達が海外旅行に行った時のお土産なんだ」
言葉に郁は唖然とする。
「…それって形見じゃないか」
「うん、でも家にあったって誰も飲まないから」
「どうしてもっと早くに言わないんだ」
もう既に味も何も覚えてはいない。
けれど、
「いいんだ」
「良く無いだろう」
「みんなに飲んでもらってきっと父さん達も喜んでるよ。だけど…僕には大切な思い出だから、かおるくん持ってて」
両親が死んだ時、助けてもらったから…
「優也が持っておくべき物だろう?」
優也は俯き加減に首を振る。
「迷惑かもしれないけど…かおるくんに貰って欲しい」
照れたように指で額を掻いてみせて確認するような瞳を郁に向ける。
それをしばらく見つめた郁は、
「ありがとう…」
言葉と共にその恵まれた容姿で極上の笑みを優也に返した。
少し前から二人の様子を観察していたギャラリーも、その笑顔に思わず見惚れてしまう。
美都が翠に対してそうであるように、この微笑みも優也でしか引き出せはしない…。
「…寝たの?」
最後の気力を振り絞っていたのか郁の返事を聞いた途端ほっとした表情でそのまま優也は瞼を閉じてしまった。
「ああ、大分飲んでたみたいだからな」
亜美の問いに静かにグラスをテーブルに置きながら郁は答える。
「平和そうな寝顔しやがって…」
「安心してるんだろ」
「それだけ心許してるってことよ」
「…そろそろ言ってもいい頃じゃないか?」
郁は自分の膝の上で寝息を立てている優也に視線を落とした。
「もう少し待ちたい」
自分の気持ちを押し付けることで優也を混乱させたくないのだ。
「聖人君子になれそうだな」
「森丘だって直ぐにお手付きしたわけじゃないだろうが」
「まぁね」
「あっ、また有ること無いことぺらぺらと」
「俺は有ることしか喋ってないって」
「どうしてそう何でもかんでも喋るんだよっ」
翠が睨んでみても美都はシレッとしたものだ。
「まぁまぁ、人助けなんだから」
はははと笑いながら和臣が軽く宥める。
翠は大いに不満顔では有るが何を言い出されるか分ったものじゃないから取り敢えず反論は諦めた。
この様子では和臣も色々知ってそうだ。
「さっき何、貰ったの?」
「ご両親の形見」
「そこまでしといて、どうして気が付かないかなぁ」
「潜在的には気付いてると思うよ」
「後は多分」
きっかけが有れば…
|
|
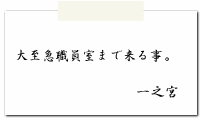
昼休みが終わる頃、翠と優也が近頃日課となっている屋外食から帰って来ると、翠の机の上に1枚のメモ用紙。風で飛ばないようにか、ご丁寧にセロハンテープで机に貼ってある。
翠は教室の時計に視線を向けた。
5時間目始業のチャイムまで後5分…
「どうかした?」
席に座って振り返った優也はまだ突っ立ったままの翠を見上げた。
「うん、一之宮の呼び出しなんだけど…」
「後にしたら?」
そうは思うが生活指導の呼び出しではかなり気になる。
何か悪いことしただろうか…?
と首を捻り、
「気になるからちょっと行ってくるよ。もし遅れたら、言っといてくれる?」
優也は快く頷いて小さく手を振ってみせた。
翠は直ぐに教室を飛び出し南階段を駆け降りる。
思い当たるとすれば美都とのことぐらいだが、バレたのなら和臣が先に言ってくれそうなものなのだ。
大体急用なら放送で呼び出せってんだ…
軽く舌打ちしながら第3校舎に向かい職員室に着くと、ノックをするまでもなく授業に向かう教師達がぞろぞろと出て来た。担任の教師が翠に気付いて、
「こらっ、いつまでもウロウロしてるんじゃない」
教室に戻るよう促されたが呼び出された旨を伝えると少し妙な顔をした。
「何の用だろう…」
生活指導で呼ばれるのなら担任がその内容を知らないのはおかしな話だ。
「でも、職員室にはいないから準備室に行ってみるといい。確か一之宮先生は5時間目、空きだったはずだから」
翠は眉間に皺を寄せる。
一之宮担当の社会準備室は第1校舎4階東の端。
つまり、ここから遠い。
どうしようか…
一瞬迷った翠だが、
「そうそう、5時間目は自習になってたから急ぎなら行ってくればいい」
担任の許可をもらって準備室に向かった。
勇み足で第1校舎に入るとチャイムが鳴る。階段を一気に4階まで駆け上がり少し息を乱しながら扉をノックした。
「…はい、どうぞ」
返ってきたのは目的の人物の声。扉を開けると彼は少し驚いた顔を見せた。
部屋の中には一之宮しかいない。
「なんだ、授業始ってるぞ」
「え?」
「えって、何か急ぎの用か?」
予想外の言葉に翠も驚いてしまった。
呼び出しておいてそれはないだろう。
「だって先生が…」
彼の側まで駆け寄りポケットからメモを取り出して見せると、
「…似せてはあるが私の字じゃない。第一そんなに急ぎなら全館放送するに決まってるだろう」
それは翠も考えたこと。
「誰かにからかわれたか?」
一之宮は軽く笑いながら机の端によけてあったプリントの束を取って翠の前に差し出した。
「6時間目の資料だ、ついでに持って行っておいてくれ」
翠が納得できない表情のままそれを受け取ると、
「とにかくそれは間違いだから早く教室に戻りなさいっ」
生活指導の鋭い目で睨まれて仕方なく返事をすると部屋を出た。
何か妙だ
こんなすぐバレるような嘘をついて誰が何の得をするというのだ。
特別教室の並ぶ4階を首を捻りながら通り過ぎるとL字に曲がる手前で階段を降りる。
やっぱりただの悪戯かなぁ
どうしても思い当たる節が無く、しかめっ面で教室に入って…
「ねぇ、優也は?」
1番側にいたクラスメートに声を掛けた。
5時間目は担任の言った通り自習になっており、各自それぞれの友人と固まって課題を進めていたが、一通り見回しても優也の姿が見えない。
「そういや、授業の前に出て行ったような…」
不安が過ぎる。
「一人で?」
言いながら教室内をもう一度、注意深く見渡した。
「いや、確か」
由岐が…
いない。
持っていた資料を危うく落としそうになり慌ててそれを教卓に置いて戻ると、
「どこ行ったかは…」
首を振るクラスメート。
「ごめん、どっちに行ったか憶えてない?」
彼には翠の懸念が分かるはずも無く、のんびりと背もたれに凭れて北側を指差した。
翠が今来た方向だ。
「有り難う」
嫌な予感…
でも、まだ確信が無い。
トイレってことは?
授業が始って5分強。教室に戻る途中も前を通ったが見落としただけかもしれない。
トイレを覗くがシンと静まり返っている、上下の階も同じだ。
ついでに1階に並ぶ特別教室も覗いてみたが使用中か生徒が入れるような部屋は無かった。
由岐は何委員だったっけ…
清掃委員だ。授業中に行く所はない。
保健室?
優也はすこぶる元気そうだったし保健委員も教室にいた。
教室で待ってれば直ぐに帰って来るってことも…
“少しでも気になることが有ったら直ぐに知らせに来い”
和臣の言葉。
“由岐は要チェックだぞ”
やっぱり待てない
念のため一度教室に戻り二人共いないことを再確認して3階へと向かった。
階段を勢いよく駆け上がり踊り場から1組の前に飛び出した翠はその廊下に響く足音で、クラス全員の視線を浴びてしまう。
気候がいいせいで扉が全部開け放たれているのだ。
「おい、授業中に何をしてるんだっ!」
当然教師も気が付くはずで翠にいきなり怒鳴り出す。
それでも怯まずに教室内に目をやると、郁が既に後ろ扉に向かっていた。
申し訳無いとは思いつつ翠は教師を無視して、
「ごめん…」
険しい表情で戸口に立った郁に、謝るしかない。
「ごめんって」
「優也がいない」
郁の表情が固まった。
「由岐と一緒にいなくなった」
言葉の途中で既に翠の腕を掴んでいた郁は、そのまま教室を後にした。
「心当たりは?」
「分らない、近くは全部探したけど…」
「いつから居ない?」
「5時間目が始るころ」
「授業は?」
「急に自習になったんだ」
「佐伯は何してた」
「変な手紙で呼び出されてて、教室に居なくって…」
「マズイな」
直ぐに追いかけてきた和臣の言葉に振り返ると、いつもの笑みが消えている。
「用意周到だ」
美都の声に郁は掴んでいた腕を放した。
いきなり3人の生徒が抜け出したにもかかわらず誰も追いかけて来ないことに、既に2階まで降りていた階段を翠が見上げると、
「白河が上手くやってくれる」
和臣は振り返りもせずに素早く答えた。
「佐伯が探した所は?」
「第2校舎は多分居ないと思う。それから第1の4階も外せそう」
「第3校舎はこの時間連れ込める所はないから…」
1階の踊り場に辿り着いたところで視線をグラウンドに向けた和臣は、
「待ってろっ」
言い置くと和臣はそこからバックネット裏まで走り誰かに手招きをしている。
体操服の生徒が一人和臣に歩み寄り、二言三言話した素振りを見せると和臣は3人に向かって大きく南側を差した。
グラウンドから南側に在るのは公道を隔てた学園のもう一つの敷地。
体育館とプール、それに第2グラウンドを挟んで、
「木造校舎」
3人は一斉に床を蹴った。
それより時間をさかのぼること10数分。
「ねえ、僕なんかじゃどうしようもないって」
優也は早足で歩く由岐の後ろで立ち止まる。
「やっぱり郁くん呼びに行ってくるよ」
そう言って来た道を戻ろうとした優也の腕を由岐は強引に引いた。
「だからさっきから言ってるだろ? 俺が思うほど大した怪我じゃないかもしれない、わざわざこんなことで橘呼び出してたら後で何言われるか」
「郁くんそんなことしないよ」
「優也は仲がいいからそう思うだけさ、アイツ等に睨まれたら学校に居られないからな。それにもう授業始ってるんだぜ」
「でも…」
いくら自習といえども授業中に教室を抜け出したことは気になる。由岐に強制的に連れ出されて行先を誰にも告げられなかった。
きっと翠も心配してるだろう。
「優也が見てヤバイと思ったら橘のところに走ればいいじゃないか」
優也は怪我をしている子犬がいると言って教室を連れ出されたのだ。
「…こんな所に居るの?」
由岐は木造校舎に足を踏み入れ迷わず2階へと続く階段に足を掛けた。
木の軋む音が静かな廊下に響き渡る。
木造校舎は戦前からの建築物で遺跡のつもりで置いてあるのか、今では少数の部活と文化祭などで場所が足りない時に使われる程度だ。 もちろん授業中に人が居るはずもなく入って来るような人間もいない。
優也は初めて入る木造校舎を物珍しそうに見回した。
外に生い茂る木々のせいで真昼だと言うのに廊下には殆ど光が射し込んでこない。重くひんやりとした空気がタイムスリップしたかような感覚を思わせる。
「何だか気味が悪いね」
その辺りの窓からこの世の物でないものが覗いているようで、窓に視線を向けられないまま俯いて付いて歩く優也。
前を歩く由岐が2階の或る部屋の前で足を止めた。
「ここだ」
由岐が木の扉を開けたが枠にカーテン状の赤い布が付けてあり、見えるのは床から5センチばかり。
「ねえ」
振り返ろうとしたその時、優也は思い切り背中を突き飛ばされた。
小さな悲鳴と共にそのまま布に絡まるよう倒れ込んだ身体を誰かが強い力で受け止める。
後ろで扉が閉じられる音。
「ちょっと…!」
布が覆い被さって状況が掴めない。
見えないことが混乱と恐怖を呼び起こし優也が自分を抱き込んでいる誰かの身体を渾身の力で突き飛ばす。と、腕からは逃れられたがその勢いで数歩後ろによろめいて、
「由岐?」
今度は後ろから羽交い締めにした人物への問い掛け。
知らず声が震える。
…その問いにはどこからも言葉が返ってこない。
訳が分らないまま床に引きずり倒され、大声で叫ぼうとして布の隙間から入り込む埃にむせ返った。
直ぐに覆い被さった布を取られる…が、眩しさで目を細めると、目の前の光景を何一つ確認できないまま細い布をがっちりと瞼の上に巻きつけられてしまう。
「誰? …どうして」
一体何をされようとしているのか…
優也が抵抗できたのはほんの束の間。
四肢を押さえつけられ誰かが身体に跨がったのがわかった。唯一動く頭を起こそうとしたがそのまま圧し掛かられ、熱気をおびた香水の匂いで優也はまたむせ返りそうになる。
自分の意志で動かせるのはもう指先だけ…
左の袖を捲り上げられ二の腕を何か強い力で締め付けられて、
「嫌だ…」
恐怖で声が掠れた。
これは以前に体験したことが有る。
この後に続く行為は…
と予感した通り腕にひんやりとした感触が襲い鋭い痛みが肌を突く。
「や…っ、…誰か」
何かが体の中に流れ込んでくるような、味わったことのない感覚に、
「…こわい」
それとは別な外因的感触が頬を這い耳元で止まった。
「恐がらなくていいんだよ」
「…だ…、れ?」
視界が塞がれているのに…一面が真っ白になって、
「SERAPHIM。…君を天国に連れて行ってあげる」
渦に…呑まれる…
…………
「いい子だ」
スーツの男が真上から薄笑みを浮かべた。
「…大丈夫なんですか?」
急に抵抗力を無くした膝から手を放し、たった今腕から抜かれた針を眺めながら眼鏡の少年は言う。
「吐かなかったわね」
赤茶の長い髪を掻き上げシリンジをケースに戻し終え、一歩踏み出すと細身のシルエットが優也の顔を覆った。
傍に屈み込みながら伸ばされた細い指が、薄らと開かれた形のいい唇を辿る。
スーツの男がすっと目を細めた。
「まっさらな天使に傷を付けるつもりか?」
視線に気付き一度優也の唇からその指を離すと、凝った美細工の指輪を抜き取り少し離れた場所に置く。
それを確認し視線を戻すと優也の口元が呟くよう微かに動いた。
「早く欲しいようだね」
スーツの男の声にマニュキアの赤が再び優也の唇に妖しく色をのせ、長い爪の先から更に奥へと急ぐ。軽くかみ合わされる歯を押し開くと誘っているかのように喉が鳴り、侵入した2本の指に弄ばれる舌が濡れた音を洩らす。
「…ぅ……、んっ…」
男達の含み笑い。
「最高だ…」
それは誰の呟きだったのか。
右腕を抑えていた浅黒い肌の少年が瞳に巻かれている布に手を伸ばすと、
「今日は止めておけ」
スーツの男がたしなめるように睨んてみせた。
「何も憶えちゃいませんよ」
「万が一ということが有る」
諦めたのか伸ばした指をうなじに付けると、スーツの男が優也のネクタイに手をかけ難なく引き抜いた。
それを慣れた手つきでポケットへと仕舞い込みシャツのボタンを外し終え、まるで味わうかのようにその薄い胸に這わされた指、
「…なんて綺麗なんだ」
恍惚と胸元に唇を押し付け舌で舐めあげる。
足を撫ぜ摩っていた別の手が待ちきれないといったふうに優也のズボンのベルトにかかり、少しいらつきながらバックルに手をかけ、ようやく外し終えたところで部屋中の空気が一変した。
廊下に響く複数の足音。
小さな舌打ちと共に室内に居た男達は一斉に立ち上がり無言でその場を後にした。
それから2、3分といったところか…
教室を一つひとつそれぞれが手分けして捜していたが最初に飛び込んだのは翠だ。
埃だらけの床の隅に倒れている人影を見止め叫んだ大声で美都と郁が即走って来た。
「優也っ!」
駆け寄って郁が抱き起こす。
その間に部屋の暗がりに別の扉を見つけた美都は、そこから飛び出して行った。
「何てこと…」
ぐったりとした様子の優也に翠は言葉を詰まらせ側に腰を落とす。
「優也」
心痛な面持ちの郁が乱れているシャツの前を合わせ、その瞳に巻かれている赤い帯を外すと優也の口から小さくうめき声が洩れた。
眩しくて光を遮ろうとしたのか腕を持ち上げようとして見せたがその動きは緩慢に途切れてしまい、
「…様子が」
おかしいと思ったのは二人同時だった。
半分閉じられた瞼の奥でその瞳は輝きを無くし虚ろに空をさ迷う。
口元もボンヤリと開かれ、時折快感とも不快感ともいえないような音を発している。
「優也、俺が分るか?」
郁が瞳を覗き込んでも焦点が合わない。
一体何をしたんだ
苦しげな表情で強く優也を抱き込み、ふと逸らした郁の視線が優也の左袖口で止まる。
まさかとは思いながらも、
「佐伯、左腕」
言葉に翠もすぐに顔色を変えるとそっと袖を上げて…
「…嘘」
翠の愕然とした声。
郁はぐっと瞼を閉じた。
「…ぶっ、殺してやる」
沸き上がる怒りのせいで握り締めた拳が震える。
とそこへ、
「逃げられた」
「見つけたぞ」
声に二人が同時に顔を上げ、和臣の横に由岐を見つけた翠は無表情で静かに立ち上がった。
母親を死に追いやった同じ手段に我慢できるはずが無い。
「優也はどうだ?」
和臣の声など耳に入るわけもなく、翠は真っ直ぐに由岐に歩み寄ると振り上げた拳を思いっきり顔面に打ち付けた。
翠より体格の大きい由岐が腰を抜かしたように尻餅をつき、頬を押さえることも忘れ驚愕としてしまっている。
更に掴みかろうとした翠を、
「おっ、おい佐伯っ」
和臣が即座に制した。
「待てってば」
「嫌だ、離せよっ!」
涙を流しながら制止も振り切らんばかりで暴れる翠を慌てて美都が抱き締めると、
「翠、落ち着け。な…」
そのまま壁に押し付けて抱き込んだ。
「どうしたんだ」
怒る気持ちは分らなくはないが…
由岐を助け起こす気などさらさら無い和臣は美都を見る。
だがその美都にも困惑の視線を向けられ、見え難い位置にいる郁の方を覗いた。
時間的にほぼ大事には至らなかったと踏んでいた和臣は、優也を抱えたままの郁を見て、
「…郁」
目を細めながらゆっくりと歩み寄る。
けれど郁は顔を上げない。
服装がそれほど乱れていないことはここからでも見ては取れるのだが、
「間に…合わなかったのか?」
一応の問い掛けに首を振った郁は、床に膝を突いた和臣へと重く頭を上げ、
「腕に鬱血の跡がある」
和臣が顔色を変えた。
「意識は?」
「分からない。光に反応したみたいだから有るというんだろうか…、まるで泥酔してるみたいだ」
「判断し兼ねるな。早い内にプロに見せるのが無難だぞ」
「養護教諭ってことか?」
「手っ取り早いのはね」
「騒ぎを大きくしたくない」
「言ってる場合じゃないだろう?」
和臣の言葉に郁は胸ポケットから小さな物を取り出した。
「さっきそこの隅で拾った」
掌には美細工の指輪。
「生徒が学校にしてきたと思えるか?」
「なんてこった…」
和臣は信じられないといったふう、眉をしかめる。
「医者に行っても、どの道学校に連絡が入るだろうし」
「僕の家に連れて行こう」
二人が見上げると、そこには泣き顔の翠。
「医者の知り合いがいるから」
「信用できそうか?」
「俺の保証付きだ」
美都の言葉に和臣は頷いてみせるとポケットから携帯電話を取り出し車の手配をさせた。
「直ぐ迎えが来る」
言って翠に電話を渡して立ち上がる。
由岐がいなくなっていることには気が付いたが、ほっておいても構わないだろう。
どの道逃げ切るには退学という道しかないのだから…。
「どんな具合?」
亜美の声でリビングに顔を出した郁へと全員が視線を向ける。と、
「ずっと寝たままだ」
答えた郁は直ぐに寝室に戻るつもりなのか、輪の中に入る様子もなく戸口の壁に凭れた。
リビングではテーブルを囲んでいつものメンツが揃っているが誰もみな浮かない顔をしている。
“もう大丈夫だと思うけど、何かあったら直ぐに呼ぶように”
夜もう一度来るからね。
そう言い残すと伸弘が部屋から出て行ったのが2時半頃だったか…。
翠の友人の医師・滝沢伸弘が仕事中にもかかわらず無理をして出向いてくれたのだった。伸弘が帰る頃には既に優也は睡眠状態に入っていて、それは今でも継続している。
「どうだった?」
さっき着いたばかりの和臣に尋ねたのは郁。
あれからずっと走り回っていたのだろう、さすがに疲労の色を隠せないまま小さく息をついた和臣は、
「あの部屋に残ってたのは優也が目隠しされていた紅い布と紅いカーテン。それに郁が拾ったルビーの指輪」
「赤づくしね」
亜美の言葉に和臣は頷いて、
「何か意味が有るのか、それともただの偶然かもしれない。床の足跡の感じからして単独ではなさそうだ。で、一応あの時間所在不明の教師や生徒を当たってみたんだが、生徒は休んでいる奴含めると2年だけで8人。明日になれば全学年分判るとは思うが、今のところはっきしりないのが2人ってところだ。後、困ったことに教師はもっと掴み難くて、授業がない時間はどこで何してるやらそれぞれお構い無しだ」
「…岡本は?」
7組に授業に来るはずだった教師の名前。
「子供が通う幼稚園から昼休みに連絡が入って慌てて帰ったらしい。理由は…これも明日だな」
「由岐はどうした」
「あのままトンズラ。だけど捕まえた時の感じからして、あまり訊き出せそうじゃない。俺が見るにただの使いっ走りだろう。本当は優也に訊くのが一番なんだが」
時計の短針がもうすぐ8の数字を指そうとしている。
「思い出させるのは気がひける」
誰とも無しに溜め息が漏れた。
優也はあれからまだ一度も意識を戻してはいない。
するとその時いきなり玄関扉が開く物音が響き、それぞれが視線を廊下へと向けると、
「今晩は」
顔を出したのは伸弘とその恋人の長谷川圭吾。圭吾も伸弘と同じく医師である。
伸弘はリビングに入ったが圭吾は挨拶だけで寝室に向かった。
「…本当は警察に行くべきなんだよ」
リビングに入った伸弘の全員に確認するかのような言葉。
この提案は昼間にも一度言っている。
伸弘も圭吾も職業柄麻薬の怖さは良く知ってはいるのだが、それを考慮しても公にしろと強く言えないのは事件の特異性を理解しているから。
幾らその対象が男の子だとはいえ、これはれっきとした強姦未遂事件だ。伸弘の看た限り薬を打たれた以外は僅かな打撲と擦過傷が有る程度。気を失っていたことを考慮したとしても殆ど手を付けないまま犯人は逃走したと思われる。がしかし噂というものは尾鰭が付いて流れるもなのだ、未遂は必ず既遂となって語られる。
何も無かったにもかかわらず優也が精神的に犯されてしまうことは明らかであろう。
その上現場が学校という一種の治外法権の場である以上、いくら警察が介入してきたところで、どこまで学校側が協力するかも疑わしい。特に今回の場合犯人に生徒以外の人間が関わっている可能性が大きいのだ。考えたくは無いが教師の内の誰か…もちろんそれは学園長をも含む誰かが関与しているという可能性を無視するわけにはいかない。
「だけどこれだけは約束しておいて欲しい。事件を伏せたい気持ちは分かるけど、他に協力者を要請すること。対象が彼にしろ他の誰かにしろ、また繰り返される恐れが有るから。ここにいる全員がいつ同じ目に遇わないとは限らないからね。犯人の年齢層に幅がある以上、できるだけ教師の中から協力者を探したほうがいいよ」
「でも先生の中に犯人が居るかもしれないのに…」
「翠君達の通っている学校はね、以前生徒に麻薬中毒患者を出したことが有るんだよ」
言葉に驚いて一様に伸弘を見た。
「2年程前になるからはっきりと内容までは憶えてないんだけど、原因探求にかなり奔走した教師がいたらしいから調べてみたらどうだろう。多分何か協力してもらえると思うよ」
壁に背を付け話に聴き入っていると、
「かおるくん…かな?」
寝室から顔を出した圭吾に郁はそっと名前を呼び掛けられた。
振り向いた郁へゆったりとした笑顔を向けながら、
「呼んでるよ」
圭吾の言葉。
「点滴。もう少しで切れるから、後頼んでいいかな?」
頷いた郁を確認すると圭吾はポンと郁の頭を撫ぜてみせ、
「大丈夫だよ」
言葉にほんの少し頬を緩めると、入れ替わりで寝室へと入り扉を閉める。
薄暗い室内。
窓側に掛けられている透明な袋から管が延び、ゆっくりとしたペースで液体が滴下されている。
その管の下、ベッドに横たわる優也の瞳が僅かな光を反射しているのが分かった。
静かに歩み寄る郁の歩調に合わせて、その光も角度を変え、
「優也」
呟きに薄い口元が小さく弛んだ。
「…助けて、くれたんだね」
少し掠れた声に郁は頭を振る。
「すまない」
守ってやれたとはいえない。
そんな郁を真っ直ぐに優也は見上げながら、
「また郁くんに逢えたから、それでいい」
穏やかな声。
伸ばされる腕に応えるよう郁がペッドに屈み込んで見せると、
「でも」
郁の背中に腕を回した優也は、
「少しだけ。もう駄目かと、思ったから…」
僅かに震える声。
「泣いても、いい?」
…閉じた瞼から涙が零れ落ちた。
「優也」
「うん?」
「ごめんな」
「うん…」
「…優也」
「……ん」
「…まさや」
「……」
…まさや
………
郁の哀しい囁きに月も黙に涙を落とす
闇の中で光る雫が
夜の帳の隙間をつたって
淡くしっとりと心の中に流れ込んでゆく
優しい流れは優しいゆりかご
穏やかな眠りへそっと誘う
郁の腕に包まれて、溶けていく意識の中
やっと優也はその想いを…
…見つけた
人は見た目によらないとはいうが…
優也はその誰もが抱擁心を掻き立てられる容姿と仕草とは裏腹に、どうやら強靭な精神を兼ね備えているようで周りの想像よりはるかに早い立ち直りを見せた。
襲われたといっても行為の初期段階で阻止されたことと、薬のせいか前後の記憶が未だハッキリしないということも立ち直りを早くした理由のひとつであろう。
それでもふと気が付くと物思いに耽ってしまうことが有るのは、どうやらその原因は月の雫にあったような…
「わざわざ呼び出して悪かったね」
生徒会室に優也が呼び出されたのは事件から1週間ほど経った頃。
伸弘の助言も有って和臣は信頼のおける一部の教師と生徒会執行部役員だけの範囲で事件の経緯を報告していた。
大事には至らなかったが校内の事件でもあり今後のことも有る。
生徒会として優也に事情を聴きたいというのはおかしな話ではない。
「思い出したくはないだろうけど形式上聴いておかないわけにもいかないから…。了承してもらえるね?」
優也は初めて話す東條生徒会長に緊張の面持ちで頷いた。
生徒会室は普通の教室の半分くらいの広さがある。
一番窓側に戸口が見える向きで左から会長・副会長・書記の席が横一列に並んでいる。副会長席と書記席の前には通路を隔てて垂直に事務用の長い机が向かい合わせで2本あり、会長席の前には簡単な応接セットが構えられている。
「くれぐれも言っておくが、外野は静かにするように」
廊下側に面した壁に立ち並ぶ4人に向かって書記の津島が声を掛けた。
呼び出されたのは優也だけなのだが心配で仕方がないのか郁をはじめ、いつものメンバーが壁に沿って並んで立っている。
入室の許可が下りたのはいうまでもなく和臣の口添えが有ったからだった。
後方に立つ4人を一瞥した東條は視線を優也へと向けた。優也は東條の正面、会長席と応接セットの間にある、やや広めの空間で事務用の椅子に座っている。
硬い表情を和ませるべく、
「思い出せないことは無理に言う必要はないから安心していいよ」
優しく笑ってみせたが東條のこの言葉は嘘。
彼とその隣で黙って様子をうかがっている副会長の瀬田には本当の目的が有るのだ。
そのために優也の健康状態が回復するのを待って呼び出しをかけたことは優也の右斜め後ろ、少し離れた席に座る和臣でさえ知らない。
「松前君に一通り聞いてはいるがもう一度詳しく事情を話して貰いたい。こちらからの質問形式でいいね?」
「…はい」
緊張しながら優也は答えた。
「じゃあまず…、あの日の昼休み教室を出たのはいつ頃だった?」
「最初はお昼休みが始って直ぐです」
「後ろのメンバーと一緒だったんだね」
優也は頷く。
「教室に戻ったのは?」
「5時間目が始る少し前に一度戻りました」
「二度目に出たのはその後直ぐ?」
はいと優也はまた頷く。
「授業が有るのに、また教室を出た理由は何?」
「由岐…くんが用が有るって」
東條は少し笑って見せると、
「普段呼んでいる通りでいいよ。で、その用件は授業を抜けてまで行く必要があったのかな?」
優也が少し首を捻る。と、
「言い直そうか、どんな用件が有るって言った?」
「怪我してる子犬がいるから看て欲しいって言われて」
「小西君はそういうことに詳しいんだ」
「…詳しくないです」
「じゃあ由岐君とはそれ程に親しかった?」
首を横へと振る優也。
「じゃあどうして付いて行ったりしたのかな」
言葉に詰まった。
東條から視線を逸らした優也に、
「ギャラリーのことは気にしなくていい、それを承知で来てるんだからね」
優也の心を見透かしたような東條の言葉。
斜め後ろの席に視線を向けると和臣が頷いてみせた。
「あの…郁くんがそういうことに詳しいの知ってたから。僕は郁くんと仲良くしてるから、まず僕の目で判断してから郁くんに相談してみるって言われました」
郁の父親は獣医師であり、自宅近くで動物病院を開業している。
「郁君って言うのは、そこにいる橘郁君だね」
「はい。…でも、途中でやっぱり引き返そうと思ったんですけど」
「授業が始っていて呼びにも戻れない、だけど子犬も心配」
優也は東條を見る。
何故か郁を思わす視線を向けられ、
「そうだね?」
言葉に頷いたまま俯いてしまった。
(…おい、由岐。お前の名前使ったのかよ)
(とことん信じられないね)
(それなりに痛い思いはさせといた)
(よく“それなり”で済ませたな)
(ただのパシリじゃ話にならない、それに佐伯の一発も効いたようだし)
(俺もあれには驚いた)
(私も見たかったなぁ、佐伯君の勇姿)
(勘弁してよ…。それで怪我してちゃ意味ないよ)
(ははっ、それは言えてる)
「オホン、オホンっ」
これ見よがしな咳払いに4人が視線を向けると、津島の鋭い視線が突き刺さった。
「なるほど。突き飛ばされた後のことは良く憶えていないんだね」
「はい、その後のことはほとんど何も」
「殆どってことは少しは憶えてるってことかな?」
何となく言ってしまった言葉を突っ込まれて、優也は少し困惑気味に東條を見る。
「例えば人数だとか、声を聞いたとかってことは?」
突き飛ばされて前に一人、後ろに一人。
「二人はいたと思いますけど…」
あまり思い出せないというよりは、思い出したくない心境で優也は目を細めた。
「聞き覚えのある声は聞かなかったか?」
「声…」
優也は首を傾げてしまう。
(形式だけとか言いながら、結構根掘り葉掘り訊いてるじゃないか)
(それも仕事なんでしょう)
(…ところで橘、それ何?)
(これ? ネクタイだ)
(包みに入ってるって事はプレゼント?)
(この間優也ネクタイ無くしただろ、先週声掛けてたら今頃になって持ってきやがった)
(誰かが、スペアくれたんだ?)
(と思う。さっき知らない内に机の上に有ってね、急いでたからそのまま持って来たんだが…)
(…もう優也買っちゃったからね)
(あっ、佐伯君知らないんだ。あれは橘君が出費したのよ)
(えーっ、そうなん…)
「外野は静かにするように」
はっきりと名指しでの津島の鋭い声に、4人は薄笑いでさっと正面に向き直る。
優也はテレ笑いで和臣を見た。
途中から会話が全部聞こえているのだ。
「小西君、ネクタイを無くしたのはあの時かな?」
声で優也は視線を戻す。
「…そうです」
「優しい友達が居て何よりだね」
東條は言うと瀬田に目配せをした。
瀬田もそれだけで分ったのか黙って立ち上がると、和臣の後ろを通って郁の前で立ち止まる。
「橘、それちょっと見せてもらいたいんだけど」
指差したのは先ほど話題になった赤い包み。
「これですか?」
どうしてそんな物をと思いながら郁はそれを瀬田に手渡した。瀬田はその場で袋の中からネクタイを取り出すと観察するように顔に近づけ、表情を若干険しくする。
「貰うけどいいか?」
返すつもりは無いといった口振り。
「どうぞ」
どうせ処分に困っていたのだ。
あんな趣味の悪い…
瀬田は礼も言わずに郁の側を離れた。
(いいのか、誰からか分らないんだろう?)
(構わないさ)
(でも親切でくれたんだから)
(ああいうのを有難迷惑って言うんだよ)
(人の好意を無下にする奴)
(さっき瀬田さんが出した時に気が付かなかったか?)
(何が?)
(香水だよ、それも悪趣味なやつ。人格を疑うぞ)
(それで瀬田さん眉間に皺寄せたのか)
(でも貰っていったわよ)
(好みなのかな)
(ふふっ、人それぞれってことなんじゃない?)
(じゃあ瀬田さんって人格異常者?)
(わははっ、そりゃ傑作)
「いい加減にしないと追い出すぞっ!!!」
ついに津島の怒鳴り声。で、
「すいませんっ」
4人はピシッと直立不動。
「後ろの4人、大人しくさせておいてくれ」
瀬田は席に戻り際、和臣に小さく耳打ちをすると背中を押すように叩いた。
後ろまで下がれということか…
ギャラリーは時々騒がしいが我慢できない程ではない。
何を始めるんだ?
瀬田に目的が有ることは分ったが、指示が出てしまえば従うしかない。 黙って壁際まで下がった和臣は、
「郁、しばらくじっとしてろよ」
念のため一番危なそうな人物に声を掛けておいた。
一方瀬田はそのまま席には戻らず会長席の前からさっきのネクタイを机の上に差し出した。東條は瀬田を見上げ、瀬田が頷いたのを確認すると優也へと向き直る。
「小西君」
言って東條が手招きをすると、不思議そうに立ち上がり3歩で机の前に着いた優也は当然瀬田の横に並ぶはず。だったのだが、優也が机に着くと瀬田は静かに後ろに下がってしまった。
優也のほぼ真後ろあたり。
東條は席から立ち上がると右手を伸ばし優也の顎を軽く上げる。
「…綺麗な瞳をしてるね」
覗き込まれた瞳に優也が驚いて身体を引こうとした時には、既に東條はその指を離していた。
次いで東條が視線を机の上のネクタイに落とす。と、つられて優也もそれを見る。
「このネクタイ、見覚えない?」
制服のネクタイなんて同学年共通なのだ。即座に首を振ろうとしたが、
「手に取って良く見てごらん」
促されて仕方無く手に取った。
折り目のしわが綺麗になっているということはクリーニングにでも出した後のようだが、どっちを向けても普通のネクタイだとしか物語ってくれない。東條の手前持て余し気味に数回ぱたぱたとネクタイを返す内にゆっくりと立ち上る匂いに気が付いて、
「―――…」
頭がそれを認識するより早く、身体が先に反応した。
優也の動きが止まる。
「知っている匂いだね」
見開かれた瞳の肯定。
優也の身体が小刻みに震え出し、足が体重を支えられない。
「なんで…」
その場に崩れ落ちそうになった優也を、後ろに居た瀬田がしっかりと抱き止めた。
「…や、だ」
手にしていたネクタイが滑り落ち、顔を覆いかけたその手の移り香で鮮明に恐怖が蘇る。
「嫌だっ!」
叫んで強く瀬田から逃れようとした優也を、身を乗り出した東條がぐっと引き寄せた。
「思い出したね」
耳元に落ちる声
「…こわいよ」
“恐がらなくていいんだよ”
フラッシュバックに息が止まる。
「SERAPHIM…」
“君を天国に連れて行ってあげる”
「…って言わなかったか?」
力が…
机の上に倒れ込む寸前、瀬田がどうにか抱きかかえると、
「橘っ!」
大きく叫んだ。
その声で力を緩めた和臣の腕を振り払った郁は即座に走り寄る。
「あんたら…!」
飛びつかんばかりの勢いの郁はあっさり瀬田から優也を受け渡されて…両手を塞がれては飛び掛かることが不可能となってしまった。
「よっぽど好きなんだな」
予想外のセリフに不意を付かれた郁が絶句しながらも睨んだ先では、何故か東條が悲しそうな表情を浮かべていた。
「…悪いことをしたね」
郁の腕の中で瞳を上げた優也に気付いた東條の言葉に優也が小さく頷くと、
「どういうことですか?」
低いトーンで輪の中に入って来たのは和臣。
「確認しておきたかったんだ」
「何を?」
「…この事件は、根が深いよ」
瀬田の小さな呟き。
「話が有る」
そう言って東條は本棚の間に挟まれている扉を開いた。
「小西は佐伯と白河に任せておけばいい、津島も付いてるから」
生徒会室と扉1枚で続きになっている8畳ほどの部屋はミーティング用なのかホワイトボードに長机、それにパイプ椅子が10程並べられていた。
部屋に入ったのは東條、瀬田、和臣、郁、美都の5人。
和臣以下3人は促されてそれぞれ適当な席に着く。と、
「黙ってたことは謝る、俺達は初めからそのつもりで小西を呼んだんだ」
「どうして言っておいてくれなかったんですか?」
東條は真面目に頭を下げたが、それだけでは納得出来ない和臣の反論。
あれでは優也が可哀相だ。
「知っていれば連れて来なかっただろう?」
睨んだ郁の視線を軽く受け、
「実際はもう少しゆっくりと思い出させるつもりだったんだが、橘達の話が聞こえたからね。あれを使わない手はなかった」
すまなそうな表情を見せる。
「優也のネクタイだったんですね?」
後ろに居た5人には小声のやり取りは聞こえず、目に映る状況でしか判断できていない。
「確かにあれが小西の物だという可能性は高いんだけど、彼が脅えたのは目に見えた物じゃないよ」
瀬田の言葉に3人が視線を向ける。
「視界が塞がれていても残る五感が潜在的に憶えていたんだ」
「匂い…?」
瀬田は頷いて、
「それと、声」
優也の耳元で囁いた何か。
「何と言ったんですか?」
「SERAPHIM」
東條の発音が良すぎて上手く聞き取れず、顔に疑問符を浮かべた3人へと、
「セラフィムと言ったんだ」
カタカナ読みで発音されても、やはり聞き覚えの無い単語だった。
「天使の名前だよ」
「…天使?」
「自分達のことを天使だとでも思ってるんだろう」
吐き捨てるよう言葉を切った東條に、
「正確に言うと階級の名前、天使最上位のこと」
補足したのは瀬田。
「ふざけた奴等だ」
「確かにね」
美都の呟きに瀬田は少し口の端を上げる。
「だけど頭は悪くない。あの赤い布切れはどこででも手に入る物だったし、結局所在の掴めなかった生徒や教師の中にも断定できるような奴は浮かばなかった。せめてあの指輪が何か手掛かりになるといいんだが…」
20金のリング全体に凝った装飾が施され、中央にはルビーがはめ込まれていた。
「赤に拘る理由って」
「赤はセルフの象徴なんだ。セラフィムと複数形で名乗るのは彼ら全員を指しているのか、グループ名にしているのか」
「グループ…って何人くらいの?」
「さぁね、5、6人は居ると思うけど…」
「だけど良く分りましたね。匂いのことといい、その…セラフィムのことといい」
当然の疑問を投げ掛けた美都へと、
「よく似た事件が昔あったんだ」
溜め息交じりに東條が呟いた。
「2年前の事件…ですね?」
和臣の言葉に頷く東條。
「小西とよく似た綺麗な瞳をしてたのに…、助けてやれなかった。友人だったんだ、俺達の」
溜め息の意味を理解する。
「あいつ等のやり口はね、1回遊んだだけじゃ済まないんだ。最初の現場を撮影して、それをネタに何度も貪り食う。一度引きずり込まれたら…」
瀬田は重く瞼を閉じ、
「地獄から抜け出せない」
「こんなところ見られたら怒られちゃうね」
優也は仰向けに真っ直ぐ天井を見上げている。寝転がっているのは机の上。
「せっかくの穴場なのに鍵貸して貰えなくなるよ」
優也の隣で郁は小さく笑った。
そう思うなら止めればいいものを…
大胆にも先に閲覧用机に這い上がったのは優也の方なのだ。
…いうまでもなくここは図書館の5階・特別室。
「寝てていいよ」
あくびをかみ殺した郁へと優也が視線だけを向けた。
「昼休み終わりそうになったら起こしてあげるから」
「大丈夫だよ」
せっかく2人っきりの貴重な時間を寝て過ごしたくない。
「でも、最近郁くん疲れてるみたいだし」
「体力には自信が有るんだ」
言ってはみたものの…精神面でも疲れていた。
“十中八九、録画されていたことは確かだな”
友人のレイプビデオを見たという東條に返す言葉など無かった。
それが元で東條達の友人は今、夢の世界をさ迷っているという。
最後まで言葉にはしなかったが東條が当時その友人に特別な想いを寄せていたことは想像が付いた。
大切な想い人を犯し続けた犯人が再び姿を現したのだ。例えそれがほんの僅かな手掛かりだったとしても、喉から手が出るほど欲しかったに違いない。
無理をしてまで優也の記憶を引き出させたのはそういうことなのだ。
立場が逆なら郁も同じことをしていただろう。
あの時どこまでの行為をされたかは郁には知りようが無いが、そんな奴等に優也の髪の毛一本でも触れられたのだと思うと気が狂いそうになる。
それも映像に残してそれを見ている奴がいるなんて…。
更に気掛かりはそれだけでは済まない。
“宣戦布告”
郁にネクタイを返してきた意味を瀬田はそう解釈した。
もう用済みという意味にも取れなくはないが和臣達のガードが有るにもかかわらず、わざわざ手を出したのだ。
例の事件から2年振りに。
“色々なことに拘りを持ってるみたいだから簡単には諦めないと思う”
いつまた手を出すか分らない。
しかも今度はもっと上等手段を使ってだ。
“橘、大切にしすぎて見失うことが有るってこと憶えとけよ”
最後に言った東條の言葉が重く胸にのしかかった。
……
「…くん」
声に郁が瞼を開くと心配そうに優也が覗き込んでいる。いつぃの間にか寝入ってしまっていたようだ。
「昼休み終わり?」
郁の問い掛けに優也は違うと首を振った。
「もうちょっと有るけど…少しうなされてたから」
不安そうに見つめる優也に、
「巨大文献に押し潰される夢だったかな」
笑顔を向ける。
余計な心配は掛けさせたくはない。
「こんなとこで寝てるから祟られたね」
答える優也の瞳にはいつもの輝きが戻っていた。
あの限りなく透明に近い輝き。
この瞳をもう二度とあんな色にはさせたくはない。
いや、…させない。
「僕も最近よく夢見るんだ。…あんなことが有ったからかな、変な夢見たりしてさ」
「早く忘れてしまえ」
「うん…。でも、郁くんも夢に出て来たんだよ」
郁が肘を付いて少し上体を起こすと、机に足を伸ばして座っている優也を少し見上げる形になった。
「あの日の夜に見た夢なんだけど…」
強姦未遂事件の夜のこと、あれからもう半月。
「郁くん泣いてた」
視線を窓の外に飛ばして呟いた。
「変だろ? いつも泣いてるの僕の方なのにね」
視線を逸らしたままの優也の横顔を郁は黙って見つめる。
…多分それは夢じゃない
「郁くんが可哀相で、抱き締めてあげたくなって手を伸ばそうとしたんだけど…結局届かなかった」
「それは、残念だったな」
優也はあれ、といったふうに視線を郁へと戻した。
「ホントにそう思う?」
「ああ」
「今もそうしたいと思ったんだけど」
一瞬動きが止まった郁の仕草に、
「ごめん、変なこと言ったね」
照れたように俯いた優也。
…気付いたんだろうか
「いいよ、そうしてくれて」
その言葉で弾かれた視線を真っ直ぐに郁は受け止めた。
やっと…、手に入る
優也は郁の瞳をしばらく見つめた後ゆっくりと腕を伸ばし、そしてふわりと郁を抱き込んだ。
腕の中で聴く優也の鼓動。
緊張が伝わる。
「郁くん…」
背中に回される優也の腕は僅かに震えている。
そして、
「好きだよ」
…ずっと
欲しかった言葉
全身に染み渡るよう郁は瞳を閉じた。
しばらくその余韻に浸っていたい。
………
短い静寂が流れ、優也の鼓動が静まった頃、
「驚かないんだね」
ポツリとした呟き。
「……」
「…もしかして知ってた?」
腕の中で郁は笑う。
「なんだ…」
優也は溜め息をひとつ。
そんな優也を郁は引き寄せながら机に仰向けになった。
顔にかかる優也の髪を両手で掻きあげてやる。
「俺のことは知ってる?」
問い掛けに何がと優也は軽く首を傾げた。
「どう想ってると思う?」
嫌ならこんなことはしないだろう。
「…好き?」
見上げる郁は首を小さく横へと振る。
「ふつう?」
答えに小さく吹き出すと、優也は少し不機嫌な顔になる。
郁は少し頭を持ち上げて口元にそっと唇を合せた。
「愛してるが正解」
短いキスと言葉に優也はしばらくその瞳を見開いて、
「違うの?」
この雰囲気にそぐわない言葉でまじめに尋ね返した。
せっかくの告白とファーストキスだと言うのに有り難味の無い奴だ。
「字がね」
郁の悪戯っぽい答えに、かなり不満そうな表情を見せた優也は、
「真面目に訊いてるのに」
「真面目にキスしたのに」
初めて頬を赤く染めた。
羞恥で身体を離そうとした優也を今度は郁が抱き寄せる。
「ずっと傍に居ろよ」
見失ってしまわないように、ずっとその手を引いていてやるから…
作:杜水月
ホーム > 小説 > 某学園シリーズ本編 > Angel eyes
ご意見・ご感想・ご質問等は 杜水月 まで。
当サイトの無断転載はご遠慮ください。
![]()