bewitched
<1>
「つまりそう言うことになったんだ」
「そう。何となく予感はあったから…、仕方がないわね」
彼女は少し寂しげに俺を見上げると、
「やぁね、そんな顔しないでよ。私平気だから」
「でもお前の気持ち考えると」
「いいの、私のことなんて。私は一人でも大丈夫」
「本当に申し訳ない…」
「二人の幸せ祈ってるわ」
「有り難う、君のことは一生…」
っと、そこでとうとう俺は吹き出してしまう。
次いで白河も爆笑。
「どこから話が逸れたんだっ」
「知らないわよ、もう!」
やってらんない
とか言いながら目に涙まで溜めている。
今日は1学期最後の日
佐伯と両想いになってから半月ばかり過ぎた頃だ。
俺と白河はいつもの定位置、教室の一番後ろの窓にもたれて立っていた。
長年佐伯に片思いをしている白河に事後報告をしていたのだ。
わざわざ知らせる必要も無いのではと思うだろうが、これは彼女との約束事。
どちらかが佐伯と付き合うことになれば隠さずに報告をする、という同志間での協定だったのだ。これで関係が拗れるような仲でもない。
「それにしても、よく告白できたわねぇ。絶対言えないと思ってたけど」
やっと落ち着いた白河の言葉に、
「何となくね、そんな雰囲気だったんだ。OK出るとは思ってなかったが」
言いながらあの日の夜のことを思い出し、つい頬が緩む。
「やぁね、思い出し笑いなんかして」
「ごめんごめん」
「随分楽しそうじゃん」
突然会話へと割って入って来たのは吉野だ。
部活は違うが同じ中学だった縁で今でもつるんでいる。
「よぉ、はよっ」
「お早う、吉野くん」
白河の満面の笑みに目を輝かせながら、吉野も精一杯の笑みで白河に微笑み返した。
ふむ
吉野も白河シンパだったんだろうか?
「それにしてもお前ら朝から仲いいな」
「そうか? いっつも、こんなだぜ」
「白河、親衛隊に何も言われないのか?」
白河は肩を竦めて見せ、
「森丘君は別格みたいね」
「男前は特だよなー、まったく」
「そんなんじゃないよ」
「そうそう違うの、このサド目に近寄って来れないだけ」
シレッと言う白河に、
「おっ、お前そういうこと言うか」
首を絞める真似。
「きゃー、だって本当のことだもん」
ふざける俺達を呆れ顔で吉野が眺める。
「ほんと、お前らが付き合ってないって不思議だよ」
…これについては佐伯にも指摘されていた。
初めは俺と白河が付き合っていると思っていたらしいのだ。
彼女が佐伯に想いを寄せていると知っておきながら、そういう発想が浮かぶというのは俺にはどうも良く解らないのだが…。
それにしても男の恋人に女の友人とは奇妙な取り合わせだよ、まったく。
人生って判らないものだ。
などと考えている最中、不意に白河の視線が逸れた。つられて俺と吉野が視線を向けた先に居たのは…
佐伯だ
いつも通り教室に入ってきた佐伯は俺を捜す仕草などおくびにも見せず、ごくごく自然に自分の席に着いた。
途端に傍へと歩み寄る佐伯の友人達。
いくら付き合い始めたからとはいえ、お互いに今までの友人関係を反故にするわけにはいかない。試験前の一件もまだ尾を引いているのだ。
その上、野球部の連中が俺達の仲を好き勝手に憶測し始め出したものだから、最近は帰りにマンションに寄ることすらままならなくなっている。
実際あの後、佐伯に会えたのは3回くらいか。
…どうも釈然としない
ずっと近くなったはずの佐伯が、反って遠くなってしまったような…。
「そういや、森丘。佐伯とも噂有ったよな」
思い出したような言葉についまじまじと吉野を見てしまった。
高橋と違って深い意味は無いだろうが…
「噂は噂よねぇ」
と、いいタイミングで白河の助け船。
「まぁね。でも俺、佐伯ならいいかなーなんて」
「えっ?!」
思わず目がマジになった。
「睨むなよ、噂だけなんだろ? だってあいつ仮面の下は滅茶苦茶綺麗じゃん」
「仮面って…」
言えてるが。
「俺、美形だったら何でもいいんだ」
「なんだそりゃ」
「だから白河も好きだし、森丘も…鑑賞用には問題ないかな」
? どうして俺だけ、
「観賞用?」
「ああ、だって見てる分には森丘だって目の保養になるけどさ。やっぱ抱くには佐伯とか6組の小西とかじゃないと、どっちがどっちとかで揉めそうだろ。俺そんなにガタイ有るほうじゃないし」
開いた口が塞がらないとはこのことだ。
ボヤッとした顔でいつもそんなこと考えてやがったのか、こいつはっ。
しかしこの発言は大いに問題だぞ。
佐伯に対して同じこと考えてる奴がいないとは限らないのだ。
今までは一途に思っているだけだったが、いざ手に入れてしまうと嬉しさの反面、無くしてしまうんじゃないかという不安も抱かないわけにはいかない。
「…でも、何か男いるんじゃないのかな」
ちょっとドキっとする。
「どうして?」
白河のさり気ない問い返し。
「だって俺こないだ見たんだ、佐伯が俳優みたいな男前と一緒に歩いているところ。それもなんかちょっと意味ありげでさ、肩なんか抱かれちゃってて…」
………
呆然としている俺の横顔に白河の視線が刺さる。
“誰?”
そんなこと知るわけが無い。
無言のまま俺が重く頭を振った時、
「おーい、そろそろ講堂行こうぜ」
何時の間にか傍まで来ていた高橋が俺達に声を掛けた。
終業式の間中、ずっと俺の頭は佐伯のことで埋めつくされていた。
…知らないことが多すぎる。
付き合い始めてたったの2週間。
お互い知り得る情報なんて限られているはず…と、どんなに自分に言い聞かせてみても、俺が知らない情報を白河ならまだしも吉野が知っていることが許せなかった。
だったら電話ででも聞けば済む話なのだが、それが出来ない原因は悲しいことに俺自身の事情に有った。
あれは1ヵ月ほど前のこと…
リビング脇でグローブの手入れをしていた俺の傍へと静かに腰を落とした母親に、
「言いたいことは、分かるわね」
携帯電話の支払い明細を差し出されて言葉が無かった。
さすがに親の脛をかじっている身で、この金額の意味するところは良く分かる。
素直に携帯電話没収に応じた俺。
だったら自宅の固定電話を使えばいいのだが実家が商売をしている都合上、夜の私用電話は厳禁なのだ。
となると学校で捕まえて訊いてみるのが一番手っ取り早いってことになるか。
苛々しながらHR終了を待ち構え佐伯を呼び止めるべく視線を向けた時には既に佐伯は戸口に差し掛かっていて、口を開いた時にはもう俺の視界に佐伯の姿は無かった。
何だよ一体…
途方に暮れてしまった俺の背中に、
「後でゆっくり確かめればいいじゃない、恋人なんだから」
慰めるような白河の声。
「それくらいのことで動揺しないの」
「そう、だな」
「周りなんて気にしないで帰り寄ってみれば?」
言葉に頷いて、
「そうするよ」
俺の返事にフフッと白河は笑顔を向けるとお迎えの親衛隊を横目に、
「じゃあ、いい夏休みを」
魅惑的なウィンクを投げかけて帰って行った。
<2>
そして、その日の夜
「美都っ、電話!」
風呂から上がると清兄の声。相手は言われなくても分った。
郵便受けに“連絡欲しい”とメモを入れておいたのだから。
「野郎相手に長話は厳禁だぞっ!」
叫ぶ清兄からトランクス1枚で受話器を奪うと保留ボタンを押し、
「向こうに聞こえるだろ!」
小さく怒鳴って2階に駆け上がると、子機の受話器を取る。
「もしもし、俺」
『こんばんはぁ』
「悪かったな、電話させて」
『ううん、別にいいんだけど。今大丈夫だったかな?』
「平気、ゴメンな。気ぃ遣わせてばっかで」
『それは仕方ないよ』
「ところでさ、今日どっか行ってた?」
部活の帰りに部屋へと寄ってはみたが留守だった。
『うん、実は今帰ったところ』
って、あれからずっと?
「HRの後もダッシュで帰っただろう、何か急用でもあったのか?」
『…うーん、急用って訳じゃないんだけど…』
なんとなく言いたくなさそうな口振りだ。
「友達か何か?」
『って言うか…』
ふと吉野の話が頭を過ぎる。
『…そんなところかなぁ』
「明日、マンション寄ってもいいか?」
『部活の帰りに?』
「そう」
『いないからダメ』
「明日も出かけるのか?」
『ちょっとね』
隠しごとをしているのは明白だ。
「一日中?」
『うん、この時間までいないと思う』
「何かやってるのか?」
『秘密』
「誰かと会うんだ?」
『ひみつー』
「おい」
『気になる?』
「当たり前のこと訊くなっ!」
茶化す口振りに苛々して、つい怒鳴ってしまった。
『あはは、森丘ってホント短気だね』
人の懸念を知ってか知らずか軽い口調の佐伯にカチンと来た。
笑って流せば済むことなのに、どうしてこんなに腹が立つんだ。
『…ごめん』
返事の無い俺に佐伯が小さく謝る。
それでも俺は黙っていた。
『森丘?』
「…いいよ、別に」
投げやりな口調。
俺ってなんて心が狭いんだろう
『声、怒ってるよ』
「苛々してるからね」
『ごめん、そんなつもりじゃなかったんだけど』
「短気なんだ」
『またそうやって開き直る、性格悪いよ』
「じゃあ嫌いになれ」
苛々しているのは自分に対してだ。些細なことに振り回されている自分に腹が立つ。
『…なれないこと知ってるだろ?』
「知らねぇよ!」
だけど怒りは収まらない。
『森丘…』
「お前は何も言わねぇだろ!」
『ちょっと、どうしてそんなに…』
「肩抱かれて歩いてた男って誰だよ! そんな奴の話、一度もしたこと無かったじゃないか!」
『…何の話を』
「美都! タイムオーバーだっ!」
いきなり部屋の戸が開いて清兄が怒鳴り込んで来る。
「うるさいっ!」
勢いで怒鳴った俺の言葉に清兄は目尻を吊り上げた。
「なんだと、てめぇ! 俺に楯突こうなんて10年早いわっ!」
タンスの上に有った置物を投げつけられて、
「危ねぇだろ! 今大事な話してんだよっ! 大体年上だと思ってなんでもかんでも言う通りになると思ったらっ…て、うおっ!」
思いっきりタックルされてベッドに吹っ飛ばされた。ついでに受話器も奪われる。
「もしもし、悪いがまた今度にしてくれ」
ピッ!
何と言うことを…!
怒鳴りたいが脇腹の衝撃がかなり堪えて声が出ない。
そんな俺を清兄は横目で睨み付け、
「お前の長電話のせいで顧客に逃げられたらどうすんだっ!」
怒りながら部屋を去って行ってしまった。
それはこっちのセリフだっ
彼氏に逃げられたらどぉすんだよ!!!
<3>
その後の数日間は悲惨なものだった。
初めの1日2日は色々なことに腹が立っていたせいで、仏頂面に磨きがかかり先輩までもが恐れおののくほど機嫌が悪かった。
もちろん佐伯からの連絡は無い。
3日目午後辺りから徐々に平常心を取り戻し自分がいかに馬鹿げたことをしたかを深く反省した。
意を決してマンションを訪ねても留守。
己の愚に気がつくとこれはもう止まるところを知らず果てしなく落ち込んでしまい音信不通も重なって、4日目以降からはもうぼろぼろの精神状態。
佐伯の部屋は相変わらずの留守続きだ。
もしや居留守を使われているのでは…と疑心暗鬼に陥ってしまうと電話も掛けられなくなってしまった。
声まで聞けなくなって今日で何日経っただろう。
そして 10日目の夜。
「具合でも悪いのか?」
夕飯もそこそこに部屋にこもってしまった俺を気遣って正兄が部屋にやって来た。
猪突猛進・単純直情型、超体育会系の長男清兄と違い正兄は随分と落ち着いた性格をしている。人の行動の変化にも聡かったりするのだ。
「別に…」
俺は取り敢えずベッドから起き上がるとそのままあぐらを掻き、
人と話す気分じゃない
と言った風に短い髪を掻き上げて俯くと自然に溜め息がこぼれる。
「彼女に振られたか?」
痛いところを突かれて即座に正兄を見上げてれば肯定したも同じだ。
まだ振られてもいないし、彼女でもないけど…。
「ふぅん…最近電話してなかったからおかしいとは思ってはいたけど、そういうことになってたとはね」
言うと正兄は勉強机の椅子に静かに腰掛けた。
「よっぽど好きだったんだ」
「まだ好きだよ」
正兄はあれ? といっふうに目を開いて、
「落ち込んでるところ見ると、すっぱり振られたか?」
俺は首を振る。
「どういうことだ?」
「喧嘩してうやむやになってしまって…、原因作ったのが俺だから連絡もでいない。きっと嫌われてしまってるよ、勢いだったけどひどいこと言ったし」
「ちゃんと両想いだったんだろ?」
「多分…」
自信が無い。
「多分って…。そういう話、してないのか?」
「したよ」
「相手は? ちゃんと返事してくれたのか?」
「うん」
正兄は優しい目で笑った。
「だったら自然消滅なんて勿体無いことするな。そんなに好きならちゃんと会いに行ってやれ、向こうだって待ってるんじゃないか?」
どうだろうか。
「付き合い始めで意志の疎通がうまくとれてないんだろ? そういう時はどっちが悪くても男の方が折れてやるもんだ」
うむむむ…
どう解釈したものやら。
「自分が悪いと思ってるんならウジウジ悩む前にきっちり頭下げてこい。落ち込むのはそれからでも遅くないだろう」
そうか!
途端に目の前の霧が晴れたような気がした。
そうだ、悩んでないでちゃんと話せば済むことだ。この前電話くれたぐらいの時間なら家に居るはずだろう。佐伯は嫌いになれないと言ってくれたじゃないか。会ってちゃんと謝って、それから誤解を解こう。
俺は勢い良くベッドから飛び降りる。
「元気になったか?」
微笑みかける正兄にガッツポーズを作ってみせると、
「今から行ってくるよ」
パーカーを掴んで部屋を出た。
<4>
勢いよく飛び出たものの、いざ部屋に着いてみると佐伯は留守。
やはりどこかに行っているのだろうか?
だとしても、こんな時間まで…
悪い方向へと思考が走ろうとするのを頭の中で揉み消してしながら、取り敢えずマンションのエントランスまで引き返した。
さてどうしたものかと悩む間も無く、そこに据付けられていた長椅子が目に入り迷わず腰を下ろす。
意を決してせっかくここまでやって来たんだ。あっさり帰りたくは無い…な、絶対。
後ろの壁に体重をかけると、見るでもなく泳がせた視界の中に僅かな光。廊下側のガラス戸から覗いているのは冴えた三日月だ。
佐伯に告白したあの夜は確か綺麗な満月だったな。
欠けて見えようが満ちて見えようが月はいつだって確かにそこにあるように、佐伯の気持ちがどうであれ好きで居続けたい。と、そう思って告白したはずだったのに…。
俺は静かに目を伏せた。
…これ以上考えるのはよそう
どれくらいそうしていたか…
マンションの前で車の止まる音。
初めは気にも留めていなかったのだが、微かに漏れてくる声に聞き覚えがあって壁から背中を離しながら視線を向けた。
ここから唯一見える運転席の窓が開き、そこから身を乗り出した男が後方から来る人物を目で追っている。
恋愛ドラマで充分主役をはれるくらいの色男。
もしかして吉野が言っていた男だろうか…。
するとまるでそれを肯定するかのように、扉の横に現れたのが佐伯。
運転席の男が何かにこやかに話しかけた後、身を屈めた佐伯に唇を寄せ…
――呼吸が、止まる。
体温が一気に下がったような戦慄が身体の芯を貫いた。
知らず握り締めた拳が小さく震えている。
目の前が真っ暗になって…
…欲しかった、現実として。
実際には立ち上がって目を大きく見開いたまま、俺はその光景を茫然と直視していた。
佐伯の頬から唇を離した運転席の男が俺の視線に気付く。
少し訝しげな表情で視線を佐伯へと戻し、もう一度俺を見やる。その視線で佐伯が振り返り、
硬直――
運転席の男が心配げに何か話しかけたようだが佐伯の反応は無い。
この場から早く立ち去りたかった。
が、マンションから出るにはあの車の前を通らなければいけないのだ。
振り返ったまま身動き一つしない佐伯を見ていると怒りより辛くなってきた。
本気で泣きたい気分を味わったのはもう何年振りだろう…
とにかく怒りであれ悲しみであれ今ここで佐伯達に涙は見られたくなくて、ゆっくりと俺は視線を逸らすと熱くなる喉に唾を流し込みそれでもようやく足を前に出した。
すると、それに弾かれたように佐伯が駆け出した。
それも俺に向かってだ。
意味が分からず首を傾げようとした途端いきなり俺の胸へと飛び込んで来た佐伯に、
え?
と思う間もなく佐伯は腕の中で顔を上げると、両手で俺の頬を包み込み、
「さ…」
「今の勘違いしたね、そうだね、そうだよね?」
らしくなく、すごい勢いで尋ねられ、
「え、っと…」
「全部話すから、何でも話すから…ちゃんと説明するから」
佐伯の涙声。
「だから怒らないで…、この前みたいに突き放すなっ」
言って俺の胸に顔を埋めた。
「佐伯…」
「こんなのもうやだよ」
掠れた声で呟いた佐伯の背に腕を回した。
「佐伯」
頬を佐伯の髪に埋めて呟く。
「信じていいのか?」
腕の中で頷いた佐伯は大きくしゃくりあげた。
<5>
「こんばんはぁ」
声に顔を上げるとマンションの入り口にはさっきの色男、ともう一人。
かわいらしいと表現すると失礼な年だろうが、それでも何か小動物を思わせるような…子供が似合いそうな、線の細い青年が並んで立っていた。
佐伯の知り合いなのは間違いない。
気まずく俺は頭を下げる。と、
「愛されてるねぇ」
色男の意味深な笑いで急に今の状況を自覚して赤面。
背中に回していた手で佐伯の肩を軽く叩き、
「佐伯、ちょっ…と」
耳元に小声で囁いた。
にも係わらず、佐伯はまったく離れる気配が無い。
弱ったぞ…
「森丘美都くんだよね」
にこやかに話し掛けてきた細身の青年へと、
「はい」
取り敢えず佐伯をこのままにして返事をした。
どういう訳かふたりは今の状況をあまり気にしていない様子で、
「はじめまして、長谷川圭吾と申します」
まず色男の方が手を差し出してみせる。
俺が戸惑っている間にその隣へともう一つほっそりとした綺麗な手が並び、
「滝沢伸弘です」
流されるまま右手を差し出し二人と握手を交わした。
手が離れる瞬間、細身の青年・滝沢さんの小さな含み笑いに何だろうかと視線を向けると、
「いや、ゴメン。翠くんは随分な面食いだったんだと思って…」
隣で大きく頷く色男、は確か長谷川さんで、
「しかも長身で身体も締まってる感じだ…っと、外見ばかりを褒めるのも失礼か。成績がいいことは翠君に何度も聞かされてるから俺達にとっては今更ってところがあってさ」
ははは
などと世慣れた笑顔を向けられたって返事に困る。
大体佐伯とはどういう…
「美都くん」
っといきなり名前を呼び掛けられて戸惑いながら滝沢さんに視線を移した俺へと、
「やっぱり翠くん何にも話してないんだ」
少しあきれ気味な滝沢さんの呟き。
ピクリともしない佐伯に視線を置いたまま、やれやれと肩を竦めた滝沢さんは、
「翠くん。離れたくないのは分るけど、そういうことは人目の無い所でしようねー」
まるで子供を諭すような口振りだ。
が、それでも反応の無い佐伯に、
「取り敢えず場所変えるか」
長谷川さんの提案。
ようやくこの状況をどうにかして貰えると思ったのに、意外にも二人揃ってエレベーターの方にさっさと歩き出してしまった。
エレベーターのボタンを押したことを確認した俺は仕方無くもう一度佐伯に話し掛けてみる。
「佐伯。ほら、エレベーター来るぞ」
それでも佐伯は離れない。
「ここじゃ話もできないだろ? 説明してくれるんじゃなかったのか? ん?」
目一杯やさしい口調で言ってみる。
エレベーターの扉が開くのが目の端に入り、
「ずっとこうしてても仕方がないぞ」
けれど首に回された腕に更に力を入れられて…。
「…そうか、そう言うつもりなら」
言うなり少し身体を屈めた俺は右腕を佐伯の膝の裏に回し入れ、
「しっかり持ってろよ! っと」
そのまま佐伯を抱き上げた。
「おおっ!」
喚声はエレベーターの二人のものだ。
そして、
「ちょっ! ちょっと…!!」
ようやく佐伯が顔を上げたがもう遅い。そのままふたりの待つエレベーターへと乗り込んだ。
「若さだねぇ」
感心感心と長谷川さんの言葉に次いで、
「いいなー、翠くん」
またまた子供に喋りかけるよう、にこにこ笑いながらの滝沢さんの言葉に、
「こらっ、降ろせ! ちゃんと歩くから!」
佐伯は耳まで真っ赤にして小さく怒鳴った。
もうこの際、無視を決め込むつもりでいる俺の腕の中で無理に身体を捩るものだから、
「暴れんなっ、結構重いんだ」
つい反撃。
「じゃあ降ろせよっ」
「佐伯が離れないからだろ、自業自得だ」
「人のせいにするな!」
「お前のせいだ!」
「絶対違うっ、いつも勝手に怒り出すのはそっちじゃないか」
「原因は佐伯に有る」
「僕は何もしてないだろ!」
「喧しいっ!」
言いながら重さでずり下がってきた佐伯を振り上げるようにもう一度担ぎ直した途端、
「うっわ!」
驚いてしがみついてきた佐伯。
「大人しくしてないと本当に振り落とすぞっ」
横目で睨みつけて今度こそ佐伯を黙らせた。
向かいのふたりがニヤニヤと笑っている。
あぁ…
初対面の人間の前でなんということだ。恥ずかしすぎるぞ。
ようやく7階に到着したエレベータから揃って降りると鍵を手にしているのは何故か滝沢さんだった。
不思議に思いながらも玄関でやっと佐伯を降ろしてやる。
拗ねてるのか照れてるのか…、俺の顔を見ないまま最初に扉を潜ったのは佐伯。促されて中に入った俺に次いで滝沢さん、そして最後に長谷川さんが扉を閉めた。
さほど広くも無い廊下に男4人が入るとさすがに窮屈さを感じる。
どやどやっといった感じでリビングに入るなり佐伯と、そして滝沢さんがまるで当然のように台所へと向かった。
いかにも勝手知ったる我が家…といった滝沢さんの行動にまた疑問符が浮かんだが、長谷川さんに背中を軽く押された俺はそのままソファーへと直進。
「美都くんお酒いけるんだよね」
ソファーに座るなり話し掛けられて慌てて返事をする。
「圭吾は? 何飲む?」
「ビールでいい」
返答しながら俺の斜め前に腰を下ろした長谷川さんは、
「美都君、結構酒強いらしいね」
言いながら端正な笑顔を浮かべポケットから皮の名刺入れを出した。
そしてそこから抜き取られた名刺を差し出され、取り敢えず軽く頭を下げながらの俺は手に取った名刺の文字を確認。
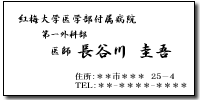
裏にはローマ字で同じ内容が印字されていた。
お医者さんか…
確かに色男では有るが嫌みでないのは、その内に知的さと品の良さを兼ね備えているからだ。
「翠君とは伸弘を通しての友人でね、俺は海外生活が長かったものだからさっきのキスも挨拶代わりなんだ」
誤解なんて解けてしまえば何てことはない。
吉野が偶然見かけたと言う、肩を組んでたって場面も多分そういうことなんだろう。
「何か俺が原因で喧嘩になったらしいね、結構責任感じてるんだが…」
俺は首を横に振る。
「俺が悪かったんです、どうも思ってた以上に短気みたいで」
長谷川さんはクスリと笑った。
「本気で惚れてるとそうなるよね、特に若いと。おまけに翠君は恋愛未経験者のようだから、不器用すぎて見てるとハラハラするよ」
「そ…うなんですか?」
そんな話すらしたことが無かった。
「美都君と電話で喧嘩した次の日なんて、ものすごい顔してたんだよ。顔パンパンに腫らして…一晩中泣いてたんだろうな、きっと」
「それって…」
信じられない言葉だ。
「その癖に意地はって自分からは連絡しない、会いにも行かないと言うし…。ここ数日、翠君の低気圧にどれだけ俺が迷惑被ったか」
呆れた笑みを浮かべながらの長谷川さんだったが、
「…だけど」
とそこで僅かに表情を変え、
「最後まで俺達に泣き付いてはこなかったな」
何とも理解しがたい微笑みで長谷川さんは俺に視線を向けた。
「もしかすると娘を取られた父親の気分に近いのかもしれないなぁ。嬉しさと寂しさが入り交じって複雑な心境なんだが、さっきの二人のやり取り見てたら何か素直に納得してしまって…この際思い切って翠君は君に任せることに決めた」
って言われたって…
「あの」
そもそも保護者のつもりでいるのなら、同性愛という関係に抵抗を持っていいようなものじゃないか。
だがしかし、その答えは直ぐに判明することになるのだ。
「何の話?」
グラスとビールを乗せたトレイをテーブルに置きながら話に割って入った滝沢さんは、
「息子をよろしくって話」
言葉でへぇと納得の面持ちで長谷川さんの横に腰掛けグラスを俺に手渡すと、
「ふつつかな息子ですが、今後ともどうぞ宜しく」
などと言いながらビールのプルトップを引き俺のグラスに注ぎ始める。
「息子じゃないだろっ!」
次いで俺の横に腰掛けた佐伯が不機嫌丸出しで残りのグラスを乱暴にテーブルへと置いた。と、
「何を今更…。俺達の可愛い可愛い息子は翠君以外にいないじゃないか」
言いながら滝沢さんの肩を引き寄せる長谷川さん。
およよ…
「人前でそういうの止めてくれないかな」
「マンションの入り口で抱き合ってるよりは普通だと思うんだが」
からかわれて再度真っ赤になりながらの佐伯は腹立たしげに自分のグラスに独酌。それを横目に更に長谷川さんは、
「箱入り息子も手を離れたことだから今夜は次の子作りにでも専念しようか」
などと言われてしまっては、いくらなんでも二人の関係を認識せざるをえなくなった。
そういうことだったのか。
どおりて俺達のことに寛大なわけだ。
で、それを機にと言うかなんと言うか。
その後の二人のいちゃつき具合ときたらもう…。見慣れている佐伯ですら呆れるほどだったのだから、俺に関しては刺激が強すぎたのは言うまでもない。
結局その後二人が帰るまで俺達は散々毒気に当てられる羽目になった。
「森丘、お風呂入ってきた?」
少しバツが悪そうに言った佐伯のそれだけの言葉に、なにやら妙に動揺してしまう。
やはり原因は長谷川さんに有るのだ。
“美都君これ”
二人が帰る間際、不意に俺は呼び止められ返事をするより先にポケットに何かが滑り込む。
何だろうと思い、こそっと覗き見たそれは…
いわゆる潤滑剤。
“初めは絶対有ったほうがいいから”
唖然とした俺に平然と顔を寄せ、続けた言葉が、
“痛がるとは思うが、まぁ愛があれば乗り切れるって”
言い置くとぎゅっと俺を抱きしめて去って行ってしまった。
晴れやかな笑顔で手を振られたところでどうしろというのだ、まったく。
俺が風呂から上がり、次いで入った佐伯がさっぱりして出てきても答えは出ない。そりゃ確かに抱きたいのはやまやまなんだが…。
ソファーに深く腰を落とし思い悩む俺の目の前へと佐伯が何やら包みを差し出した。
?
何だろうと俺の横に座った佐伯に視線を向けると、
「少し早いんだけど…。誕生日おめでとう」
照れくさそうに微笑んでみせた。
…言われてみれば
一連の騒動ですっかり忘れてた、自分の誕生日を。
「開けてみて」
佐伯の言葉に促され感動しながら包みを開ける。
中身を確認して更に感動が募った。
携帯電話だ
「これでゆっくり話せるだろ? 通話料も僕が持つから」
「いや、そこまでは」
けれど佐伯は首を振り、
「そのためにバイトしてたんだ、圭吾さんの知り合い紹介してもらって」
それで留守だったのか。
「早く渡したかったからちょっとバイトの時間無理したんだけど。…どうしても親の小遣いでは買いたくなかったから」
「佐伯…」
「それに」
俺の言葉を遮りながら佐伯は傍の鞄を探り、
「ほら、お揃い」
取り出したのはやはり携帯電話。しかも同じ型の色違いだ。
「これで、いつでも捕まるし」
捕まえられる。
言い終わらないうちに俺は強く抱きしめていた。
「ごめん、俺…」
どうして佐伯の気持ち、疑ったりしたんだろう。
「ありがとう、だよ」
腕の中で笑う佐伯の唇を軽く塞ぐ。
そして、小さく何度も口付け。
「さえ…」
呼び掛る途中、そっと唇に触れた細い指。
「名前で呼んで」
囁きは耳のごく近くで、
「名前がいい…」
掠れた声にゆっくりと陶酔感に浸りながら俺は瞼を閉じた。
「翠…」
初めは呟きに似た声で、
「あきら」
少し色を含んで囁いてみる。
「…あきら」
甘く、甘く…
その唇で耳の後ろ、髪の生え際からうなじを辿って今度は無声で呼んだ。
翠は僅かに身体を震わせ俺のシャツをきつく握る。その反応にそそられて身体の芯がジワリと疼きだした。自制しようと軽く首筋に歯を立てると、翠に小さく声をたてられて失敗。
どうしよう…
「俺、…やばいかも」
熱い吐息混じりについて出た言葉。
本当に無理だ。
…異常に感じてる。
そのまま体重に任せて翠をソファーに押し倒すと、深く深く唇を重ねた後、
「…いいよ、…僕も、美都…欲しい」
呟いた翠をジッと見つめた。
「ベッド、行く?」
問い掛けで頬を染めて頷く翠に小さく口付けた俺はいったん身体を離す。ソファーから立ち上がると翠を抱き上げるつもりで振り返ったのだが思惑に反して何故か翠も立ち上がっていた。
そして、
「タオル…取ってくる」
短く告げた翠は俺から目を逸らすとリビングを出て、どうやらバスルームへと向かったよう。
何をしに…?
と俺は意図を計り兼ねつつもこれ幸いと言った感じで、パーカーのポケットから長谷川さんからの贈り物を手に寝室へと向かう。目につかない場所にそれを忍ばせると軽くベッドに腰を掛け翠を待つことほんの1,2分。
程なく寝室にバスタオルを持って俯きながら翠が入って来た。
「何だ、それ?」
翠は答えずに掛け布団を剥がすとバスタオルをふわりと大きく広げて見せて、
「翠?」
「…汚すから敷いといたほうがいいって…、伸弘さん言うから。……シーツは別にいいんだけど…敷布団はちょっと困るかな、なんて…」
言葉に驚いてしまったが、しどろもどろに説明する翠が可愛くて強く引き寄せた。
つまりは二人共けしかけられてたということだ。
今思うとあの子作り宣言も俺達に対する挑発行為だったのかもしれない、親だなんだと言いながらとんでもない大人達だ。
で、その後の行為はよく憶えていない…
と言うと大嘘付き呼ばわりされそうなので要所だけ付記しておこうと思う。
初めは色々と考えていたのだが直ぐに興奮しきってしまった俺は、情けないことに手順も何も有ったものじゃなかった。
すっかり意識の殆どは夢の彼方へ飛んでいたんだから。
あまりにも翠が綺麗で、可愛くて…。
俺自身セックスは初めてではなかったが、こんなに感じたのはやはり相手が翠だからだろう。片や翠に関してはキスも俺とが初めてだったのだから当然そういう行為も初めてなようで、囁く度触れる度に戸惑いの表情を浮かべた。
けれどそれは嫌悪ではなく、むしろ未知の快楽への戸惑い…。
頬を高揚させきつく瞼を閉じ細くまつげを震わせる。唇を噛んで理性と羞恥心と戦いながらも翠は一度も俺を拒まなかった。
それは行為の最後に至ってもまた然り。
腰を進める度、無意識に漏れる呻き声があまりに辛そうで途中何度も辞めようとしたのだが翠がそれを許さなかった。やっとの思いで挿入し終えた俺に向かって、翠は満足げに目を細め汗に濡れた俺の髪を両手で掻き上げる。
朦朧とした表情でキスをせがんだ翠に応えてやった後、
「…愛してる」
翠の掠れた甘い囁きで、苦労して一つになった甲斐無く俺はあっさりイッてしまった。
だが落ち込む間もなくせがむように翠に爪を立てられ、そのまま翠もイかせてやるとその震える吐息がゆっくりと俺の呼吸と重なり始め、何か不思議な共鳴感が胸を支配する。
それは心も共に重なり合ってる…
と、本気でそう信じたくなるような不思議な感覚だった。
<6>
―――翌朝
電話の音で目が覚めた。
俺の腕の中で覚醒はしているようだが一向に動く気配の無い翠に、仕方なく枕元の受話器へと手を伸ばす。ついでに時計を見ると6時半を過ぎたところだ。
こんな時間に電話をしてくるのは多分…
「…はい」
『おはよー』
この男にしては高めの声は滝沢さんだ。
「お早うございます」
『ふぅん…美都くんが最初に出たということは、そういうことなのかなぁ』
含み笑いで言われてしまっては返す言葉が無い。
赤面している俺の様子など分るはずも無く、何か向こう側で音がしたなと思っていると
『おはよう、美都君』
今度は打って変って低いトーンの声で話し掛けられる。もちろん言うまでもなくだが長谷川さんの声だ。
俺はもう一度朝の挨拶を返しながらも電話の向こうの景色を軽く想像していた。
二人の距離感と時折何かが軋む様な物音が混ざるのは…。
多分相手もベットの上か。と、
『上手くいった?』
いきなり単刀直入な質問に、
「…と言われても」
困るのだが…。
『良かった?』
あぁ、どうしてそうストレートにこういうことが訊けるかなぁ。
『…返事が無いのはどう解釈したものやら』
からかうように言われてつい、
「ご心配なく、滅茶苦茶良すぎて言葉では語り尽くせません!」
受話器の向こうで揃って爆笑されたのが分った。
スピーカーで聞いてやがったな。
するとそこでようやく翠がゆっくりと手を伸ばし、
『それはそれは…』
そこまで聞いた所で奪われた受話器。
「もしもし」
言いながらの翠は穏やかな笑顔を俺に向けている。
視線を俺に置いたまま何やら応対している翠の髪に軽く口付け。
そしてそのままゆっくりと額に唇を移し唇は今チョット無理…だから受話器を持つ手の指にキス。受話器からの声が聞こえる位の至近距離で鎖骨に舌を這わせてみると、
「…大じょ …、っ!」
小さく体を震わせて応対の声を乱す翠。
ここもいい所か…インプットしとかなきゃ。
などと思いながら顔を上げると翠に睨まれてしまった。
「うん、じゃあまた」
早々に会話を打ち切った翠に受話器で軽く頭を叩かれる。
「ばれたじゃないか! 馬鹿」
苦情に俺は悪びれもせずにその受話器を枕元に置き直し、
「最初っからばれてたぞ」
翠を抱き込んだ。
「昨夜のことじゃなくて今のことだよ、朝から元気だとか言われただろっ」
「でも、本当に元気そう…」
言ってそっと翠の中心を握ってみせると今度ははっきりと身体を震わせ俺の胸に顔を埋めてしまった。男の生理現象なのだから当然のことでは有るのだが、それでも嫌とは言わない翠が愛しくてしょうがない。
「身体、大丈夫か?」
「どう…だろ。わかんない」
胸の中で小さく呟いた。
電話に気を取られていて気付かなかったが、僅かな動作や仕草を見れば翠が普通の体調でいられるはずが無いことは直ぐに分った。
「シャワーしよっか、俺洗ってやるから」
笑いかけながら当然のごとく部活を休む決心をした。
そしてシャワーの後は再びベッドの上の住人と化す俺達。
翠は体調こそ悪そうだったが機嫌はすこぶる良く、昨夜の約束通り俺の疑問を全て取り除いてくれた。
今ここで一人暮らしをしている事情も伊達ではないがああいうセンスの悪い眼鏡をしている理由も、滝沢さん達がどうして保護者代わりにならなければならなかったかも(春先まで翠と同居していたのは滝沢さんだった)…元を辿れば翠の母親・佐伯みどりの失踪が原因となるわけだ。
テレビドラマのような翠の身の上話に一々唸らされる俺だが、それ以外にこの日驚きの事実を聞かされることになった。
それは何かの拍子で誕生日の話題になった時のこと。
「翠、誕生日いつ?」
なんと俺は翠の誕生日を知らなかったのだ。
白河と二人して3ヵ月間片想いをしてきたわりには何とも情けない話では有るのだが…。
「11月30日」
「ふぅん、何座?」
などと言いながら危うく聞き流しかけてふと気がついた。
「俺、誕生日の話しなんかしたっけ?」
翠の細い髪で遊んでいた手を止めて問い掛けてみる。すると悪戯っぽい目で見上げる翠。
「話して…無かったよなぁ」
記憶の何処を探してもそんな会話をした覚えが無い。同じクラスなのだから本気で調べようと思えば出来なくはないが、わざわざこっそり調べなければならない理由が無いじゃないか。
付き合い始める前に翠が俺に好意を持っていたとか…
まさかね。
すると、
「美都に教えてもらったんだよ」
それは意外な答えだった。酒飲み過ぎた時も記憶が途切れるところまではいってなかったはず…
「言った記憶が無いんだが」
小さく翠は笑った。
「聞いた訳じゃないんだけど」
聞いてない?
「でも俺が教えたんだろ?」
「美都は知らずに教えたんだから、憶えてなくてもしょうがない」
「どう言うことだ?」
少し不満気に俺が睨むと翠は肩を竦めてみせた。
「気付いて欲しくなかったんだけどなぁ…」
「翠」
隠しごとはもめごとの原因。
ばれてしまったのなら白状させるしかない。
翠は観念したように溜め息をつくと、
「あのさ、梅雨頃に富樫に頼まれて僕一日だけバイトしたことが有るんだ」
「…ふ、ん?」
「正確には富樫のお姉さんに頼まれたんだけどね。お昼頃から夕方まで座ってればいいだけだって言われて…あんまり頼み込むものだから、なんだか良く分らなかったけど引き受けたんだよ」
「富樫の姉さんって何してたっけ?」
「OL兼、占い師」
…占い師?
「全身真っ黒の服着せられて街角に座らされて恥ずかしいったら…。お客さんが来たらどうするんだと思ったんだけど、ああいうのって意外に来ないものなんだよね。あからさまに怪しい格好してたからかもしれないけど…」
え…?
真っ黒の服? 街角に座ってた?
当然の如く俺の脳裏に過ぎるものがあった。
「一日中雨は降るし、服は暑苦しいしでウンザリしてた時に…」
腕の中で俺を見上げながら翠は不適の笑みを浮かべる。
「思い出した?」
回答拒否。
「美都にはそれまでひどい目に遭わされてたからね、これくらいの冗談は洒落のうちかと思って声かけたんだ」
衝撃の真実とはまさしくこういうことだ。
「てっきり白河と付き合ってると思ってたから、美都が書いた名前見て驚いたの何のって。最初気付かれたのかと思ったんだけど、まじまじと見ても美都大真面目だったし…」
翠は少し頭を上げると唇の端にキスをくれた。
気まずく見やった視線の先では澄んだ眼差しを向ける翠が居て、
「僕あの時に美都のこと好きになったんだよ」
「…え?」
驚き混じりに小さく問い返す。
「人を好きになるのに理由なんていらない、って言っただろ。あの言葉聞いた時、なんだか頭の上で教会の鐘が鳴ったような…、そんな気分だったんだ。親に捨てられてから自分自身にずっとコンプレックス持ってたから、僕は母親にすら愛してもらえないような何の価値も無い人間なんだって」
翠は痛みに少し眉を顰めながらも肘をついて軽く上体を起こし、
「だから無条件で好きだと言ってくれたことがすごく嬉しかった。初めて他人に全部認めてもらえたような気がしたんだ」
覆い被さるように唇が重ねられる。
「美都はまだあの時同性ってことにこだわってたけど、周りにそういう人が多かったからかな、僕はそれに対して抵抗が無かったからね。待ってても言ってくれそうに無かったから僕からモーションかけた」
まったく気がつかなかった…いったいいつ?
そんな俺の気持ちを読んだかのように翠は続ける。
「あの日すでにそれらしいこと言っただろ? って言っても憶えてないかな。相性がいいだとか、告白してみろだとか…大体名前だけで性別まで分るわけ無いじゃん。取りあえずいい方向に考えて欲しかったから、勝手なこと並べ立てといて、後日対策を練ろうと思って…」
何かますます信じられないぞ。
「だけど美都の気持ち知ってた分、きっかけを作るのは簡単だったかな」
身体を起こしたままの翠が少し辛そうで、俺はゆっくりと突いていた肘を外して翠を横にしてやる。代わりに俺が翠を見下ろす体制になった。
そうしながら過去を回想してみる。
きっかけと言えば…
「嵐の時?」
翠は口の端で笑ってみせた。
「でもあれのどこが…」
「学級日誌つけてたら美都が顧問の所に寄って行くって話してるのが聞こえてきてさ、僕も鍵と日誌を戻しに職員室行かなきゃならなかったからそれなりにタイミング見計らって戸締まりしたんだ」
あれは偶然じゃなかったんだ…。
「後は成り行きに任せたんだけど…雷はちょっと意表を突かれたかな、あれが無かったら結構いい雰囲気になってたのに」
にしても、
「気持ち知ってたんなら、翠から言ってくれればよかったんだよ」
翠は首を振った。
「美都からちゃんと僕に言って欲しかった。同性でも好きだって言って欲しかったから…」
ゆっくりと柔らかい頬を撫ぜてみる。
「でも夏休み終わるまで、なんて待ってられなかったからまた家に呼んだ。あの日告白してくれなかったから毎日でも誘うつもりだったんだよ」
「大胆なんだな」
「…早く、もっとって。近くなりたくて」
募るのは愛しさばかりだ。
「一日だって待っていられなかった、美都に告白されてからずっとずっと欲しかった…。昨日まで僕がどんな想いでいたかなんて分かってないんだろう?」
伸ばされた白い腕が俺を抱き込むように絡み付く。
まるで誘うような翠の激白に、今日はなんとか納まっていた欲望が目を覚ました。
そのまま今朝憶えた翠の性感帯に唇を寄せると、
「ん…っ」
漏らした小さな喘ぎ声に、
「…その声、好きだな」
甘い声で翠への侵略開始。
姿勢を変えるたび、眉間にしわを寄せる翠に、
「今日は無理させないから…」
告げた俺へと恍惚の瞳を向けた翠は首を横へと振った。
「いいよ好きにして…美都がいいならそれで…」
後は瞼を閉じて淫靡の縁へとまた意識を飛ばして行く。
きっと一生離れられない
そんなことを考えながら俺もまたその縁へと落ちて行った。
作:杜水月
ホーム > 小説 > 某学園シリーズ 本編 > bewitched
ご意見・ご感想・ご質問等は 杜水月 まで。
当サイトの無断転載はご遠慮ください。
![]()